「働きがいは、生きがいに通じる」
データの会社が真摯に「従業員の声」を集める理由
データアナリティクスラボ株式会社
代表取締役社長 近藤雅彦 様
更新日 2025.07.162025.07.15
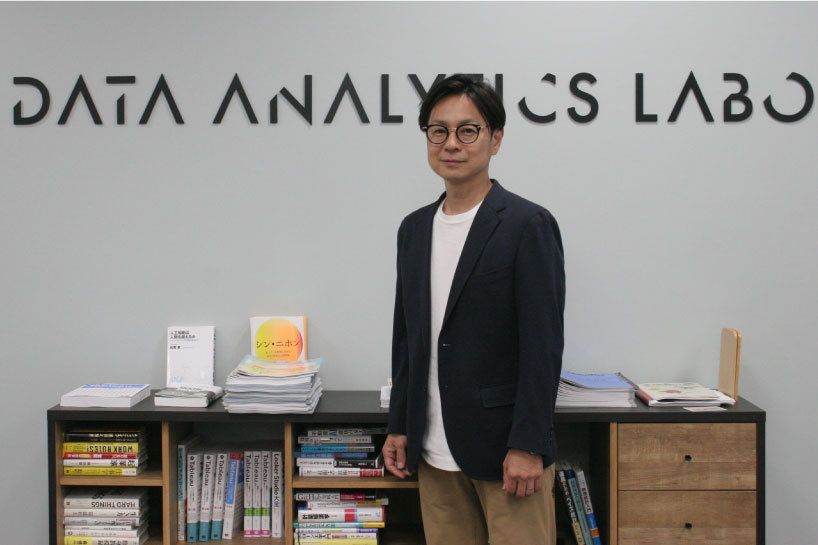
「働きがいは、生きがいに通じる」
データの会社が真摯に「従業員の声」を集める理由
データアナリティクスラボ株式会社
代表取締役社長 近藤雅彦 様
データアナリティクスラボ株式会社は、急成長するAI・データサイエンス分野で、データ分析とデータサイエンス教育の「民主化」を推進する企業です。従業員が挑戦と成長を楽しめる環境づくりに注力し、「働きがいのある会社」認定も取得しています。なぜ同社がGPTWの「働きがいのある会社調査」を実施しているのか、そして調査結果や認定をどのように活用しているのか。代表取締役社長の近藤様と人事担当の河野様にお話を伺いました。
<抱えていた課題>
✓働きがいのある職場づくりを進めるために、現状の可視化が必要だった
✓事業が急成長する中で、従業員一人ひとりがどんな気持ちで働いているのか確認したかった
<導入の決め手>
✓調査機関としての「社会的認知度」 が高く、安心して利用できると判断した
✓働きがいを可視化できる信頼性の高い指標で、現状把握に最適だった
GPTW 御社の事業概要とその特色を教えてください。
近藤様 かつてデータサイエンスは、一部の大企業や専門家だけに手の届くものでした。私は「これでは日本の経済や社会全体がデータ活用を推進できない」と常々感じており、データサイエンスの「民主化」を掲げて会社を立ち上げました。
我々は単なる分析結果の提供にとどまらず、お客様の課題を深く理解し、その解決策まで一緒に考え、実装・運用まで支援しています。お客様の意思決定を「このデータをどう活かすか」という観点から支え、寄り添う姿勢が現場で評価されています。価格面でもデータサイエンス のハードルを下げ、高品質なサービスを適正価格で提供することで、民主化を進めています。
社外向けのデータサイエンス人材の育成も当社の大きな柱の一つです。理系の専門職に限らず、文系や未経験者でもスキルを身につけ、ビジネス現場で活躍できる人材を育てることを目指しています。現在、従業員数は180名を超え、その約9割がデータサイエンティストです。理系・文系問わず多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。
GPTW 御社にとっての働きがいの位置づけを教えてください。
近藤様 私は仕事とは、人生そのものだと思っています。なぜなら、人生の大半を仕事に費やすからです。だからこそ、仕事の中で働きがいがあるかどうかは、人生の充実度を大きく左右します。
もしその時間が楽しくなく、やりがいを感じられないのであれば、それは「人生自体が楽しくない」ということにつながってしまいます。経営者は、従業員の人生の多くの時間をあずかっている立場です。だからこそ、働きがいを高める環境を整えることは、経営者としての責任であり、不可欠な使命だと考えています。
GPTW 働きがいのある会社調査に参画したきっかけを教えてください。
河野様 働きがいのある職場づくりを進めるために、まずは現状を可視化したかったからです。社内アンケートも不定期で実施してきましたが、人事や経営の目線だけでは見えにくい課題もあります。特に会社の成長が早かった分、従業員一人ひとりが今どんな気持ちで働いているのかを改めて確認したかったのです。
近藤様 数あるエンゲージメントサーベイの中でGPTWを選んだのは、その「信頼性」と「社会的認知度」の高さが決め手でした。GPTWは世界中で実績があり、働きがいを可視化する指標として信頼されていますし、認定されれば対外的にも「働きがいのある会社」であることを示せます。私たちはデータサイエンスの会社として「データドリブン経営」を大切にしているので、信頼できる評価軸を持つ調査を選びたかったのです。
GPTW 働きがいを高めるために、具体的にどんな取り組みをしていますか。
近藤様 まず、従業員の成長を後押しするために、資格取得支援制度を整えています。データサイエンスや統計検定、など、業務に関連する資格を積極的にサポートし、取得すれば評価や報酬に反映します。従業員が自分のスキルアップを実感できることが、働きがいにつながると考えています。
次に、従業員同士のつながりを大切にするカルチャーづくりです。データサイエンスの会社は個人作業が多い印象がありますが、私たちは「研究室のように学び合える空気」を重視しています。部署横断で部活動や勉強会を開き、週に1回ほどテーマも自由に参加できる仕組みを整えています。これが、一緒に挑戦できる仲間づくりにつながっています。
三つ目 は、経営層と従業員の距離を近くする取り組みです。これはGPTW調査で判明したことですが、会社の成長に伴い、経営の想いが従業員に届きにくくなっていました。全社会議や懇親会などの場を通じて、会社のビジョンや戦略をしっかり届け、「自分たちがどこを目指して働いているのか」を実感してもらえるようにしています。
GPTW 働きがいのある会社調査を通じて、気づきはありましたか。
近藤様 当社は1クライアントにつき1名の専任担当制を基本とし、お客様のビジネス課題に深く寄り添い、最適な提案や実装支援を行っています。一般的な企業に比べると従業員同士が同じのオフィス空間で交流する機会が少なくなるケースもあるため、横のつながりを心配していましたが、予想以上に従業員同士のつながりが強いことが分かりました。社員が気軽にコミュニケーションを取れるよう、オフィス環境の整備を進めてきたことや、未経験から入社した人材が多く、常に新しいことにチャレンジする風土が根付いていることが、大きな要因となっています。当社の強みを再認識できたことは、非常にポジティブな気付きとなりました。
一方で、会社の成長に伴い、経営層の想いが従業員に十分に届ききっていない課題も見えてきました。そこで、従業員の9割近くが参加するBBQイベントなどに私も積極的に参加するようにし、直接従業員の声を聞いています。従業員からも「リアルで話すと安心感がある」といった声が寄せられ、こうした場の大切さを改めて実感しているところです。
河野様 従業員が「会社がどういう方向性を目指しているのか」を知りたいと感じていることが分かり、その課題を深掘りするために全従業員アンケートを実施しました。オフィス環境や働き方、コミュニケーションについて意見を集め、「ホワイトボードを増やしてほしい」「集中スペースが欲しい」といった声をすぐに実現。経営層のメッセージもSlackやリアルイベントを通じて直接届けるようにしています。また、やりっぱなしにならないよう、取組や改善活動について定期発信をしていくことも大切にしています。
近藤様 やはり、アンケートを取るだけで終わらせず、スピード感を持って行動に移すことで、従業員の満足度や会社の成長につながると確信しました。
GPTW 「働きがいのある会社認定」をどのように活用していますか。また、どのような効果を感じていますか?
河野様 まず、社内向けには、Slackや社内報、などで「働きがいのある会社に認定されました」と発信し、社員が自社に誇りを持てるようにしています。社外向けには、採用ページやコーポレートサイト、SNSなどにGPTWの認定ロゴを掲載して、「働きがいのある会社」であることをアピール。候補者の方にとっても、外部機関から認められていることで、安心して応募してもらえるきっかけになると思います。実際、面接でも「働きがいのある会社に選ばれているのですね」と話題になることもありました。
近藤様 認定をいただいたことは、ある意味、良いプレッシャーにもなっています。働きがいの認定を取って終わりではなくて、従業員アンケートを通じて課題を深掘りして、具体的に改善につなげていく動きが加速したのは、この認定制度があったからこそです。
GPTW これから働きがいを高めていきたい企業に向けてのメッセージをお願いします。
近藤様 まずお伝えしたいのは、「働きがいは、生きがいに通じるもの」だということです。従業員にとって会社で過ごす時間は人生の大半を占めます。その時間が楽しくなく、成長や挑戦を感じられないのは、つまり人生そのものを楽しめないということだと思うのです。だからこそ、私は「働きがい」を、制度や福利厚生だけではなく、「自分が挑戦できているか」「成長できているか」を実感できるかどうかで捉えています。
そしてこれは、個人だけの問題ではありません。従業員一人ひとりの「働きがい」を支えることは、経営者にとって重要な使命です。とはいえ、経営者としては事業を円滑に回すことが最優先事項となり、「働きがい」はどうしても後回しになりがちです。つい重い腰が上がらず、気づけば手つかずの宿題のようになっていることも少なくありません。この機会にぜひ、「後回しの宿題」に取り組んでみるのはいかがでしょうか。


