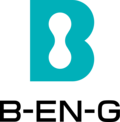「働きがいのある会社」認定がOKRの成果指標
各部署が主体的に組織改革に取り組む風土をつくる
ビジネスエンジニアリング株式会社
代表取締役・専務取締役 別納 成明 様 経営統括本部 人事総務部 副部長 福澤良彦 様
更新日 2025.10.082025.08.01
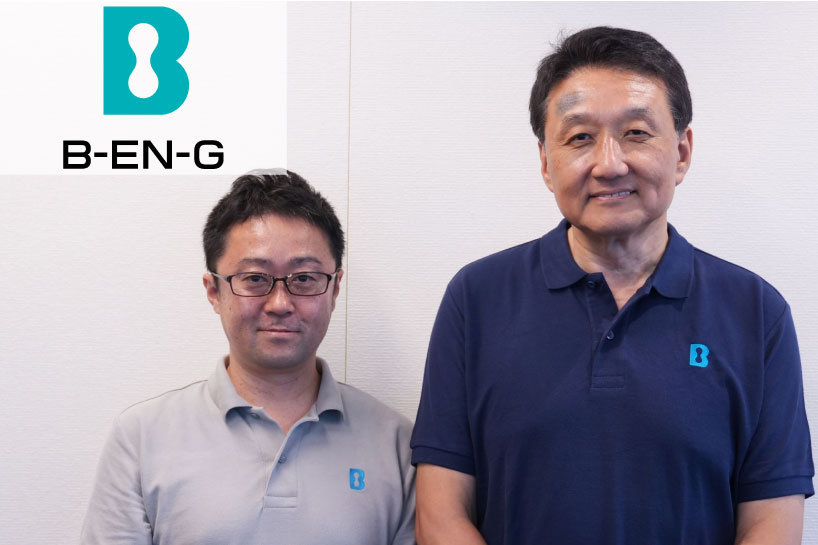
「働きがいのある会社」認定がOKRの成果指標
各部署が主体的に組織改革に取り組む風土をつくる
ビジネスエンジニアリング株式会社
代表取締役・専務取締役 別納 成明 様 経営統括本部 人事総務部 副部長 福澤良彦 様
製造業を中心にITサービス・製品を提供する企業として、ERPを中心とした業務改革支援を長年にわたり手がけてきたビジネスエンジニアリング株式会社。「人がすべて」という価値観のもと、OKRの目標に「社員が誇りを持って働ける会社となること」を掲げる同社は、なぜ「働きがいのある会社」調査に着目し、組織改革に活用しているのか。代表取締役・専務取締役の別納成明様、経営統括本部 人事総務部 副部長 福澤良彦様にお話を聞きました。
<抱えていた課題>
✓エンゲージメントサーベイを実施していたが、社内での主観的評価に留まっていた
✓取り組みを通じた「働きがい」の実現度を測る成果指標を模索していた
<導入の決め手>
✓認定・ランキングによる客観的な評価で、自社の立ち位置を把握できると感じた
✓OKRの成果指標に「働きがいのある会社」認定取得を位置づけることとした
GPTW 御社の事業概要とその特色を教えてください。
別納様 当社は、「製造業のためのIT」を軸に、長年にわたりものづくり企業の課題解決を支えてきました。特に、ERP(基幹業務システム)を中心とした業務改革の分野での実績と専門性を持っています。

私たちの強みは、単なるITベンダーではないということ。ITの仕組みを提供するだけでなく、「製造業をよく知るITパートナー」として、現場の業務プロセスや課題に深く入り込み、本質的な改善提案ができることが差別化のポイントです。
私たちは創業当初から製造業一本に絞ってきた結果、生産管理やサプライチェーンマネジメントの領域において、他社にはないノウハウと経験値を蓄積できています。IT技術と製造業の業界・業務に関する知見、そしてモノづくりの現場を理解する力。この3つを掛け合わせることで、複雑化する製造現場の課題に対して、最適なソリューションを届けることが私たちの役目です。
GPTW 御社にとっての「働きがい」の位置づけを教えてください。
別納様 私たちのような製造業向けのシステム導入や業務改善の仕事では、社員一人ひとりの知見・創造力・対応力が直接的に価値を生み出します。つまり、人こそが最大の経営資源であり、競争力の源泉です。
なかでも私たちは、製造業のサプライチェーンや生産管理に、深く入り込む専門性を大事にしています。そのためには、社員一人ひとりが「相手に言われたことをやる」のではなく、「自ら考えて、相手の立場を思いやって、行動する」ことが求められます。そのような主体的な行動は、強制では決して生まれません。やはり、「もっとやりたい」「もっと良くしたい」という内発的な意欲、言い換えると「働きがい」が原動力になると考えています。
「働きがい」があるからこそ、社員が楽しんで仕事に取り組み、結果としてクライアントに高い価値を提供できる。つまり、社員の「働きがい」が、そのまま会社の力になるわけです。
GPTW 「働きがいのある会社」調査に参画したきっかけを教えてください。
別納様 当社では、OKRという目標管理のフレームワークを導入しており、その中で掲げているObjectives(目標)の一つが、「社員が誇りを持って働ける会社となること」です。
この目標は、単なる理念ではなく、私たちの経営の中核をなすものです。社員一人ひとりが誇りを持って日々の仕事に向き合えるような組織だからこそ、持続的な成長も、顧客への高付加価値提供も実現できると考えています。
そして、このObjectivesに対して、具体的なKey Result(成果指標)として設定したのが、「働きがいのある会社」認定の取得でした。
福澤様 これまでにも私たちは、エンゲージメントサーベイを通じて、社員の声を継続的にモニタリングしてきました。部署ごとのスコアを全社員が閲覧できる透明性の高い仕組みを構築し、エンゲージメント向上に取り組んでいます。
ただしそれは、あくまで社内での主観的な評価に留まる側面もありました。だからこそ、「働きがいのある会社」認定・ランキングのような社外からの客観的な評価を通じて、自分たちの取り組みがどの位置にあるのかを把握したかったのです。結果として認定を得られたことは、私たちの取り組みに対するひとつの「外からの証明」になったと思います。
一方で、「働きがいのある会社」調査を行ったことによる新たな気づきもありました。私たちは以前からエンゲージメントサーベイを通じて、組織ごとの課題や傾向を把握しており、同規模・同業界の利用企業の上位10%程度にあたるエンゲージメントの高さを維持していました。しかし、「働きがいのある会社」調査のスコアと、中規模部門のランキング上位企業のスコアを照らし合わせてみると、想定よりもギャップがあることが分かったのです。特に従業員一人ひとりの「仕事との向き合い方」に関する部分で、伸びしろがあることがわかりました。
GPTW 「働きがい」を高めるために、具体的にどんな取り組みをしていますか。
福澤様 弊社では、エンゲージメント向上を目的とした様々な取り組みを行っています。全社的な取り組みとしてまず挙げられるのは、経営層からの情報発信の強化です。全社員向けに、経営方針や中期経営計画、業績の進捗などを丁寧に説明しています。これまでは管理職を対象としていた情報共有の場を全社員に開放することで、会社全体の透明性と納得感の向上を図っています。
働く環境の整備も重要な施策の一つです。社員の声をもとにオフィス改革を実施しました。会社主導での単なる設備改善にとどまらず、「どんな職場にしたいか」を社員自らがタスクフォースを組んで考え、実現していくプロジェクトとして進めました。オフィス改革以外にもこうしたタスクフォースを多数作り、社員の自発性や参画意識を育てる貴重な機会となっています。

また、各部署が自分たちで課題を定義し、行動を起こしているのも当社の取り組み姿勢の特徴です。たとえば、各ライン長を中心に、半期ごとに部署単位でアクションプランを策定・実施する仕組みを整備し、取り組みの成果や進捗は全社で共有される体制を構築しています。これにより、部署間で互いに刺激を受けながら改善が進む風土が育まれています。
具体的なアクションの例を挙げると、1on1やワークショップといった定期的な対話の場を設け、形式的な会話にとどまらず、信頼関係の構築や価値観のすり合わせを重視しています。なかには独自のミッション・ビジョン・バリューを策定した組織もあります。加えて、全社員が全部署のエンゲージメントスコアの変化を閲覧できることで、相互の刺激と自律的な改善サイクルが生まれています。
GPTW 「働きがいのある会社」認定をどのように活用していますか。
別納様 先ほどもOKRの取り組みについてご紹介しましたが、私たちは「働きがいのある会社」認定をただの称号ではなく、「働きがい」の実現度を可視化する「成果指標」としての意味を持たせています。
OKRに加えて、サステナビリティ経営の一環としても「働きがいのある会社」認定を活用しています。今後はESG(環境・社会・ガバナンス)や統合報告などでも積極的に紹介していく方針です。
 さらに「働きがいのある会社」としての認知拡大を目的に、プレスリリースやWebサイト、そして採用ページなどの各種チャネルで情報発信を行います。特に採用においては、「社員がやりがいを持って働ける会社」であることを裏付ける信頼性のある証明として、この認定の活用を進めているところです。
さらに「働きがいのある会社」としての認知拡大を目的に、プレスリリースやWebサイト、そして採用ページなどの各種チャネルで情報発信を行います。特に採用においては、「社員がやりがいを持って働ける会社」であることを裏付ける信頼性のある証明として、この認定の活用を進めているところです。
そして、今回は「働きがいのある会社」認定の取得をOKRの指標にしていましたが、次回以降は「働きがいのある会社」ランキング上位30〜40位に選ばれることをひとつの道標としつつ、社員一人ひとりが自社に誇りを持ち、主体的に仕事に向き合う環境を整えていきたいと考えています。
GPTW これから働きがいを高めていきたい企業に向けてメッセージをお願いします。
別納様 「働きがいを持って働くこと」が従業員一人ひとりの成長や、プライベートにも良い影響を与えるというのは、どの企業にも共通する考えだと思います。
ただ、それをどう実現するかは会社ごとに異なるのではないでしょうか。業界の特性、組織の規模、カルチャーによっても取り組み方はさまざまで、たとえば、私たちのように各部署の自発性を重視してボトムアップで進める方法もあれば、会社全体で方向性を合わせて、トップダウンで一体感を持って進めるスタイルもあるでしょう。
どちらが正しいということではなく、その会社の目的や文化に合ったやり方を、柔軟に設計し、地道に続けていくことが大切だと思っています。それぞれの会社が自社に合ったスタイルで、粘り強く、継続的に取り組んでいくこと。そうやってエンゲージメントを高め、結果的に「働きがい」を育んでいくのだと思います。