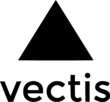「働きがい改革」で採用難時代に立ち向かう
MVV経営×地方IT企業の挑戦
株式会社ベクティス
代表取締役 曽我部 壮様
更新日 2025.09.102025.09.10

「働きがい改革」で採用難時代に立ち向かう
MVV経営×地方IT企業の挑戦
株式会社ベクティス
代表取締役 曽我部 壮様
東京と島根を拠点に日本のDX人材不足の解消を目指す株式会社ベクティス。モダンな技術を駆使した開発力と、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を軸にした組織づくりで成長を遂げてきました。地方のIT企業として存在感を発揮している同社がなぜ、「働きがいのある会社」調査に着目し、組織改革に取り組んでいるのか。代表取締役 曽我部 壮様にお話を聞きました。
<抱えていた課題>
✓自社カルチャーや働きやすさを客観的に伝え、求職者に安心感を持ってもらいたい
✓社内の雰囲気やMVVの浸透度について全社員の本音をもとに客観的に把握したい
<導入の決め手>
✓「働きがいのある会社」認定を得ることで、採用活動における信頼性を高め、候補者の不安を払拭できると感じた
✓社員の声を数値やコメントとして可視化し、組織課題の把握と改善アクションの設計に活かせると考えた
GPTW 御社の事業概要とその特色を教えてください。
曽我部様 私たちベクティスは、「島根から日本のDX人材不足を解決する」というミッションのもと、エンジニアの育成とモダンなWeb開発を主軸に事業を展開しています。拠点は東京と島根(出雲・松江)の3か所ですが、島根のメンバーが大半を占めています。
 React(Next.js)やTypeScript、Ruby(Ruby on Rails)、Python、AWSなど、モダンな技術でWebサービスやSaaS、ECサイト構築を行っています。一般的なSESや受託開発、ニアショア開発とは異なり、100%自社オフィスで島根の開発拠点においてチームでアジャイル開発を行います。要件定義から設計、開発までをチームで行うことにこだわり、地方にいながらも成長実感の得られる開発環境を提供しているのが強みです。単にプロダクトをつくるだけでなく、社会的意義のある開発を大切にし、全国規模で価値あるサービス開発を提供し続ける組織を目指しています。
React(Next.js)やTypeScript、Ruby(Ruby on Rails)、Python、AWSなど、モダンな技術でWebサービスやSaaS、ECサイト構築を行っています。一般的なSESや受託開発、ニアショア開発とは異なり、100%自社オフィスで島根の開発拠点においてチームでアジャイル開発を行います。要件定義から設計、開発までをチームで行うことにこだわり、地方にいながらも成長実感の得られる開発環境を提供しているのが強みです。単にプロダクトをつくるだけでなく、社会的意義のある開発を大切にし、全国規模で価値あるサービス開発を提供し続ける組織を目指しています。
また、地方でも面白い技術ややりがいのある開発をしたいエンジニアはいます。そういった場を提供し、地方創生、社会貢献をしています。
GPTW 御社にとっての「働きがい」の位置づけを教えてください。
曽我部様 「働きがい」は、会社づくりの中心にあるテーマです。私は独立するまでに、大手SIerやWeb制作会社、大手インターネット広告会社、スタートアップなど合計5社で勤務し、職種もエンジニア、ディレクター、プロデューサー、新規事業責任者など幅広く経験してきました。企業の規模や業種、立場を問わず働いてきたからこそ、様々な会社の良い面、悪い面を理解できました。その中で仕事の充実度を大きく左右するのは人間関係や職場の雰囲気だと痛感しました。やる気のない上司、飲み会で愚痴と悪口ばかりが出る職場では、どんなに仕事が面白くても充実感は得られません。逆に、飲み会やランチが活発でお互いの仕事の工夫を語り合ったり、自然と助け合える文化がある会社もありました。
また、私自身、キャリア初期は「自分がやりたい仕事につけない」「成長を実感できない」といった状況があり、何度も転職を繰り返しました。だからこそ社員には、可能な限り希望する領域で、成長を感じながら働ける環境を提供したいという思いがあります。
仕事の時間は人生の大部分を占めます。社員にも、ただ仕事を"こなす"のではなく、働く中で成長や充実を感じ、前向きな気持ちで働いてもらいたいと思っています。そのために会社の方針やプロジェクトの内容、育成の仕組みのすべてが「社員の成長とやりがい」に結びつくよう注力しています。
GPTW 「働きがいのある会社」調査に参画したきっかけを教えてください。
曽我部様 調査に参画した理由は2つあります。1つ目は、採用活動において対外的な信頼を得たかったからです。私たちはMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)に基づいた経営をしている自負がありますが、面接の短時間でその文化を十分に伝えるのは難しく、客観的な認定があれば候補者にも安心してもらえると考えました。
2つ目は、社内の実情をより客観的に把握したかったからです。職場の雰囲気はいつも良好であると感じていましたが、社員が本当にどう感じているかを「見える化」する手段として調査を活用したいと考えたのです。実際、調査結果を見てみると、全体のスコアは高く、これまでやってきたことが間違っていなかったと確認できたのは大きな成果でした。
GPTW 「働きがい」を高めるために、具体的にどんな取り組みをしていますか。
曽我部様 私たちは、これまでも「文化」を重視した取り組みに力を入れてきました。特徴的なのは、年に数回行う全社員参加の合宿。1日かけてMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や重要な経営テーマについて語り合う場です。例えば「挑戦とは?」「成長とは?」「チームワークとは?」といった当社の価値観を題材に1日集中型のワークショップを行い、社員一人ひとりが自分の言葉で解釈し、共有することで、MVVを自分ごととして考える土台をつくっています。
合宿をきっかけに、勉強会やイベントなどが社員発案で動き、役職や年齢を問わず自由にチャレンジできる風土が育っています。

また、私ができる価値観の実践として、合宿で決めたことですが、社員の目線を高め、価値観を浸透させるため、MVVに関係する考え方を毎週Slackで投稿しています。具体的には、私が好きなビジョナリーカンパニーの書籍、ピーター・ドラッカーやアンソニー・ロビンスの言葉、ビジネス書の実践知などを引用し解説します。
その投稿と合わせてアンケートを添えて、「この一週間でどんなMVVに繋がる行動を取れたか?」「誰のどんな行動がMVVを体現し、素晴らしかったか?」などを振り返ってもらいます。月末の締め会では価値観に沿った行動を発表し、表彰も行いますが、「仲間の良さを見つけて言葉にする」こと自体が、ポジティブな組織文化をつくっていると実感しています。
さらに「働きがいのある会社」ランキングのトップ常連だったコンカー社を見習い、フィードバック文化の醸成も進めています。プロジェクト報告会としてプロジェクトでの取り組みや個々の学習の取り組みなどの週報を毎週報告し、普段関わりの少ないメンバー同士のシャッフルチームで相互に意見を伝え合う仕組みや、360度評価も導入しました。互いにフィードバックし合うことで、社内の人間関係を円滑にすること、成長を実感すること、お客様への報告力、論理的思考のトレーニングの場としても位置付けています。

「ビジネス書購入手当」「ランチ手当」「チームワーク手当」など、コミュニケーションや成長を後押しするユニークな制度も整備しました。こうした取り組みに共通するのは、強制ではなく、自発的に行動が生まれる環境やきっかけをつくること。社員と一緒に「働きがい」を育てることを大切にしています。
「働きがいのある会社」調査の結果、「社長が仕事を抱えすぎている」という声や、権限移譲に関する項目のスコアが他と比べて低い傾向がありました。小規模な組織のため私の目が自然と届いてしまう構造的事情でしたが、規模拡大に伴い権限移譲を進め、採用やメンター制度の運営などを現場メンバーに任せています。メンバーを信頼して任せることが各自の成長を後押しし、組織全体の働きがいが高まることを期待しています。
GPTW 「働きがいのある会社」認定をどのように活用していますか。
曽我部様 主に採用とブランディングの両面で活用しています。私たちのような規模の会社は知名度が高いわけではありません。求職者の方にとっては、「どんな会社なのか」「信頼できるのか」という不安があるのも自然なことです。そうしたときに、第三者からの客観的な評価であるこの認定が、安心材料になっていると思います。
加えて、営業や企業説明の場でも、認定は信頼を補完するツールになっています。「働きがいのある会社」として評価されているという事実があることで、「社員を大切にしている会社なんだな」と受け止めてもらいやすくなる。これは開発力や技術力だけでは語れない、組織としての価値を伝える後押しになってくれると期待しています。
GPTW 「働きがいのある会社認定」の影響をどのように感じていますか?
曽我部様 採用に関して言うと、認定を取得してから明らかに応募数が増えました。特に、選考の最終段階で迷っている方にとっては、「最後の一押し」になっている印象があります。
新卒採用でも効果は大きいです。どうしても「大手企業の方が安心」という空気はありますが、「働きがいのある会社」として客観的な評価を受けていることを提示すると、説得力が全然違います。実際に、島根の国立の高等専門学校(高専)向けのイベントでも、優秀な学生からの関心が高く、実際に入社につながったケースも出てきています。これらは非常に大きな成果ですね。
GPTW これから働きがいを高めていきたい企業に向けてメッセージをお願いします。
曽我部様 私は、会社は社会の課題を解決するために存在するものだと考えています。社会にとって意味のある価値を生み出すからこそ、組織の存在が許される。そうした社会的責任を担うのが企業の役割です。そういう役割のはずなのに、社員が精神的な豊かさや幸せを感じられない状態で社会貢献を語るのは、本末転倒だと思うのです。だからこそ、社員一人ひとりが「ここで働けて良かった」と思える環境をつくることは、経営者としての責任だと感じています。
働きがいは一朝一夕に生まれるものではないですし、「これをやればOK」という特効薬もありません。大切なのは、従業員を巻き込み、共に良い会社を作ろうとしていく姿勢だと思います。
やるべきことは地道ですが、MVVや「働きがい」と照らし合わせ、会社全体のありとあらゆることを一貫性ある設計にしていくことです。営業・採用・育成・評価・福利厚生とあらゆるタッチポイントで、会社として何を大切にしているのかを問い続け、実際の行動に落とすべきです。私たち自身もまだ道半ばですが、「働きがいのある会社」を目指す仲間が増えることで、日本全体の働く環境も健全で希望のあるものになると願っています。