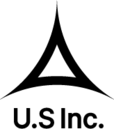「無形の価値」を働きがいのある環境で育む
スモールカンパニーが挑む、本気の組織設計
株式会社U.S 執行役員
重野 茉衣子 様
更新日 2025.07.182025.07.18

「無形の価値」を働きがいのある環境で育む
スモールカンパニーが挑む、本気の組織設計
株式会社U.S 執行役員
重野 茉衣子 様
ブランディングやクリエイティブなど「無形の価値」で企業変革を支援する株式会社U.S。同社が、「Great Place To Work(R)働きがいのある会社調査(以下、働きがいのある会社調査)」を通じて「働きがい」の実態と「自社らしさ」を客観視し、さらなる成長の土台を築いたプロセスとは? 執行役員の重野茉衣子さんにお話を伺いました。
<抱えていた課題>
✓事業成長の根幹として、メンバーがアイディアを生み出すための環境づくりが必要だった
✓これまでの取り組みに対して、社内の受け止め方を確かめたいと思っていた
<導入の決め手>
✓調査を通じて他社と比較しながら自社を客観視できると感じた
✓課題と強みを定量的に可視化することで、次のアクション実行に活用できると感じた
✓働きがい認定取得により社外に向けての採用ブランディング効果が期待できると感じた
GPTW 御社の事業概要とその特色を教えてください。
重野様 当社は企業や事業、組織の変革を通じて、新たな社会体験を創出する「総合プロデュースカンパニー」です。ブランディング、コンサルティング、クリエイティブなどの機能を活かし、企業の事業成長や組織づくりを支援しています。

事業領域は大きく二つ。一つは、商品開発・ブランディング・マーケティングといった「外向き」の支援領域。もう一つは、HR施策・育成・インナーブランディングなど「内向き」の支援領域です。どちらの領域にも対応できる専門性を持ったメンバーが社内に在籍しています。そのため、バックグラウンドも多彩です。コンサルからクリエイティブ、事業会社出身まで多彩な人材がいますし、そうした多様な視点を持つメンバーが、チーム一丸となってプロジェクトに取り組むのが、私たちの大きな特徴です。
GPTW 御社にとっての働きがいの位置づけを教えてください。
重野様 私たちの提供する価値は、アイディアや企画といった「無形のもの」です。だからこそ、そのアイディアを生み出すメンバーが、最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりが、事業成長の根幹だと考えています。
当社は「遊ぶように働く」というワーキングポリシーを掲げています。仕事が楽しいだけでなく、仕事以外の時間で得たインプットが、自然と仕事に活きる。そんな人生全体を豊かにする働き方を目指しており、「働きがい」とも通じる点があると思っています。
GPTW 働きがいのある会社調査に参画したきっかけを教えてください。
重野様 会社の規模は20名程度とまだ小さいですが、調査を通じて他社と比較しながら今の自社を見つめ直せると思い、導入を決めました。特に知りたかったのは、社内と社外、両方の視点からの評価です。まず社内的には、「U.Sらしさ」がきちんと反映された環境になっているか、それがメンバーにポジティブに届いているかを確認したかった。そして、課題と強みを定量的に見える化することで、次のアクションにつなげていきたいと考えました。
もう一つは社外的な意義です。私たちはまだ小さな会社ですし、大企業のように制度が整っているわけではありません。だからこそ、入社を検討する方にとっては不安があるのも当然です。「この会社、本当に大丈夫かな?」と。
働きがい認定のような客観的な外部評価があることで、少しでもその不安を和らげ、安心してもらえる材料になると思いました。また、私たちはHR領域の支援も行っている立場です。「人事を支援します」と掲げている会社が、自社の仕組みを整えられていないのは説得力に欠けるという想いもありました。
GPTW 働きがいを高めるために、具体的にどんな取り組みをしていますか。
重野様 10人規模の頃から、グレード制度やミッションマネジメント、全社合宿など、制度設計に力を入れてきました。大手企業で実践されるような制度を、小規模だからこそ丁寧に導入してきた自負があります。その歩みがどう受け止められているのか、調査を通じて確かめたかったという意図もあったのです。
私たちは「仕事を楽しめる環境づくり」を重視しており、その仕組みの一つがミッショングレード制度です。業務レベルを10段階で定義し、半期ごとに見直しとフィードバックを実施。メンバーは自分の役割や目標に対する達成度を振り返り、その成果によってグレードが上がる仕組みです。目的は「上下をつけること」ではなく、「納得感のある評価」を行うことにあります。少人数だとなんとなくの印象で評価されがちですが、それを避けるために業務の基準を明確にし、自分の現在地を把握できる仕組みを設けています。
また、半期に一度の全社オフサイトミーティングも大切にしています。新メンバーが多い時期は相互理解やチームビルディングを、直近では10期目に向けたビジョン共有など、中長期の方向性をテーマに経営陣と全員で対話する機会を設けています。

さらに力を入れているのがインプット支援です。書籍購入や外部研修、セミナーへの参加支援に加え、リーダー職以上には3年に一度、10日間の特別休暇と10万円の補助がセットになった「インプット・アウトプット休暇」も用意しています。人生経験や外部刺激がアイディアに直結する仕事だからこそ、枯渇しないための環境づくりは欠かせません。
働きがいのある会社調査の結果を見て、これまでの取り組みが制度としてだけでなく、働く人たちの体験としてきちんと届いていた手応えが得られたのは、本当に嬉しいことでした。
GPTW 「働きがいのある会社認定」をどのように活用していますか。また、どのような効果を感じていますか?
重野様 「働きがいのある会社」認定は、求職者やクライアントとの信頼醸成に役立っています。PR TIMESでの発信や採用面談での説明など、安心材料のひとつとして伝えるようにしています。
アンケート結果を基に算出された「働きがいポイント」トップ3を、GPTWのホームページに掲載いただいており、自社ではそれらが選定された背景やワークポリシー、制度の説明などを交えながら言語化し、発信しました。
第三者機関の調査結果で裏付ける形になるので信頼も得られ、私たちの仕組みや働く環境など求職者やクライアントへはより伝わりやすくなった実感はあります。明確な採用効果は測りづらいですが、内定承諾率が上がった感触もありますね。
また、「仕事に行くのが楽しみ」というスコアが高かったのはとても嬉しく大きな収穫でした。しかも、その情報を認定取得とあわせて周知できたことも、プラスに働くと感じています。
GPTW 働きがいのある会社調査を通じて、浮き彫りになった課題はありますか?
重野様 もちろん、課題もありました。印象的だったのは、「経営層の考えが見えづらい」と感じているメンバーが一定数いたことです。情報は隠していないつもりでしたが、伝え方に課題があったと実感しました。現在はリーダー層を通じた共有を進めていますが、仕組みとしての改善が必要だと感じています。
この気づきを受けて、1月の全社オフサイトミーティングでは、会社の創立背景やミッション・ビジョン・バリューの原点を経営陣から直接伝える場を設けました。ただスローガンを覚えるのではなく、「なぜこの言葉なのか」を共有することで、理解と共感が深まったと感じています。今後、今回の取り組みが次回調査にどう影響するかを見るのが楽しみです。
GPTW これから働きがいを高めていきたい企業に向けてのメッセージをお願いします。
重野様 今後、人材の流動性はさらに高まっていくと思います。そんな時代において組織が生き残るカギは、「この会社に居続けたい」と思ってもらえるかどうか。

私たちのようなベンチャーは、人の出入りがあるのが自然ですし、それ自体をネガティブに捉えてはいません。ライフステージや方向性に応じて、在籍期間がその人のキャリアの一部になれば十分だと思っています。
ただ一方で、「なぜこのチームで働くのか」という意味がより強く問われる時代になっている。働きがいは、もはや単なる人事施策ではなく、これからの組織づくりの中心テーマです。もし同じような思いを持つ方がいれば、ぜひ調査の導入や定点観測を検討してみてほしいと思います。