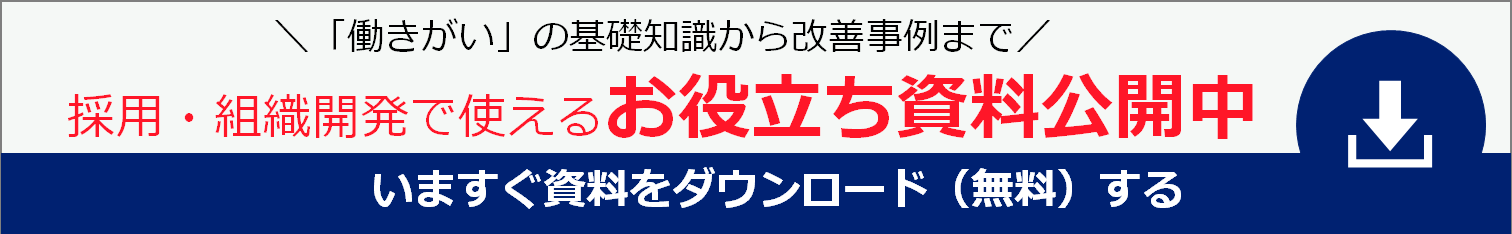従業員の当事者意識を高めるには?ポイントと成功事例を紹介
更新日 2025.02.282025.02.28コラム

従業員の当事者意識を高めることは、組織の成功にとって極めて重要です。当事者意識とは、自分の仕事や組織の課題を「自分事」として捉え、責任感を持って能動的に関わる姿勢を指します。この意識が高まることで、従業員は自発的に問題解決に取り組むようになり、業務の効率化や成果向上につながります。
本コラムでは、当事者意識の定義から、その重要性、低下の原因、向上のためのポイント、そして企業で実践されている事例まで、包括的に解説していきます。
目次
当事者意識とは?
当事者意識とは、自分の役割や責任を理解し、それに対して主体的に関わろうとする意識や態度のことを指します。言い換えれば、与えられた仕事や課題に対して、他人事ではなく自分の問題として積極的に関わろうとする姿勢といえるでしょう。
社会人と密接な関係にある当事者意識
当事者意識の重要性は、特にビジネスの場において顕著です。
当事者意識が高まると、その人は自分の仕事に対してより大きな興味や情熱を持ち、自発的な行動をするようになります。例えば、プロジェクトの進行中に問題が生じた際、単に上司や同僚に報告するだけでなく、自ら解決策を提案したり、他のメンバーと協力して対処法を見つけたりする行動が見られることがあります。このような主体的な行動は、チーム全体の士気を高め、プロジェクトの成功に大きな影響を与えます。
つまり、当事者意識が高い社会人は、自身の仕事の生産性が高いのはもちろんのこと、組織全体の生産性を向上する上でも非常に重要な役割を担うのです。
こうした背景から、企業の成長戦略において、従業員の当事者意識を育むための環境作りは極めて重要なステップだと言えるでしょう。
【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~
「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。
当事者意識が低い人の特徴
当事者意識が低い従業員には、以下のような特徴がみられることがあります。
自分の役割や責任に対する意識が薄い
当事者意識が低い人は、自分の役割や責任に対する意識が希薄です。例えば、チームプロジェクトで何か問題が発生した場合でも、自分に関係のないことだという姿勢が見られることが多く、積極的に解決に寄与しようとしません。
受け身・言われたことしかやらない
物事を「他人事」と捉えがちなため、指示待ちの姿勢が強く、自ら課題を見つけて行動することが多くありません。また、指示された仕事のみをこなし、それ以上の付加価値を生み出そうとしないといった傾向もあります。
自分の意見を言わない
自分の意見を言わないことは、当事者意識の欠如を示す典型的な行動の一つです。会議の場で積極的に発言せず、他の人の意見に同調するだけといった姿勢が見られます。自分の意見を言わないことは、他のメンバーに対して「自分の貢献は必要ない」と誤解させる要因にもなり、チーム全体の士気を低下させるといった悪影響も及ぼします。
危機感が欠けている
組織や業界の課題に対して無関心で、自分に直接影響が生じない限り行動を起こそうとしません。さらに、当事者意識がない人は情報収集を怠ることも多いです。そのため新しいルールや方針の変更があった際に、内容を十分に理解していないケースも少なくありません。これらは、その後の業務においてトラブルを招く原因になる可能性があります。
責任を転嫁する
当事者意識が低い人は問題が起きた際に、自分の責任を認めず、他の人や環境のせいにしようとする傾向が見られます。責任を押し付け合うことはチームワークを損ない、協力体制を崩壊させる要因にもなります。
自分に自信がない
当事者意識が低い人は行動に対する自分の影響を過小評価する傾向があります。たとえ周囲で問題が起こっていても、「自分が何かを変えたところで結果が変わらない」、「失敗することを避けたい」と考え、消極的になってしまいます。これにより、問題解決のための意欲や努力が欠けることになります。
当事者意識が低くなる原因
当事者意識が低くなる原因は多岐にわたりますが、個人的要因と組織的要因の両面があります。
個人的要因
1.自信の欠如:自分の能力や判断に自信がなく、主体的に行動することをためらう
2.過度な損失回避:失敗を恐れるあまり、リスクを受け付けず消極的な態度になる
3.楽をしたい心理:最小限の努力だけで仕事をこなそうとする
4.目的意識の欠如:仕事の意義や自分の役割を理解していない
5.キャリアビジョンの不明確さ:将来のビジョンが不明確で、現在の仕事との関連性が見出せない
組織的要因
1.トップダウン型組織:意思決定が上層部に集中し、従業員の意見が反映されにくい
2.変化を嫌う:保守的な風土で、新しいアイデアや挑戦を受け入れない
3.仕事の細分化:業務が細かく分割され、全体像や目的が見えづらくなっている
4.評価制度の不透明さ:成果や努力が適切に評価されない、また評価基準が不明瞭になっている
5.過度な管理体制:従業員が自主性を発揮できる余地が少なく、細かな指示や監視が行われている
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
当事者意識を高める重要性
当事者意識を高めることは、個人と組織の双方に大きなメリットをもたらします。
仕事へのモチベーション向上
当事者意識が高まることで、自分の仕事に対する責任感が強まります。これにより、仕事をただこなすだけではなく、創意工夫を加えた付加価値の高い仕事へと変化させることができるようになります。結果的に、仕事に対する満足度や達成感も高まり、モチベーションの向上につながります。
チームワークの強化
次に、チーム内での信頼関係が築かれるという点も重要です。当事者意識を持つ従業員は、自らの行動に対してオープンであり、チームメンバーとのコミュニケーションが円滑になります。また、自分の担当業務だけでなく、チーム全体の成果を意識して行動するため、協力体制が強化され、相互信頼のもとで効率的に業務を進めることができるようになります。
会社への参画意識の醸成
当事者意識が高い従業員は、組織の課題や目標を自分事として捉えるため、会社全体の方向性に対する理解が深まります。これにより自分の役割や仕事の意義を認識し、より積極的に組織にかかわろうとする姿勢が強まります。
組織のパフォーマンス向上
当事者意識が高まれば、従業員は自分の役割や目標に対する理解が深まり、主体的な行動が促進されます。この結果、仕事の効率や質が向上します。また、そうした当事者意識が高い従業員が増えることで、組織力が高まり、組織全体の生産性は大きく向上します。
変化への適応力向上
当事者意識を持って仕事に臨むことで、環境の変化や新たに生じた課題に対し、柔軟かつ迅速に対応できるようになります。これは劇的に変化する現代のビジネス環境において、非常に重要な能力となります。
当事者意識を高めるために必要なアプローチ
ここでは、組織やマネジメントの観点から当事者意識を高める方法を5つ紹介します。
従業員一人ひとりの目標を明確に設定する
目標を明確に設定することは、当事者意識を高めるための基本となります。目標が曖昧な場合、従業員がどういった行動をとるべきか、どういった努力をすべきかといった方向性を見失いがちです。その結果、従業員それぞれの役割や責任感が薄れ、組織に対する貢献度も低下します。
具体的な目標設定は、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限付け)の枠組みを活用することが有効です。例えば、「営業成績を10%向上させる」という目標を設定する場合、ただ「営業成績を向上させる」とするのではなく、具体的な数字と期間を明記することで、達成に向けた具体的なアクションが見えてきます。
また、定期的に目標を見直すことも重要です。環境の変化や新たな課題が現れることが多い現代では、最初に設定した目標がもはや現実的でない場合もあります。そのため、適宜目標を再評価し、必要に応じて修正することが求められます。これにより、目標を追い続ける意欲が湧き、当事者意識がさらに強化されます。
仕事の目的と役割をしっかり伝える
従業員が当事者意識を持つためには、仕事の目的や役割を明確にし、それをしっかりと伝えることが重要です。目的意識や役割が具体的に伝わることで、評価基準も明確になり、従業員は自身がどのように貢献することで評価されるのかを理解します。これにより、従業員は自身の行動に対して責任を持ち、より主体的に業務に取り組むようになります。
また、役割や目的をチーム内で共有することによって、コミュニケーションの活性化も期待できます。定期的なミーティングを設けて相互に共有することで、各人の進捗状況や課題を確認することができ、組織全体としての一体感も醸成されます。
このように、仕事の目的意識と役割を明確にすることは、従業員が当事者意識を持つための重要な要素であり、組織の成果を上げるためにも欠かせない取り組みです。
失敗を許容できる環境作り
失敗を許容できる環境は、当事者意識を高めるための土台として効果的です。多くの企業が、従業員が自由に意見を表明できたり、挑戦できたりする文化を構築しようと努力しています。このアプローチは、意欲的な挑戦や試行錯誤の過程での失敗を受け入れる土壌を作り上げます。
失敗を恐れない文化の構築には、上司やリーダーが積極的に関与することも不可欠です。リーダー自身が失敗を公にし、それに対する改善策を話すことで、部下たちも安心してリスクを取れるようになるのです。
また、失敗を許容できる環境を作るためには、悪い結果に対して罰則を設けず、代わりにリフレクションの機会を設けることが重要です。このような改善の取り組みは、単なる失敗への耐性を超えて、積極的な行動を生み出す基盤となります。
組織内コミュニケーションの活発化
組織内のコミュニケーションを活発にすることは、従業員の当事者意識を高めるための重要な要素です。コミュニケーションが円滑に行われることで、チームメンバー間の信頼関係が強まり、目標に対する共通理解が深まります。具体的には、定期的なチームミーティングやワークショップを設けることで、意見交換の場を増やしたり、アイデアを自由に共有できる環境を整えることが効果的です。
また、オンラインツールや社内SNSを活用することで、物理的距離に関係ないコミュニケーションを促進できます。例えば、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネス向けチャットツールを導入することで、情報の共有やリアルタイムでの意思疎通が可能となり、業務の効率化にも寄与します。
さらに、それぞれの役割や目標設定、成果を可視化することで、チーム全体の意識が一致しやすくなります。相互にフィードバックを行う文化が浸透すれば、個人の成長とともにチーム全体の結束も強化されます。これによって、従業員一人ひとりが自分の役割に自信を持ち、主体的に行動するようになります。
適切な評価基準の設定とフィードバック
適切な評価基準の設定は、従業員にとって自らの役割を理解し、当事者意識を高めるための重要なステップです。評価基準が明確であることで、従業員は自分の仕事がどのように評価されるかを理解しやすくなります。これにより、自分の目標を設定しやすくなり、日々の業務に対して責任感を持ちやすくなるのです。
具体的な評価基準には、業績や成果だけでなく、プロセスや行動面の評価も含めることが求められます。例えば、売上目標を達成するだけでなく、顧客への対応やチームとの協力を評価することで、全体的な業務の質を向上させることができます。また、定期的なフィードバックの実施が従業員の成長を促し、結果として当事者意識を高めることにもつながります。定期的な評価ミーティングや1 on 1の対話を通じて、従業員の意見を尊重しながら、その出来た部分や改善点を具体的に指摘することが重要です。
さらに、評価基準は固定的なものではなく、時折見直しを行うことが大切です。業務環境や会社の方向性が変化する中で、評価基準もそれに応じて調整をすることで、常に従業員にとって意義のあるものとなります。こうしたプロセスを通じて、従業員は自己成長を感じ、ますます高い当事者意識を持つようになるでしょう。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約150ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
当事者意識を高める企業の取り組み事例
組織全体で当事者意識を高めるためには、経営層のリーダーシップとともに具体的な施策が必要です。ここでは、実際の企業の取り組みを紹介します。
コミュニケーションの促進
事例:感謝の気持ちを伝えあう社内SNS
A社では、従業員同士で「ありがとう」の気持ちを簡単に送れるように、社内独自のSNSを構築しています。当初は感謝を伝え合う風土があまりなかったため、まずは事務局がランダムに選んだ従業員に感謝のメッセージを送信するよう働きかけ、徐々に社内SNSの存在を浸透させました。
社内SNSの構築や事務局の積極的な関与によって、「ありがとう」を伝えることへの心理的な負担を下げ、コミュニケーションの活性化につながっています。
従業員参加型の意思決定プロセス
事例:参画意識を高めるアイデア投稿
B社では、全従業員が誰でも自由にマーケティングやイノベーションに関するアイデアを投稿できる制度を設けています。アイデアに対し社長自らが24時間以内に返信したり、翌日の会議で議論され製品化につながったりするなど、従業員の参画意識や満足度の向上につながっています。
この制度の成果は、従業員の新しい発想から生まれる商品やサービスの創出だけではなく、経営陣と現場とのギャップを埋めるコミュニケーションの手段として、また、異なる部署の業務への理解を深める機会の創出としても有効です。
失敗を歓迎する文化
事例:失敗の表彰
C社では、社内の表彰制度として、失敗を恐れずにチャレンジした人を称える「失敗賞」を設けています。 「新しいアイデアを実践していく時に失敗はつきものである」という経営陣の考えのもと、全社総会の場でその勇気ある行動を称賛します。
この表彰により、従業員には「失敗したとしてもチャレンジすることは良いことである」という価値基準が生まれ、イノベーティブな文化の醸成に繋がります。
まとめ:当事者意識が個人と組織の成長を促進
当事者意識を高めることは、個人の成長と組織の発展に両面おいて非常に重要です。従業員一人ひとりが自分の仕事や組織の課題を「自分事」として捉え、主体的に取り組むことは組織の文化に良い影響を及ぼし、結果として高いパフォーマンスにつながります。
従業員の意識改革は単なる個々の成長ではなく、組織全体の未来を明るくする重要な要素といえるでしょう。
組織課題にお悩みなら、こちらもあわせてご覧ください。
組織のパフォーマンスを上げるためには、当事者意識はもちろん従業員一人ひとりの「働きがい向上」も欠かせません。こちらでは「働きがい」とは何か、高めるメリットは何か、若手や職種別でのポイントなどを資料にまとめて公開しています。ぜひお役立てください。