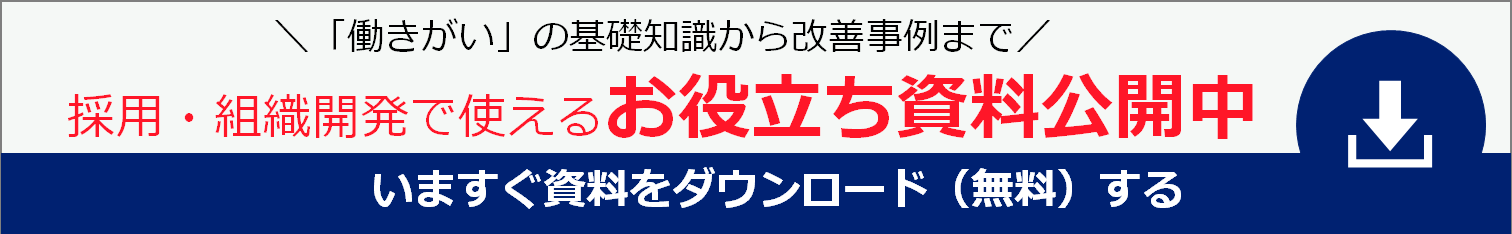協調性とは?身に付ける方法とある人ない人の特徴・仕事で必要な理由や意味をわかりやすく解説
更新日 2025.03.242025.03.24コラム

職場での円滑な人間関係やチームワークを築く上で欠かせないのが「協調性」です。
協調性とは、異なる意見や価値観を持つ人々の間に立って調整を図り、協力し合い、共通の目標に向かって行動できる能力を指します。
仕事においては、円滑なコミュニケーションを促進し、職場の生産性向上にも貢献するため、多くの企業が重視しているスキルのひとつです。
協調性が高い人は、周囲との関係を大切にしながら柔軟に対応できる一方、協調性が低い人は、意見の対立や孤立につながることもあります。
本記事では、協調性の意味や仕事における重要性、協調性がある人・ない人の特徴について詳しく解説します。
目次
協調性とは何か?基本的な意味とその重要性

まずは協調性とはそもそも何か、定義や意味のほか、近い概念であるコミュニケーション能力との違いを解説します。
協調性の定義と意味
協調性とは、異なる価値観や立場を持つ人々と円滑にコミュニケーションを取り、互いに協力しながら目標達成に向けて行動できる能力を指します。仕事においては、チームワークや生産性向上などに欠かせない重要なスキルのひとつです。
協調性が高い人は、周囲の意見を的確に把握し、相手の立場を尊重しながら的確に意見や人間関係を調整できます。立場の異なる人に対して見方や言い方を変えながら、わかりやすく折衝できるのも特徴です。
対立が生じた場合でも冷静に解決策を模索し、組織全体の成果を優先して行動するため、信頼されやすい傾向があります。
協調性とコミュニケーション能力との違い
協調性とコミュニケーション能力は、どちらも職場や人間関係を円滑にする上で重要な能力ですが、それぞれ異なる側面を持っています。
コミュニケーション能力は相手に適切に情報を伝えたり、相手の意図を正しく汲み取り理解したりする、その人単体の能力を指します。
一方の協調性は、意見や立場の異なる人々と調整しながら共通の目標に向かって協力できる、複数人の中で発揮される能力です。
例えるなら、会議でわかりやすく意見を伝えるのはコミュニケーション能力であり、異なる意見を調整しながら合意形成を図るのは協調性です。つまり、協調性はコミュニケーション能力に加えて、対立を解決し他者と協力しながら物事を進める力といえるでしょう。
このように、協調性とコミュニケーション能力は意味合いが異なる能力のため、両者の違いを正しく理解する必要があります。
なぜ仕事において協調性が必要なのか?その理由を解
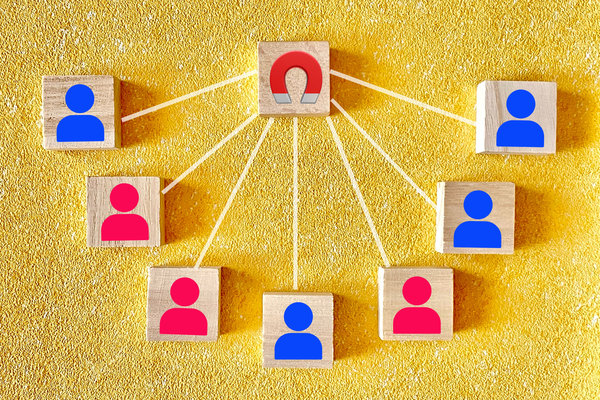
仕事において協調性は重視される傾向にありますが、なぜなのでしょうか。4つの観点からその理由を解説します。
組織内のコミュニケーションを促進するため
協調性があることで、組織内やチーム内のコミュニケーションの促進が期待できます。
メンバーが意見交換やアイデアの共有を行う際、協調性があるとお互いの視点や考え方を尊重し合うことで誤解や衝突が発生しにくいため、常に建設的な議論が可能になります。
このような環境では、それぞれのメンバーが意見を発しやすく、相談もしやすくなるため、合意形成も図りやすくなるほか、イノベーションが生まれやすくなる効果も期待できます。
日常的なコミュニケーションがスムーズになされていると、意思決定の正確性やスピードが上がるため、結果的に組織全体の生産性の向上にもつながります。
また、コミュニケーションが活発な職場は風通しが良く仕事がしやすい傾向にあるため、間接的に従業員満足度や離職率などにも影響するでしょう。
職場環境の改善につなげるため
協調性の有無は、職場環境の改善にも大きな影響を与えます。
協調性が高い職場では、従業員同士が互いに助け合いながら働くことができるため、ストレスの少ない快適な仕事環境が形成されます。このような働きやすい環境は、従業員の会社に対する総合的な満足度を向上させる要因にもなり得るため、離職率の低下や優秀な人材の定着率向上にもつながります。
組織づくりの観点においても協調性は重要です。コミュニケーションミスや無用な対立が少ない組織はチームワークを発揮しやすいため、生産性や競争力を高水準で維持できるためです。
さらに、良好な職場環境の影響は社内だけに留まりません。企業から適切な発信を行うことで、対外的な企業のブランドイメージや魅力を高める効果も期待できるでしょう。
このように、協調性は内外さまざまなシーンで企業にポジティブな影響をもたらします。
組織が抱える問題解決につなげるため
協調性は、組織が抱える問題を解決する場合にも重要です。
協調性がある複数人が協力することで、多様な視点やスキルが融合し、より効果的な問題解決策を導き出すことができます。
例えば、新規プロジェクトの立ち上げにおいて、営業・技術・マーケティングなど異なる部門のメンバーが協力することで、それぞれの視点から多面的な分析を行い、より実践的な戦略を導き出すことが可能です。これは今までになかった新たなアプローチや、斬新なイノベーションが生まれやすいことも意味しています。
さらに、協調性が高いチームでは、メンバーが互いの強みを理解し合い、役割分担を最適化することで業務の効率が向上します。このような体制を構築することで、より複雑な課題にも柔軟かつ迅速に対応できるようになるでしょう。
リーダーを育成するため
協調性はリーダーを育成する場合にも重要な要素です。優れたリーダーには専門知識や経験だけでなく、チームをまとめる協調性が求められるためです。
チームで成果を上げていくためには、メンバーのバランスを保ちながら円滑に協力し合える体制を構築することが重要です。リーダーとして適切な意思決定を行えるよう、メンバーから適切に意見を吸い上げるためにも、やはり協調性が欠かせません。
また、協調性が高いリーダーは仲間たちに良い影響を与えるだけでなく、チーム外の関係者たちとも信頼関係を築けるため、部門の垣根を超えて組織の発展に貢献します。
このように、優れたリーダーを育成するシーンにおいても、協調性の有無が非常に重要な要素になります。
採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約150ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!
協調性がある人とない人の特徴

企業の発展や事業の成長には、協調性の高い人材が不可欠です。 ここからは、協調性がある人とない人の主な特徴を解説します。
協調性がある人の主な特徴
企業が求める協調性は、利害や立場の異なる人たちと調整・協力しながら業務を進められる能力です。
では、「協調性がある人」とはどのような特性を持つ人なのでしょうか。ここでは協調性がある人に共通してみられる5つの特徴を解説します。
柔軟性が高い
協調性が高い人は、高い柔軟性を備えているのが特徴です。異なる価値観や意見を持っている人やさまざまな立場の人達を受け入れ、自らの視野を広げられる傾向にあります。
組織やチームメンバーの多様性を尊重し、より良い解決策を模索する力があるため、状況に応じた最適な判断が可能です。チーム全体の調和を保ち、円滑なコミュニケーションを促進し、生産性を高める上でも重要な役割を果たします。
また、周囲の状況にあわせて臨機応変に自分の行動や主張を調整できるため、周囲からの人望も厚く、管理職やリーダーとして活躍するケースも少なくありません。
このように、協調性がある人は持ち前の高い柔軟性を活かして組織の中で幅広い信頼関係を築き、業務の効率化や成果の向上に貢献する傾向にあります。
受動的で傾聴力がある
受動的で傾聴力が高いのも協調性がある人の特徴です。
受動的な態度は「受け身」などのネガティブな意味に捉えられがちですが、協調性がある人はこれをポジティブな方向に活かします。周囲のニーズや意見に耳を傾けて同調するため、周囲との信頼関係の構築や組織の調整、合意形成などに優れた力を発揮します。
この受動性や傾聴力がチームに調和をもたらし、結果的に共通の目標に向かって進んで行けるという意味では、単に相手の発言や指示を待つ「受け身」とは異なり、「協調性が高い」と表現するのが適切でしょう。
特に、営業職や企画職では、相手のニーズを的確に把握し適切な提案を行う必要があるため、相手の考えを引き出す傾聴力が非常に重要です。
協調性のある人は周囲の状況にあわせて柔軟な対応をする上で、受動性や傾聴力が重要な役割を果たしています。
チームの目標を共有できる
チームの目標を共有できるのも、協調性がある人の特徴です。協調性がある人は個人の利益や自身が目立つことよりも、チームの目標や全体の成功を優先する姿勢を持っているためです。
組織においては個々の能力よりもチームワークが求められるため、他のメンバーと連携する必要があります。協調性のある人は、自己中心的な考えで自己主張するのではなく、調和を重視して周囲と協力して物事を進めようとするため、チームや組織全体の結束やパフォーマンスを高める役割を果たします。一人ひとりのパフォーマンスが向上することでチーム全体が底上げされるため、結果的に大きな成果を生むことができるのです。
このような特性を持つ人は組織内での信頼も厚く、円滑な人間関係を築けるため、長期的に企業の成長を支える重要な存在となります。
問題を解決する能力がある
協調性がある人は、問題解決能力にも優れています。困難な状況や対立が生じた際にも、冷静に対策を考えて問題を解決する力を持っているためです。
協調性がある人は組織全体の利益を優先し、感情的にならず、客観的な視点から課題を分析し、最適な解決策を模索します。自身の利益や意見を押し付けることなく、チーム全体の調整役を担うことで、不要な衝突や対立を避け、円滑に問題を解決に導けるのです。
また、協調性がある人は中長期的な視点で物事を考えて信頼関係を築くよう働きかけるため、安定した持続可能な関係性を築くことができます。
このような人材は、問題が発生している場面で非常に心強い存在であると同時に、人間関係における問題の解決や防止においても優れた力を発揮する傾向にあります。
人を洞察する力がある
協調性がある人は、洞察力に優れているのも特徴です。「調和を重視する」という特性も相まって、常に周囲の状況を気に欠けているためです。
例えば、チーム内で誰が決定権を持っているのか、誰にどのようなサポートをすれば物事がスムーズに進むかなどを即座に判断できたり、特定の状況になった際に誰がどう困るかなどを先読みできたりするため、状況に合わせた臨機応変な対応が可能です。
また、困っているメンバーがいたら自ら進んでサポートする側面もあるため、縁の下の力持ちとしてチーム全体のパフォーマンスを底上げしてくれている場合もあります。
協調性がある人はその優れた洞察力で相手の考えや感情を察知し、適切なタイミングでフォローができるため、相手の立場を問わず周囲からの信頼を得やすい傾向にあります。
協調性がない人の主な特徴
協調性がある人とは対照的に、協調性がない人も一定数存在します。ここからは協調性がない人の主な特徴を解説します。
人とのコミュニケーションが苦手
協調性がない人は、人とのコミュニケーションが苦手な傾向があります。
他者の意見を理解するのが難しく、意思疎通に支障をきたすケースも少なくありません。伝え方が不適切で十分な説明を行わないため、常に誤解を招きやすい状態にあります。
相手の立場に立って考えるのも苦手なため、会話のキャッチボールが苦手で一方的に話を進めたり、相手の意見を遮ったりしがちです。
このようなコミュニケーションの欠如はミスを誘発するだけでなく、チーム内の協力体制をも損なうため、組織全体の成果にマイナスの影響を与える可能性があります。
上司やリーダーのような立場にある人が協調性に欠けると、組織への悪影響はさらに大きくなります。生産性やパフォーマンスが下がるだけでなく、職場環境の悪化や従業員のモチベーション低下を招くため、離職率の上昇を招くリスクもはらんでいます。
融通が利かない
協調性がない人は、融通が利かないのも特徴です。自分と異なる意見や新しいアプローチをなかなか受け入れることができなかったり、従来の考え方や方法を変えることに抵抗を感じたりする傾向があります。
自分のやり方に固執し、他者の意見を受け入れにくいことで業務の効率が低下する場合や、新たな業務フローに対応できない場合もあります。突発的な変更やトラブルにも弱い側面があり、問題を長期化させる要因にもなるケースも少なくありません。
また、個人主義的な態度が目立つと、連帯感やチームワークを損なう原因となり、組織全体のパフォーマンスに悪影響を与える恐れがあります。
このように、協力性の欠如に起因する融通の利かなさは、職場の効率や雰囲気を悪化させる要因となり、人間関係のトラブルを引き起こす可能性もあるため注意が必要です。
相手の立場で物事を考えられない
協調性のない人は、相手の立場に立って物事を考えることが苦手です。
自分の考えや感情を優先することがベースになっているため、他者の意見や気持ちに配慮できず、人間関係のトラブルにまで発展してしまう場合もあります。
具体的には、チーム内での会議において自分の意見を押し通そうとしたり、他者と真っ向から対立して周囲の調和を乱したりするケースなどが挙げられます。相手の視点を理解しようとせず、自分の価値観や経験だけを基準に判断しようとするため、意見の食い違いが生じやすくなるのです。
このような自己中心的な姿勢はチームワークを阻害するだけでなく、メンバー間の連携を困難にする要因にもなり得ます。リーダーやマネージャーの立場にある人がこのような性質を持っていると、チーム内の関係が悪化し、より大きな組織の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
人の意見を聞くのが苦手
協調性がない人は、他者の意見を聞くのが苦手なのも特徴です。
上司やリーダーの立場にある人がこのような性質を持っている場合は、部下の意見に耳を傾けず、自己中心的な判断を下したり、一方的な独断で指示を出してしまったりすることが多く、チームの雰囲気が悪化しやすくなります。
また、協調性がない人は頑固で柔軟性に欠ける傾向にあるため、新しいアイデアを受け入れることができず、業務の効率化や組織の成長を妨げる可能性もあります。
人によっては「他の人の意見を聞いても意味がない」と極端な考えを持っている場合もあり、周囲との関係自体が希薄になり、業務に支障をきたすケースも散見されます。
どのような立場であれ、人の意見を聞けないのは致命的であり、チームで仕事が成り立たないばかりか、周囲からの信頼を失って孤立してしまうことにもなりかねません。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約150ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
従業員の協調性を身に付けるために企業ができる方法

協調性は、業界や職種を問わずあらゆる仕事で役立つ重要なスキルです。従業員の協調性を養う上で、企業ができることを3つご紹介します。
協調性を高めるための研修を導入する
1つ目は、チームビルディングなどの協調性を高める研修を導入する方法です。
チームビルディングとは、チームのメンバー同士が協力し合い、信頼関係を築きながら共通の目標に向かって行動するための取り組みやプロセスを指します。単なるグループではなく、一体感を持って高い成果を生み出せる強いチームを作ることを目的とした概念です。
研修に簡単なゲームを取り入れることで、楽しみながら協調性を身に付けることも可能です。社員一人ひとりが研修を通して協調性やコミュニケーション能力を身に付けることで、全体の底上げを図ります。
社内に研修のノウハウがない場合でも、外部の講師や研修プログラムを活用すれば即座に導入することも可能です。
また、研修の導入はリーダーシップの向上も期待できるため、次世代のリーダーを育成する際にも有効な手段といえるでしょう。
協調性を重んじる組織文化を設計する
2つ目は、協調性を重んじる組織文化を設計する方法です。
協調性を企業文化の一部として定着させることができれば、従業員同士が自然と協力し合う環境が当たり前になります。
具体的には、経営層が協調性の重要性を発信し、リーダーが率先してチームワークを実践することなどが挙げられます。
組織の文化や風土は影響力の大きい人たちによってベースが作られるため、まずは経営層やマネジメント層が一般社員の見本になるべく、率先して協調性を発揮することが重要です。
また、従業員の行動規範やスローガンなどに協調性を重んじるメッセージを入れる方法も有効です。
このような取り組みで組織文化を根付かせることに加えて、評価制度や人事制度を連動させて、制度上も協調性を発揮することを是とすることで、さらに組織文化として定着しやすくなります。
自然に協調性を高められる人事評価制度を構築する
3つ目は協調性を重視した人事評価制度を導入する方法です。
協調性を発揮することが直接的に評価に結びついていれば、従業員は積極的に協調性やチームワークを意識するようになります。
例えば、評価項目にチームへの貢献度や他者へのサポートが評価に反映される項目を入れることで、従業員の行動を促します。協調性はやや抽象的な概念なので、どのような協調性に含まれるのか、具体的に何をすれば評価されるのかを明確にしておくことが重要です。
評価基準を明確にし、基準通りに協調性を発揮した従業員が適切に評価され、昇進や報酬につながれば、協調性に加えてモチベーションの向上も期待できます。
このような制度を整えることで、従業員は努力すべき方向性が明確になります。うまく機能すれば組織全体の結束力やチームワークが高まり、より働きやすい職場環境を実現できるでしょう。
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
採用担当者が面接で協調性を見極めるポイント
人材採用のシーンにおいて協調性の有無を見極めたい場合もあるでしょう。ここからは採用担当者が面接で協調性を見極めるための3つのポイントを解説します。
チームワークに関係する質問をしてみる
面接においては「チーム」や「チームワーク」といったキーワードを使って質問することで、より具体的な回答を引き出しやすくなります。
例えば以下のような質問が考えられます。
-
「チームで仕事を進める際に心がけていることはなんですか?」
-
「これまでにチームで協力して成果を出した経験を教えて下さい」
-
「チームで成果を上げたエピソードと、その時のご自身のチーム内における役割について教えて下さい」
このような質問をすることで、候補者がチームワークをどのように考え、業務においてどのように協調性を発揮してきたかを確認できます。
また、トラブルが発生した際の対応方法や、意見が異なる相手とどのように合意形成してきたかを聞くことで、実際の行動を把握するのも効果的です。
質問をしながら協調性を探る
候補者が協調性についてどう考えているのか、なぜそのように考えるに至ったのかを尋ねてみる方法も有効です。
例えば、「協調性とはどのようなものだと思いますか?」や「仕事における協調性の重要性についてどのようにお考えですか?」などとストレートに尋ねることで、相手の価値観や協調性に対する率直な考え方を確認できる可能性があります。
単発の質問で終わらせずに、その考えに至った具体的なエピソードや、実際の行動に反映している部分などを聞くことで、発言の整合性や再現性の有無を探れます。
また、「協調性を発揮できたと感じた出来事」や「その際に周囲から、または上司などからどのような評価を受けたか」などを尋ねることで、自己評価と他者評価の一致度を確認することもできます。
いずれの場合も考え方や価値観を探るだけでなく、具体的な行動やエピソードを聞くことが大切です。そうすることでその回答に対する裏付けが取れるためです。
適性検査の導入をする
より正確に協調性の有無を評価したい場合は、適性検査を導入するのもひとつの方法です。面接はどうしても面接官の質問スキルや評価基準の精度によって評価がぶれがちですが、適性検査であれば客観的かつ定量的な評価が可能なためです。
多くの適性検査は、協調性以外にもさまざまな職務適性やパーソナリティを評価できるようになっており、検査の種類も非常に豊富です。協調性の有無や程度に重きを置きたい場合は、チームプレイやリーダーシップ、コミュニケーションスタイルなどに焦点を当てた検査が特に有効です。
これらの検査では、チームにおける業務遂行能力や他者との連携の得意・不得意なども把握できるため、協調性を多面的に評価できるでしょう。
検査を受けるために費用はかかりますが、面接官のスキルや経験値に左右されることなく、精度の高い評価ができるメリットがあります。
昨今、企業の認知度や求職意識を高めるために、採用ブランディングをする企業が増えています。この資料では、採用ブランディングの概要、メリット・デメリットに加え、具体的な実施手順や成功のポイントを解説します。
「働きがい認定」は組織の協調性を高める施策につながる

協調性とは、異なる意見や立場を持つ人々と円滑にコミュニケーションを取り、共通の目標に向かって協力できる能力です。
協調性がある人は組織内のコミュニケーションを促進し、職場環境を改善し、問題解決能力を向上させるなど、企業に多くのメリットをもたらす貴重な存在です。このような人が多い職場は居心地が良く仕事も捗るため、人材の定着率も高まります。
企業の職場環境や従業員満足度を第三者が評価する「働きがい認定」も、組織の協調性向上に役立つ施策のひとつです。この認定を取得することがインナーブランディングにつながり、従業員が改めて自社の組織カルチャーを再認識することにつながります。