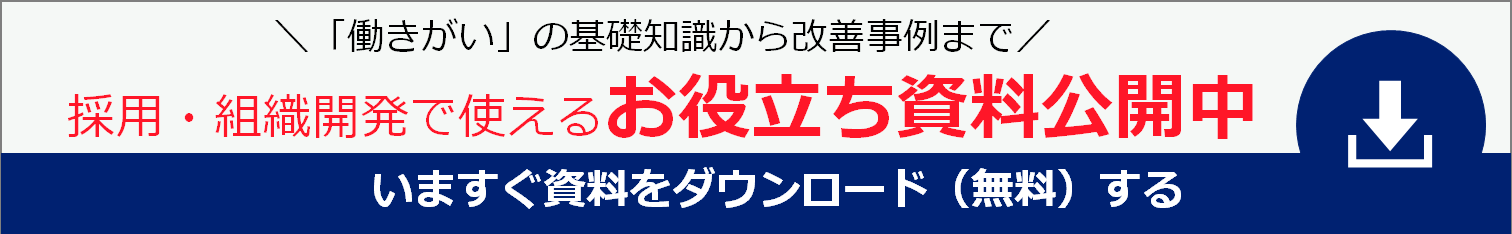カルチャーアドとは?カルチャーフィットとの違いや注目されている背景を解説
更新日 2025.02.182025.02.18コラム

働きがいのある会社の特徴は何か。それは、よいカルチャーの土台があることといっても過言ではありません。どんなに優れた人材が集まり、最高の制度や福利厚生があっても、よいカルチャーがなければ、企業成長や価値増大は限定的と言えるでしょう。よいカルチャーは維持していくことが大切です。そこで多くの企業では、カルチャーに合った人材を採用すること(カルチャーフィット)に注力してきました。しかし最近、このカルチャーフィットを重視しすぎることへの弊害が指摘されています。代わりに注目されているのが、“カルチャーアド”。このコラムでは、“カルチャーフィット”と“カルチャーアド”の違いについて、またカルチャーアドが求められるようになった背景について紐解きます。
目次
カルチャー(企業文化)とは
カルチャーとは、その組織において当然とされる独自の価値観や信条、行動様式の総体と定義できます。カルチャーは、組織におけるリーダー(経営・管理者層)の日頃の言動、組織構造、人事制度やルール、あるいは日々のコミュニケーションなど多様な要素が影響して形成されます。目に見えないものではありますが、“職場においてどうふるまうべきか”について従業員に対して影響を与え、集団を特徴づけるものです。
企業文化は産業によって異なる特徴があるようです。組織文化の研究者として知られるギデオン・クンダによると例えば、ハイテク産業ではイノベーション創出ために“リスクを推奨したり、チームワークを重視したりするカルチャー“があること、あるいは製造業では品質やコスト、職場の安全性が重要視されるので、”階層的な管理、ルールの徹底がリスペクトされるカルチャー“があることが明示されています。
Great Place To Work(R)は世界150か国以上で、その国における働きがいのある会社を認定・ランキング発表していますが、どの企業にも共通しているのは、長い年月をかけて独自の優れたカルチャーづくりに力を注いでいるということです。特に、経営トップの考え方や行動は、カルチャーに多大な影響を及ぼすと言われています。
カルチャーが重要な理由
カルチャーはなぜそれ程までに重要なのでしょうか。強固なカルチャーを醸成するメリットを考えてみるとその理由は明らかです。主に3つあると考えています。
- 従業員の働きがい(エンゲージメント)向上
- 組織の競争力向上
- 採用力の向上
従業員の働きがい(エンゲージメント)向上
組織の価値観が共有されている職場では、従業員は安心して働くことができます。仕事をする上では様々な判断が迫られますが、優先すべき大事なことが明確で周囲に共有されていることで迷いが小さくなるからです。自分の仕事も価値観と結びつけられているので自発的に行動できることも多く、その結果意欲も高まりエンゲージメント向上に繋がります。
組織の競争力向上
カルチャーが浸透している組織では、従業員が価値観に添って自律的に行動するので高い生産性が期待できます。また同じ価値観や信条に共感しているため、お互いに安心して意見を言いやすく新しいアイデアや改善が生まれやすいともいえるでしょう。顧客サービスにおいても一貫した行動が期待できるので人による品質のばらつきなどが回避され、市場において競争力を発揮することができます。
採用力の向上
カルチャーが明確であれば、それに合った人の採用を行うことでいわゆる入社後のミスマッチも低減できます。早期離職のリスクが限定されることは、人事コストの削減にもメリットがあります。
参照:GPTWコラム「組織文化とは?4つのタイプや改革のステップ、企業事例を紹介」

カルチャーフィットとは
採用において自社カルチャーに合う人材を見極めようとする手法をカルチャーフィット(Culture Fit)と呼びます。具体的に選考基準になるのは、ミッション・ビジョン・バリューへの理解と共感、求める行動規範の賛同などが挙げられます。
Great Place To Work(R)が選定する働きがい認定企業にも、採用において、その人の持つ知識やスキルよりも、カルチャーフィットをより重視している企業は多くあります。採用説明会では、会社の大事にする価値観、目指す方向性、仕事をする上での優先順位などをストーリーと共に語り求職者に理解してもらいます。そのため入社後に理想と現実のギャップを感じて、モチベーションを低下させる入社者は少ないようです。
カルチャーフィットを取り入れるメリット
カルチャーフィットを採用プロセスに組み込むことは、時間も労力も要します。フィットすることを見極める方法は単純ではなく手間暇がかかるのです。例えば、多数の既存従業員との面接をしてもらうため回数を多くしたり、求職者の価値観を理解するために長時間にわたり話を聞いたりといったことが挙げられます。しかしながら、そこまでしてもカルチャーフィットした人材採用はその後の定着や早期離職率防止など大きなメリットが期待できます。加えて、組織運営においても以下のような効果があるでしょう。
- スムーズなコミュニケーション
- 迅速な意思決定
- チームワークの良さ
スムーズなコミュニケーション
価値観が一致していると職場におけるコミュニケーションはとてもスムーズです。問題解決や意思決定の場面においても意見が対立することは少なく、合意形成がしやすいと考えられます。
迅速な意思決定
仕事の優先順位はなにか、行動で優先されるものはなにか、が共有されているので、物事の判断は同質であります。よって何か重要な意思決定をする場面においても比較的迅速に行うことが可能です。
チームワークの良さ
会社の目指す方向性が一致しているので、職場には仲間意識が醸成されます。同じ目的を実現する上では、困った時にはお互いを思いやり、助け合う雰囲気があります。
カルチャーフィットのデメリット
良いことだらけのカルチャーフィットですが、最近この手法に異論を唱える意見もあるようです。つまり、カルチャーフィットが行き過ぎると均質的な組織になりかねないという懸念です。チームのまとまりや仲の良さという面ではカルチャーフィットは好ましいものの、新しい未知の領域やイノベーションの探求の観点からみるとどうか、という指摘です。
そこで登場したのが、「カルチャー・アド」(Culture Add)という考え方です。

カルチャーアドとは
カルチャーアドとは、現在組織が大事にするカルチャーに合っていることを前提としつつ、加えて新しい価値観や多様性を持っている人を採用する手法のことです。 導入に積極的な業界には特徴があり、主にはIT業界やクリエイティブ業界、スタートアップ、ベンチャーなどに多いようです。
カルチャーフィットとカルチャーアドの違い
カルチャーフィットは、現在のカルチャーに合う人を採用することで、具体的には組織の価値観や行動規範、コミュニケーションのアプローチなどに親和性があることが特徴です。
これに対して、カルチャーアドは、現在のカルチャーに基本的にはフィットしつつ、新しい価値観や視点をもたらす可能性がある人材採用を意味します。
カルチャーアドが注目されている背景
カルチャーフィットが組織にとってメリットも大きい中で、カルチャーアドが注目されている背景について整理してみましょう。
2015年~2018年頃にアメリカのテクノロジー企業、例えばGoogle、Meta(旧Facebook)などを中心に取り入れられたのが始まりです。元々はカルチャーフィットを重視していた企業群ではありますが、グローバル化、市場の変化への対応として同質性組織が行き過ぎることで、新しい発想の行き詰まり、変化への硬直化の弊害が出始めたこと、また社会的に組織における多様性がより重視されるような時代背景が影響していると考えられます。
【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~
「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。
カルチャーアドのメリット
カルチャーアドは組織に新しいチャレンジを促し変化を起こす人材採用によって、長期的に組織に望ましい変化と成長をもたらすことを目的とします。これまでとは異なる視点を持つ多様な人材が集まることで、組織の柔軟性が増し、イノベーションが向上することが期待できます。
カルチャーアドのデメリット
カルチャーアドは、新しく登場した採用手法ではありますが、組織にとっては一時的には、今いる従業員との対立やコミュニケーションの齟齬が発生するリスクがあります。組織に醸成された既存の価値観との対立が最も大きいデメリットと言えるでしょう。
カルチャーアドを導入する際には、いくつかの注意点を押さえる必要があります。次にそのことについてお話ししましょう。
|
カルチャーフィット |
カルチャーアド |
|
|---|---|---|
| 定義 |
自社カルチャーに合う人の採用 |
これまでのカルチャーとは異なる新しい価値観や多様性を持っている人の採用 |
| メリット |
●対立は少なく迅速な意思決定が可能 ●コミュニケーションがスムーズでチームワークも安定 |
●意思決定のプロセスに新しい観点や気づきを付加 ●変化と成長、イノベーションの創出 |
| デメリット |
●均質的な組織による膠着・同調圧力 ●既存の枠組みを超えた新しい発想の不足 |
●既存の従業員との対立 ●コミュニケーションの齟齬 |
| 業界別適応 |
金融、法律、医療、行政 |
IT、広告、コンサルティング |
カルチャーアドを推進するための3つのポイント
カルチャーアドを採用において手法として実践する場合、いくつかのポイントがあります。
- 変えてはいけない価値観を明確にする
- 現在のカルチャーと共存させる
- カルチャーアドで採用した人材をサポートする
変えてはいけない価値観を明確にする
カルチャーアドによってこれまでとは違うタイプの人材が採用され、新しい改革をいきなり実践すると、既存の従業員は驚き組織の一体感が低下するリスクが高まります。新しい視点を入れるということは、従来の価値観を全て否定することとは異なります。なぜこれまでとは違うタイプの人材を採用するのか、どのような変革への対応のためなのか事前に説明しておくことが大切です。例えば、国内事業だけでなく海外展開も行う場合、異文化理解に長けた人材採用を行おうとか、デジタル化の対応のためにその分野の専門人材を採用しようという場合にこれまでとは違う革新的な人材が採用される、ということで職場の雰囲気にも揺らぎがある可能性があります。既存のカルチャーの何を変えて何を変えてはいけないのか、改めて明確にしておくことが大切です。
現在のカルチャーと共存させる
先にも述べたように、突然新しい価値観を持つ人の採用を始めると、これまでとは異なるバックグラウンドを持つ従業員の存在に職場には混乱が生じます。よい意味で居心地のよい環境下に“合っていない人”が採用された、“間違った採用”がされていると誤解を生む可能性もあります。最悪の場合、カルチャーアドで採用された人と既存の従業員の間で衝突や対立が起こることもあるかもしれません。想定しない離職なども防ぐためには、早急なカルチャー変革を進めるのではなく現在のカルチャーの強みを認めながら共存させ、長期的な視野で変化を進めていくことが大切です。なぜ新しいタイプの人を採用しているのか、将来の事業方針や組織戦略について見通しがあれば、無用な衝突は避けられるでしょう。
カルチャーアドで採用した人材をサポートする
組織に新しい風を吹き込むことを期待して採用した人材が精神的に強い人であるかは別の問題です。職場になじんで周囲にも理解されるには、会社の丁寧なサポートが必要です。カルチャーアドによる採用を積極に行っている企業によくある問題として、結局新しく入社した人が既存のカルチャーに合わず辞めてしまうことです。これまでにない方法でなにかを実践することを期待されている人材には、全力でそれが実行できる環境整備を上司や会社が整えることもセットで求められるでしょう。なにか小さな改善が起きれば機会を逃さず称賛することで職場にもメリットがあることを伝えることができます。

カルチャーを見える化するために
カルチャーフィットとカルチャーアド、これまで見てきたようにメリットとデメリットがあります。どちらが正解かというより、組織の特徴や今後の成長フェーズに合わせてうまく取り入れるとよいでしょう。カルチャーアドを導入したからといって直ちにこれまでのカルチャーが変わるわけではありません。長い時間をかけてカルチャーを前向きに進化させていくことなのです。時代の変化や社会の要請に応じて組織は時にカルチャーを変革させていくことも必要です。
健全な変革を進めていくためにも定期的に組織の状態を測定することが大切です。Great Place To Work(R)の「働きがいのある会社」調査には、よいカルチャーを醸成するためのリーダシップ、仕事への誇り、チームワークの状態を測る世界共通の60設問があります。また「この会社に合った人が採用されている」という設問は、カルチャーアドを始めたばかりの企業にとっては新しいタイプの採用について既存の従業員がどんな風に感じているのか、相互理解は進んでいるかといった職場の反応を測るのに適しています。
ぜひ貴社の採用の成功ためにGreat Place To Work(R)の「働きがいのある会社」調査に参加してみませんか。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約150ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
Great Place To Work(R) Institute Japan シニアコンサルタント 今野 敦子

フランス国立ボンゼショセ工科大学MBAコース取得。
外資系航空会社、医療系商社の人事部を経て、リクルートマネジメントソリューションズに入社。人事領域において、採用・制度設計・人材育成など一連の業務に携わる。
2009年GPTW Japan設立メンバーとして、事業立ち上げに参画。働きがいのある職場を目指す多くの企業などに調査分析、経営層への提言と支援を行う。