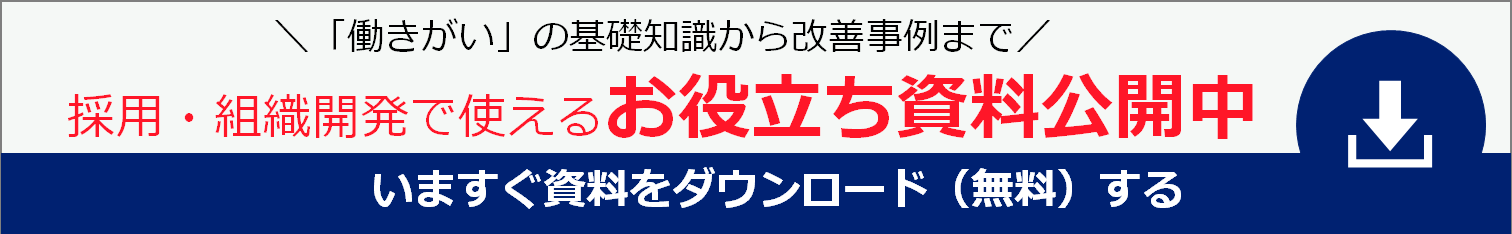ジョブ・クラフティングとは?効果を高めるコツや実施手順を紹介
更新日 2025.03.242025.03.24コラム

ジョブ・クラフティングとは、従業員が主体的に業務を見直し、働きがいや生産性を向上させる手法です。
変化が非常に激しい現代のビジネス環境において、従来のトップダウン方式の働き方では適応が難しくなってきているため、企業はこれに代わる体制を構築する必要性に迫られています。
このような難しい状況下で効果的な手法として注目されているのがジョブ・クラフティングです。
本記事では、ジョブ・クラフティングの概要や注目されるに至った背景に触れつつ、具体的な進め方や導入のポイントなどを網羅的に解説します。
目次
ジョブ・クラフティングとは?その定義と目的

ジョブ・クラフティングとは何か、まずはその定義と目的を解説します。
ジョブ・クラフティングの意味と特徴
ジョブ・クラフティング(Job Crafting)とは、従業員一人ひとりの仕事に対する認知や行動を主体的に修正していくことで、退屈な作業や「やらされ感」を解消し、やりがいのあるものへと変えていく手法です。
例えば、単調な業務になんらかの工夫を加えたり、業務の目的や自身の役割などを前向きに捉え直したりすることで、仕事に対するモチベーションの向上を図ります。
ジョブ・クラフティングを取り入れることで、単なる作業として認識していたさまざまな業務が自己成長の機会となり、仕事への満足度やパフォーマンスの向上が期待できます。
ジョブ・クラフティングは個人の意識改革にとどまらず、取り組み方次第で組織全体の生産性向上も実現できる可能性があるため、近年多くの企業から注目されている手法です。
ジョブ・クラフティングの目的
ジョブ・クラフティングの目的は、仕事の意義や取り組み方を主体的に見直し、働きがいを見出し、生産性やパフォーマンスを向上させることにあります。
具体的には、業務のやり方を工夫してより良い成果を生み出すことや、自主的に資格取得を目指しスキルアップを図ることなどです。
また、人間関係のあり方を変えることもジョブ・クラフティングに含まれます。例えば、これまで以上にチームワークを意識したり、協力し合う体制を作ったりすることで職場環境が改善され、モチベーションやパフォーマンスが向上する場合もあります。
このほかにも、仕事の意義を見つめ直すことで業務の見え方が変わり、同様の効果が得られるケースもあります。
このように、ジョブ・クラフティングはさまざまな角度から仕事のアプローチを変えることで、その人自身や組織全体のパフォーマンスを向上させることを目的としています。
<関連記事>
ジョブ・クラフティングとジョブ・デザインとの違い
ジョブ・クラフティングとよく似た概念にジョブ・デザインがあります。両者は仕事をより良くするための理論ではあるものの、主体や視点に違いがあります。
ジョブ・クラフティングとは、従業員自らが主体となって業務そのものや人間関係などを見直し、働きがいやモチベーションの向上を図る手法であり、個人の自主性を重視し、働き方を主体的に変える点が特徴です。
一方、ジョブ・デザインは、企業や各部署の管理者などが主体となって業務の設計を行い、メンバーや組織全体の効率・成果を最大化することを目的とした手法のため、従業員は受け身の立場になります。
それぞれ主体が異なるため、企業側は人事戦略の一環としてジョブ・デザインを最適化しつつ、従業員一人ひとりがジョブ・クラフティングを実践するといった運用も可能です。
ジョブ・クラフティングが注目されている理由

ジョブ・クラフティングは、従来の手法に代わる企業の成長戦略として注目されています。ここではその具体的な背景を2つの観点から解説します。
変化の激しい「VUCAの時代」の到来
現代はその変化の激しさから「VUCAの時代」と呼ばれています。VUCAとは変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字を取ったものです。
近年は技術革新や経済の変動、主要国の政権の不安定さやグローバル化の進展など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、企業を取り巻く環境は急速に変化しています。
このような先読みが難しい状況では、従来の固定的な考え方や業務の進め方では変化への対応が難しいため、より柔軟な働き方が求められています。
ジョブ・クラフティングは、従業員一人ひとりが自ら業務の意味を見直し、主体的に変化していくアプローチのため、まさにVUCA時代に不可欠な考え方、在り方と捉えられています。
トップダウン方式に限界が生じつつある
従来の企業経営の主流であった「トップダウン方式」に限界が生じつつあるのも、ジョブ・クラフティングが注目される一因となっています。トップダウン方式とは、経営層が主要な意思決定を行い、その意思決定に沿った指示が現場に伝達される方式です。
しかし、変化の激しいVUCA時代においては、トップダウン方式では顧客のニーズの多様化や新たなツールの登場などの変化に対応しきれないケースが増えています。
トップダウン方式の限界が指摘される中、この課題を解決する方法として注目されているのがボトムアップ方式とジョブ・クラフティングです。
両者はトップダウン方式とは対称的で、現場の従業員が主体的に業務を改善し、環境の変化に柔軟に対応する手法です。
いずれにせよ、企業は社会の急速な変化に対応するべく、従来のトップダウン方式に代わる体制を構築する必要性に迫られています。
採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約150ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!
ジョブ・クラフティングの種類とその進め方

ジョブ・クラフティングにはいくつかの種類があり、それぞれ異なるアプローチで仕事のやりがいや満足度の向上を図ります。ここからは、ジョブ・クラフティングの種類とその具体的な進め方について解説します。
3つの視点:作業・人間関係・認知クラフティング
厚生労働省(※)によると、ジョブ・クラフティングは大きく以下3つの視点に分類されるとしています。
- 作業クラフティング:業務のやり方を工夫し、仕事の内容を充実させる方法。
- 人間関係クラフティング:職場の人間関係に工夫を加え、より良い関係性を築くことを目的とした方法。
- 認知クラフティング:仕事の捉え方や考え方を変え、業務への意欲を高める方法。
以降でそれぞれの視点についてより詳しく解説します。
(※)参考:厚生労働省(2019)「令和元年版 労働経済の分析 ー人手不足の下での「働き方」をめぐる課題についてー」 p.231-232
1. 作業クラフティング
作業クラフティングとは、業務の進め方や手順を主体的に工夫し、仕事の質や効率を向上させるアプローチです。
業務プロセスを見直して細かな無駄を削減したり、新しいスキルを習得して仕事の幅を広げたりすることを指します。
具体的には、タスクの割り振りを変えたり、優先順位を調整したりすることで、仕事の負担を減らし、より効果的な働き方を実現します。例えば、目標を設定したり、優先順位をつけたスケジュール管理などが挙げられます。
作業クラフティングにより単調な業務を違うやり方で進め、新しい学びを得たり、業務フローを見直して無駄を減らしたりすることが可能です。
作業クラフティングを実践することで、業務に対するやりがいや満足度が向上し、個人の成長や企業の生産性向上につながります。
2. 人間関係クラフティング
人間関係クラフティングとは、職場での対人関係を見直し、より良い関係性を築くことで仕事の満足度を高めるアプローチです。
例えば、積極的に上司や同僚とコミュニケーションを取ることで、業務の円滑化や正確性の向上を図ることなどが挙げられます。
また、異なる部署のメンバーと交流し、新たな視点を得るのも効果的です。リモートワークが増加した現代では、オンライン会議やチャットツールをうまく活用しつつ、意識的にコミュニケーションの機会を増やすことの重要性が高まっています。
そのほかにも、職場の人間関係をポジティブに捉え直すことでもストレスの軽減やエンゲージメントの向上が期待できます。良好な人間関係を構築することで、業務の質やスピード、仕事に対するモチベーションなどが高まり、成果にも好影響を与えられる可能性があります。
3. 認知クラフティング
認知クラフティングとは、仕事の捉え方や考え方を主体的に変えることで、業務のやりがいを高めるアプローチです。
例えば、一見すると単純作業である仕事が、会社全体や社会にどのように役立っているか、どのような価値をもたらしているのかを再認識することでモチベーションの向上を図れます。
また、業務の意義を見直し、より大きな目標と結びつける方法も有効です。営業職の場合を例にすると、単に商品やサービスを売るのではなく、「顧客の課題を解決することが本来の役割である」と捉え直すことで、仕事に対する意識が変わる可能性があります。
認知クラフティングの実践で、働く意味や目的を明確にし、ポジティブな姿勢で業務に取り組めるようになるほか、習慣化することで日々の業務に対する充実感が増し、成長意欲を維持しやすくなります。
ジョブ・クラフティングの進め方・手順
ジョブ・クラフティングを実践するためには、明確な手順を踏むことが重要です。以下の手順を参考にしながら、主体的に仕事の内容や捉え方を見直していきましょう。
- 業務内容の洗い出し
- 自己分析を行う
- 業務に落とし込む
- 実践と振り返りを繰り返す
1. 業務内容の洗い出し
ジョブ・クラフティングを実践するための第一歩は、現在携わっている業務を詳細に洗い出すことです。
業務の内容に加えて、関わる人物やその業務に必要なスキル、業務の目的など包括的に整理することでより具体的な改善が可能になります。
これらの情報を整理する際は、日常的に行っている通常業務だけでなく、イレギュラーな対応や一過性のプロジェクト業務も含めてリスト化することが大切です。リスト化した業務を「重要度」「負担度」「満足度」などの観点で分類してみると、どの業務に対してジョブ・クラフティングを行うべきかが明確になります。
このほかにも、関わっている人物を精査することで、どの人間関係を改善すれば業務が円滑になるかも見えてきます。業務の全体像を把握することで、より効果的なジョブ・クラフティングを進めるための基盤を作れるでしょう。
2. 自己分析を行う
続いて、自分自身の強みや価値観を把握するための自己分析を行います。ジョブ・クラフティングでは、「自分らしさ」を勘案することが重要なためです。
これまで携わった業務の棚卸しを行い、自分が得意とする業務や達成感を感じた経験を整理してみましょう。例えば、特に成果が高かった業務や、自分に合っていると感じた仕事などを振り返ってみることで、自分の適性や強みが見えてきます。
また、「どのような価値観を重視して仕事に取り組んでいるか」を整理するのも有効です。「人との関わりを大切にしたい」「常に新しい知識を学びたい」など、自分が仕事に求める要素を認識することで、より自分らしいジョブ・クラフティングを実践できます。
ジョブ・クラフティングはその人自身のモチベーションやパフォーマンスを向上させることが目的のため、自分に合った改善方法を見つけるためにも、自己分析が非常に重要です。
3. 業務に落とし込む
続いて、自己分析の結果を具体的な業務に反映していきます。
この段階では、「作業クラフティング」「人間関係クラフティング」「認知クラフティング」の3つのアプローチをバランス良く活用しながら、業務の質を高めていくことが大切です。
例えば、作業クラフティングでより効率的な方法を導入するなどして業務の進め方を見直し、人間関係クラフティングで同僚や上司とのコミュニケーションの取り方を工夫し、より円滑に業務を進める方法を検討します。さらに、認知クラフティングで業務の意義や目的を再確認し、仕事に対するモチベーションの向上を目指します。
このように、適切な手順で自分の業務を主体的に捉え直し、より良い働き方へと変えていくことで、ジョブ・クラフティングの効果を最大化できるでしょう。
4. 実践と振り返りを繰り返す
ジョブ・クラフティングは、一度実践して完了するものではなく、継続的に改善を重ねてブラッシュアップしていくことが重要です。
変えるべきことを実際の業務に反映しつつ、具体的な行動計画を立て、それに基づいて実践を行います。
業務プロセスを例にすると、ジョブ・クラフティングを施した新しい手順をまずは実務で試してみて、その効果を測定します。一定期間実践したあとに振り返りを行い、改善点や成功したポイントを洗い出してみましょう。また、上司や同僚からフィードバックを受けるなど、客観的な視点を取り入れるのも有効です。
チームで取り組む場合は、ジョブ・クラフティングの成功事例を共有することで、チーム全体での取り組みを促進するのもひとつの方法です。
このようなサイクルを繰り返すことで、より良い働き方が定着し、業務の効率化やモチベーション向上につながります。
【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~
「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。
ジョブ・クラフティング進め方のポイント

ジョブ・クラフティングを効果的に実践するためには、適切な進め方と環境整備が必要です。ここからは、ジョブ・クラフティングを進める際に知っておくと良い2つのポイントについて解説します。
従業員が自主的に取り組める環境を整備する
ジョブ・クラフティングを効果的に実践するためには、従業員が自主的に取り組める環境を整えることが重要です。
上層部からのトップダウンで半ば強制的に導入してしまうと、従業員は「やらされ感」を感じてしまい、かえってモチベーションが低下するおそれがあります。ジョブ・クラフティングはこの「やらされ感」を払拭することも目的のため、従業員の自主性を引き出すことに重点を置く必要があります。
具体的な取り組みの一例として、ワークショップの導入が挙げられます。ワークショップとは、参加者が主体的に考え、対話協力や特定のテーマについて深く学ぶ体験型の活動です。講義形式とは異なり、実際に手を動かし意見を交換しながら、新しい知識やスキルを学び、課題解決の方法を探ったりします。企業研修や教育、地域活動など幅広い分野で活用され、参加者同士の相互作用を重視した学びの場として設計されるのが特徴です。
従業員同士がアイデアを共有し合うことで、より実践的なクラフティングの方法を学ぶことができるでしょう。
組織全体でジョブ・クラフティングの取り組みを習慣化する
ジョブ・クラフティングは、一過性の取り組みで終わらせるのではなく、習慣化することが大切です。一度だけの実施で継続的な効果を得るのは難しいため、習慣化を目的として継続的に実施するのがポイントです。
ジョブ・クラフティングを企業文化として根付かせるためには、定期的な振り返りの場を設け、従業員同士が取り組みの成果や気づきを共有できる環境を整えるのが効果的です。
また、取り組みはスタッフ層だけにやらせるのではなく、管理職や経営層が率先してジョ取り組みましょう。そうすることで、「やらされ感」が薄れると同時に一体感が生まれ、従業員の参加意識が高まります。
さらに、成功事例を社内で積極的に発信することで、ジョブ・クラフティングの具体的な効果や重要性を認識しやすくなるため、新たな取り組みへの意欲を促進できるでしょう。
【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】
エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。
ジョブ・クラフティングを実施することで得られるメリット

ジョブ・クラフティングを実施することで、従業員の働き方や意識に良い影響を与え、企業全体の生産性の向上も期待できます。ここからは、ジョブ・クラフティングの効果と具体的なメリットについて解説します。
ジョブ・クラフティング効果:エンゲージメントや生産性の向上
ジョブ・クラフティングを実践することでエンゲージメントや生産性の向上が期待できます。従業員一人ひとりに主体性が生まれ、仕事への取り組み方が大きく変化するためです。
これまで「やらされ感」を感じていた業務でも、自分なりの工夫を加えることでネガティブな感覚が軽減され、前向きな姿勢で取り組めるようになります。自分が会社や組織に提供できる価値を見出すことで、今の仕事に新たな意義を感じたり、やりがいを感じやすくなったりする場合もあるでしょう。
また、業務に主体的に取り組むことで、自己成長の機会が増え、新しいスキルの習得やキャリアアップにもつながります。これにより、会社や組織に対するエンゲージメントの向上や、従業員のモチベーション・業務の質・生産性などを総合的に向上させる効果が期待できるのです。
企業における導入で期待できる成果
ジョブ・クラフティングの導入は、前述のモチベーション・エンゲージメント・生産性の向上以外にも多くのメリットをもたらします。
例えば、従業員が主体的に業務を再設計することで、自己成長感ややりがいを見出し、継続的なスキルアップの促進が実現できます。 これにより従業員一人ひとりのモチベーションが高まれば、組織全体の活性化につながるでしょう。
また、従業員のエンゲージメントが高まれば、意欲ある人材の定着や離職率の低下も期待できます。さらに、従業員が能動的に伸び伸びと業務に取り組める環境は、創造的なアイデアが生まれやすくなったり、イノベーションが起きやすくなったりする点もメリットです。
ジョブ・クラフティングの導入は従業員一人ひとりの底上げが主な目的ですが、組織全体で見れば非常にメリットが多く、意義のある取り組みといえるでしょう。
【ホワイトペーパー】若手が活躍する職場とは ~「働きがいのある会社」ランキング上位企業に学ぶ~
この資料では、若手ランキング企業の特徴を通じて、組織で若手がイキイキと活躍するためのポイントを解説し、「働きがいのある会社」ランキング上位に選出された企業の実際の取り組み事例を紹介します。
ジョブ・クラフティングを成功させるための進め方と注意点

ジョブ・クラフティングを効果的に進めるためには、適切な方法を理解し、注意点を押さえることが重要です。ここからは、ジョブ・クラフティングを成功させるための進め方と、実施する際の注意点を解説します。
属人化を防ぎながら主体性を引き出す工夫をする
ジョブ・クラフティングを進める際、特定の従業員に業務が依存する属人化のリスクが生じる可能性があります。ジョブ・クラフティングは従業員本人が主体となって業務の見直しを図る取り組みのためです。
属人化が起きると、特定の従業員が抜けてしまった場合に業務が滞り、組織全体の業務効率に悪影響を与えるおそれがあるため注意が必要です。
属人化を防ぐためには、業務の標準化やマニュアル化など、情報共有の仕組みを整えておくことが重要です。また、定期的なミーティングで業務の進捗や課題などを共有することで、他のメンバーも業務の流れを把握しやすくなります。
ジョブ・クラフティングを実施する際は、個人の裁量を尊重しつつも、属人化が発生するリスクを理解した上でそれを防止する対策を講じておくことが重要です。
従業員を主体としてエンゲージメントを保つ
ジョブ・クラフティングは、従業員が業務に対して主体的に取り組み、エンゲージメントを高める手法です。この点をよく理解せずに上司が過度に干渉してしまうと、従業員の主体性が損なわれるおそれがあります。
ジョブ・クラフティングを成功させるためには、従業員が自らの働き方を見直し、改善できる環境を整えることが重要です。企業や上司は挑戦を促す環境づくりをしつつ、従業員の自主性を見守る姿勢が求められます。
具体的には、1on1ミーティングで従業員の意見を尊重しながら目標設定を行ったり、成功事例を社内で共有してお互いに刺激を与え合う環境を作ったりするなど、ジョブ・クラフティングの取り組みが自然と広がる環境を作るのがポイントです。
管理職も自らジョブ・クラフティングに取り組むなど、従業員の自発的な成長を支援する体制を構築することに重点を起きましょう。
【ホワイトペーパー】広報・ブランディングに使える!働きがい認定活用事例12選
この資料では、GPTWの「働きがい認定」を取得した企業がどのように働きがい認定を活用しているかを実際の例を用いて解説します。働きがい認定の取得を検討している方や、働きがい認定を取得したがうまく活用できていないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
ジョブ・クラフティングの効果を得るなら「働きがい認定」

ジョブ・クラフティングは、従業員が主体的に業務を見直し、やりがいを高める手法であり、エンゲージメントや生産性の向上、企業の成長が期待できます。
属人化を防ぐ仕組みを整えた上で、従業員自身の自主性を尊重すること、組織全体で習慣化して継続的に改善を行うことが成功の鍵です。
ジョブ・クラフティングのように従業員の働きがいやエンゲージメントを高める施策として、企業の職場環境や従業員満足度を第三者が評価する「働きがい認定」を取得するのもひとつの方法です。企業が客観的な評価を受けることで、従業員は自社の強みや魅力を再確認できるでしょう。