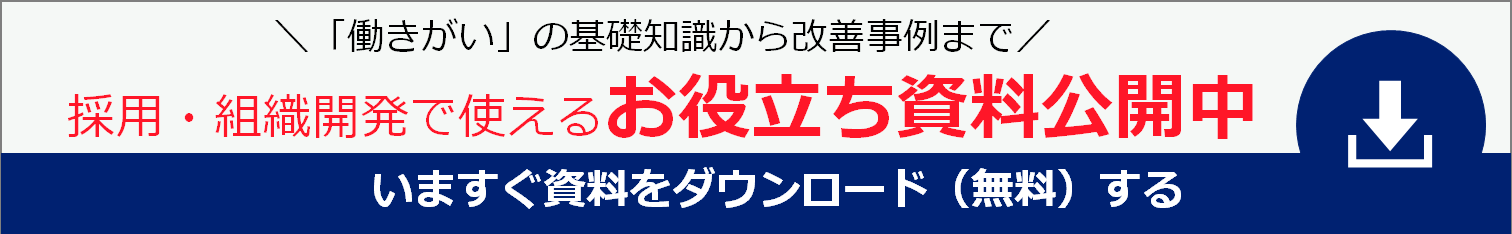ジョブローテーションとは?意味やメリット・デメリット・人事・採用に効果的な方法を解説
更新日 2025.03.242025.03.24コラム

ジョブローテーションは、企業の人材育成や組織の活性化において重要な役割を果たす制度です。従業員が定期的に異なる職務や部署を経験することで、多様なスキルを身につけ、キャリアの幅を広げられます。
また、部門間の連携強化や幹部候補の育成など、組織全体の成長にも寄与します。一方で、スペシャリスト育成には不向きであるなどの課題も存在します。
本記事では、ジョブローテーションの仕組みやメリット・デメリット、効果的な実施方法について詳しく解説します。
目次
.ジョブローテーションの意味・概要

ジョブローテーションとは、従業員が定期的に異なる職種や配置を経験する人事制度のことです。一つの職種・部署に携わる期間はさまざまですが、2~3年ごとに職種や部署を変更することが一般的です。
例えば、営業、人事、販売など複数部門を経験する形式や、小売店などで販売、仕入れ管理など異なる業務を経験する形式がジョブローテーションに該当します。
ジョブローテーションの主なねらいは人材育成です。従業員は、異なる職務を経験することでスキル向上が見込めます。また、部門や部署に横断的に関わることで、企業全体の人材の多様性や適応力を高める効果が期待できます。新人育成や適正な配属決定、次世代リーダー育成や業務の属人化防止といった観点から、多くの企業で導入されています。
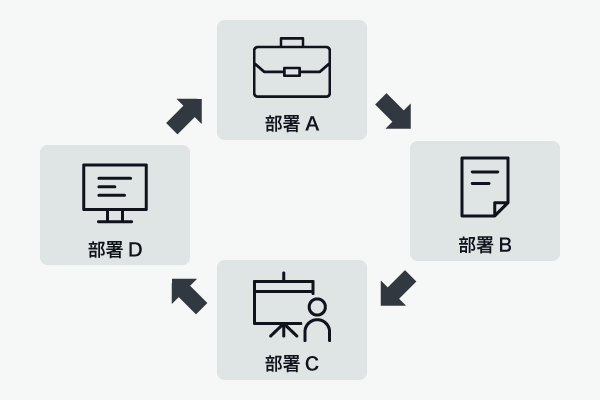
ジョブローテーションと他の人事制度の違い

企業には、ジョブローテーション以外にもさまざまな人事制度が存在します。ここでは、混同されやすい「人事異動」と「社内公募制度」との違いについて詳しく解説します。
ジョブローテーションと人事異動の違いとは
ジョブローテーションと人事異動は、異なる業務や部門を体験するという点では同じですが、目的に違いがあります。
人事異動は、企業経営方針や組織のニーズに基づき、昇格・降格、転任、役職任命などを行うことです。企業内での役割の変更や職務の変更、部門異動は人事異動に含まれます。人事異動は、組織の活性化や競争力強化などを目的としています。
一方で、ジョブローテーションの目的は、人材育成です。ジョブローテーションは、人事戦略の計画に含まれており、対象となる従業員のスキル向上やキャリア形成を重視した上で行われる点が特徴です。ジョブローテーションも人事異動と同様、従業員の希望通りに行われるとは限りません。職務や部門が変更となるという意味では、ジョブローテーションは広義の人事異動に含まれます。
ジョブローテーションと社内公募制度の違いとは
社内公募制度とは、企業内の特定のポジションについて従業員に異動の希望を募る制度をいいます。従業員自らが立候補するという性質上、会社主導ではなく従業員の自律的なキャリア形成を重視している点が特徴です。配置転換の透明性を高める効果も期待できるでしょう。
一方で、ジョブローテーションは、企業の戦略的な人材育成のために実施されるため、必ずしも従業員の希望通りに異動が行われるわけではありません。ただし、双方の制度の良い部分を活用するため、社内公募制度とジョブローテーションを併用し、適材適所を実現する企業もあります。
【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~
「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。
ジョブローテーションの効果

ジョブローテーションには、企業の成長や組織の強化にさまざまな効果があります。ここでは、主なメリットについて解説します。
人材育成における効果
ジョブローテーションは、一般的に3年から5年の期間で異動を繰り返しながら行われます。これにより、従業員は多様な業務を経験し、営業職やエンジニアなど幅広いスキルを身につけることができるのです。
例えば、営業職として顧客対応を経験した後にマーケティング部門に異動することで、現場の知識を持ちつつ、さらに市場分析やプロモーション戦略の知識を習得できます。また、エンジニアが開発部門から製品企画部門へ異動することで、技術面だけでなく、ビジネス視点での製品開発の考え方を学ぶ機会にもなります。
このプロセスを通じて、企業は成長できる人材を育成し、即戦力として活躍できる従業員を増やすことが可能です。
社内の連携とネットワーク構築
ジョブローテーションを通じて、異なる部署の従業員と関わる機会が増え、社内のリレーションが強化されます。複数の部署が存在する組織では、横断的な関わり方が組織の成長に影響します。
例えば、営業部門の従業員が一時的に製造部門へ異動することで、製品の生産プロセスを理解し、より的確な顧客対応が可能になるでしょう。また、社内外のさまざまなプロジェクトに関与することで、マーケティングと開発部門が協力しやすくなり、新商品の企画や改善がスムーズに進むようになります。これにより、他部門との連携が強化され、組織全体の生産性向上が見込めます。
従業員のモチベーションが向上する
ジョブローテーションには、モチベーションの向上という効果もあります。同じ業務を何年も行うと、業務のマンネリ化が進み、従業員の成長意欲を低下させる原因になるでしょう。例えば、ベテラン従業員が長年同じ業務だけを行っていれば、新たなスキルを習得できず、キャリアの停滞を感じてしまうかもしれません。
ジョブローテーションによって定期的な配置転換を行い、新しいチャレンジを与えることで、新たな成長の機会を得られます。例えば、営業から企画部門へ異動した従業員が、これまでの経験を活かしながら市場分析を学ぶといった刺激を得られます。これにより、従業員のモチベーションを維持し、キャリアアップの可能性を広げられるでしょう。
幹部候補の育成と組織基盤の強化
ジョブローテーションは、幹部候補の育成や新規事業の推進にも大きな効果を発揮します。日本企業においては、幹部候補の従業員が営業、開発、管理部門などを順番に経験することで、経営視点を持った人材へと成長するケースが多く見られます。
また、新規事業を立ち上げる際には、異なる部署での経験を持つ人材がリーダーとして選ばれることが多く、組織全体の柔軟性と競争力を高める要因になります。従業員を適材適所に配置しながら、企業の成長戦略を加速させることが可能です。
採用コストを抑えられる
採用市場が売り手市場となる現代において、外部から優秀な人材を獲得するのは難易度が高いでしょう。とりわけ、経験豊富な人材や専門性の高い人材を採用するのは、競争の激化により難しいといえます。ジョブローテーションを活用すれば、仕事での経験をもとに、社内で必要な人材を育成することが可能です。
例えば、事業内容に精通しつつ経理の知識も備えた人材を経営管理部に配属させるということができます。外部採用の比重を調整しつつ、事業成長につながる人材を育成・定着させることも可能です。
昨今、企業の認知度や求職意識を高めるために、採用ブランディングをする企業が増えています。この資料では、採用ブランディングの概要、メリット・デメリットに加え、具体的な実施手順や成功のポイントを解説します。
ジョブローテーションのデメリットと課題

ジョブローテーションにはメリットがある一方、スペシャリストの育成には不向きであったり、社内調整の負担が大きいといったデメリットがあります。代表的なデメリットについて詳しく解説します。
スペシャリスト育成には適さない
ジョブローテーションのデメリットは、スペシャリストの育成には適さないという点です。3年程度で部署や職種を異動してしまうため、同じ分野の経験を積むには限界があります。
例えば、同じエンジニアの人材を育成する場合でも、フロントエンジニアからバックエンドエンジニアに異動してしまうなど、多様な経験を積める一方、スキルの習得に制限が出てしまいます。他にも、法務、会計などの職種では、長期間にわたり専門スキルを磨くことが求められます。短期間でのジョブローテーションがデメリットにならないよう、異動や配属転換の理由を慎重に検討することが求められます。
運用コストおよび社内調整の負担
ジョブローテーションのメリットを最大限にするためには、入念な計画をもとに実行することが重要です。人事部では、対象者である従業員の経歴やスキルを把握しなければならないことはもちろん、組織の人材戦略にも沿わなければいけません。さらに、会社としての経営方針に基づきつつ、人員不足といった各部署の希望にも応える必要があります。
なかには、育ってきた若手が他部門に異動してしまうことに難色を示されることもあるでしょう。逆のケースでは、受け入れる人材を教育するのが負担であるといわれるかもしれません。ジョブローテーションはルールや方法を明確にしつつ、こうした社内調整をスムーズに行う必要があります。
従業員の不安や離職リスクが生じることがある
ジョブローテーションは、従業員にとって必ずしも望ましい異動とは限らず、適応が難しい場合にはストレスや不満が蓄積する可能性があります。とくに、異動のタイミングがキャリア形成に影響を与えることがあり、従業員が自らの将来に対する不安を感じることもあります。
例えば、営業職の従業員が経理部門へ異動するというように、新たな業務に移る場合、適応が難しく、モチベーションの低下を招く可能性があります。ジョブローテーションが原因で、従業員が定着できない状況が生まれ、転職してしまうなど、離職率の上昇につながるかもしれません。こうした課題に対応するためには、アンケート調査を通じてジョブローテーションの満足度を測定し、育成戦略を見直す取り組みが求められます。
【ホワイトペーパー】職種別働きがい向上のポイント ~これを読めば、職種ごとに対応すべきポイントが分かる!~
この資料では、働きがいを高めるうえで起こりがちなネガティブな状態を、職種ごとに分析・解説します。あわせて、職種ごとに起こりがちなネガティブ状態に合わせた対応策も方針として示しているため、ぜひ参考にしてみてください。
ジョブローテーションを効果的に実施する際の方法と計画

ジョブローテーションを導入する際には、計画的な方法を用いることが重要です。企業は、事前に従業員の意向を把握し、適切な配属を検討することで、円滑な実施が可能になります。ここでは、ジョブローテーションを効果的に進めるための具体的な方法と計画について解説します。
導入目的を明確にする
ジョブローテーションを導入する際には、まず目的を明確にすることが重要です。導入によって得たい効果や結果を事前に定めることで、実施の進め方が明確になり、組織全体の理解を得やすくなります。
例えば、企業が人材の多様なスキル向上を目的とする場合、従業員にはどのような経験を積んでもらうのかを具体的に検討し、業務のローテーション計画を立てる必要があります。多様な分野で経験を積むことで、どのようなキャリアが築けるのかロールモデルを示すことも、従業員のモチベーション向上に効果があります。
ジョブローテーションの目的は、企業によって異なります。目的が不明確なまま進めると、ただ職種や部門が頻繁に変わるだけで、従業員のモチベーション低下や適性のミスマッチを招く可能性があります。
対象者選定と配属先の検討
導入目的を明確化した上で、異動の対象となる従業員を適切に選定することが必要です。企業は過去の事例を参考にしながら、勤務年数、適性、スキルセットなどを総合的に判断し、ジョブローテーションの対象者を決定します。
例えば、新入社員に対しては業務全体の理解を深めるために広範な部署を経験させる一方、管理職候補にはリーダーシップを養うために戦略的な部署への異動を優先するなど、対象者ごとの適性を考慮することが求められます。
また、配属先についても、異動の効果を最大化できる環境を整えることが重要です。適性を考慮せずに配属を行うと、従業員の能力が発揮されず、ジョブローテーションの効果が半減してしまう可能性があります。
実施と改善プロセス
対象者と配属先が決定したら、ジョブローテーションの実施を進めます。この際、対象従業員と配属先の責任者に、異動の目的と期待される役割を明確に伝えることが重要です。なぜ、この人材がこの部署に配属されるのか、どのように育ててほしいのかという話を具体的に伝えることで、共通認識を持って人材育成に取り組むことができます。
また、実施の過程では、定期的に面談の機会を設け、対象者の不安や質問に耳を傾けることが必要です。とくに、異動後の環境に適応するまでの期間は、企業側が積極的にサポートを行うことで、スムーズな定着を促すことができます。
さらに、ジョブローテーションの効果を最大化するためには、配属後のフォローアップも欠かせません。定期的な評価やフィードバックを行い、必要に応じて改善策を講じることで、より良いローテーション制度の構築につなげることができます。
【ホワイトペーパー】広報・ブランディングに使える!働きがい認定活用事例12選
この資料では、GPTWの「働きがい認定」を取得した企業がどのように働きがい認定を活用しているかを実際の例を用いて解説します。働きがい認定の取得を検討している方や、働きがい認定を取得したがうまく活用できていないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
ジョブローテーションが向いている企業の特徴

ジョブローテーションが向いている企業もあれば、組織的に向いていない企業もあります。以下に、企業規模に分けてジョブローテーションが向いている企業の特徴を解説します。
多様な職種が存在する大企業
複数の部署と多様な職種が存在している大企業では、一般的にジョブローテーションが適しているといえます。ジョブローテーションを導入することで、従業員はさまざまな業務を経験し、部門間の理解を深めることができます。
営業部門のなかでも異なる商材を取り扱うこともあるでしょう。多様な経験と人脈をジョブローテーションで積むことで、新しいアイディアが生まれやすくなります。組織を活性化させ、イノベーションを促進したいという組織風土にも適しています。また、ジョブローテーションを活用することで、企業全体の業務プロセスの理解が深まり、部門間の連携が強化されるという効果も期待できます。
一方、従業員数が多いがゆえに、一人ひとりへのフォローを手厚く行うことが重要です。メンター制度を併用したり、従業員のキャリア支援を行ったりするなど、ジョブローテーションを人材育成計画の一つとして組み込み、多角的なアプローチを展開します。
部門や職種が限定される中小企業
部門や職種が限定される中小企業の場合でも、ジョブローテーションは有効な施策となります。とりわけ、自部門の利益を優先し部門同士の協力が阻害されるようなセクショナリズムを予防したい企業にとって、ジョブローテーションは部署間の協力を促進する手段となります。
中小企業では、従業員一人ひとりの役割が広範にわたることが多いため、異なる部署の業務を経験することで、組織全体の生産性向上につながります。
例えば、営業経験者がバックオフィス業務に携わることで、見積書作成や契約管理、請求処理などの社内業務の流れを理解できます。さらに、営業経験で培った顧客理解が業務効率化のアイデアにつながるかもしれません。
また、ジョブローテーションを導入することで、業務の属人化を防ぐ効果が期待できます。一定期間で人員が入れ替われば、業務のマニュアル化が求められます。複数の従業員が同じ業務を理解している状況を作り、チームワークを向上させられます。
グループ企業のケース
グループ企業においては、各企業間での知識共有やシナジー効果を高めるために、ジョブローテーションが有効な手段となります。企業文化の醸成や集約が課題となる場合、グループ内の異動を活用することで、共通の価値観や業務プロセスの標準化を促進できます。
例えば、親会社の従業員がグループ会社に異動し、現地の業務プロセスを学ぶことで、グループ全体の経営戦略に反映させることができます。また、グループ企業間でのローテーションを行うことで、従業員の視野を広げ、柔軟な対応力を身につけられます。
このように、ジョブローテーションを導入することで、グループ企業全体の競争力を向上させ、統一された企業文化を築くことが可能です。
【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~
「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。
ジョブローテーションが不向きな企業の特徴

ジョブローテーションは、多くの企業にとって有効な施策である一方、すべての企業に適しているわけではありません。業務の特性や組織の構造によっては、ジョブローテーションが適さないケースもあります。 ここでは、ジョブローテーションが向いていない企業の特徴について解説します。
専門性が求められる業務中心の企業のケース
専門性が求められる企業では、特定の分野の深い知識やスキルが必要とされるため、頻繁な異動がスキルの習得を妨げる可能性があります。例えば、医療機関の医師、弁護士、会計士、エンジニアなどの職種では、長期間にわたる専門教育や実務経験が不可欠です。
こうした企業では、従業員が一つの分野に特化することで高い専門性を身につけ、企業の競争力を向上させることが重要です。そのため、ジョブローテーションを導入すると、専門スキルの蓄積が難しくなり、業務の質の低下を招く可能性があります。
長期プロジェクトが多い企業のケース
長期的なプロジェクトを多く抱える企業においては、ジョブローテーションの導入が難しい場合があります。大規模な建設プロジェクト、システム開発、研究開発などの業務では、プロジェクトの完了までに数年かかることが一般的です。
このような企業では、一つのプロジェクトに一貫して関与することで、業務の質を維持し、成果を最大化することが求められます。ジョブローテーションによってプロジェクトの途中で担当者が異動すると、業務の引き継ぎが煩雑になり、プロジェクトの進行が遅れるリスクが高まります。そのため、長期的な業務に携わる企業では、ジョブローテーションの導入は慎重に検討する必要があります。
初期リソースに制限がある企業のケース
スタートアップやベンチャー企業など、初期リソースに限りがある企業では、ジョブローテーションの導入が難しい場合があります。これらの企業では、限られた人数で業務を遂行する必要があり、従業員一人ひとりが特定の業務に精通し、高い生産性を発揮することが求められます。
また、ジョブローテーションを実施するには、異動の計画や教育コストが発生するため、人的リソースや時間に余裕のない企業にとっては負担が大きくなります。とりわけ、事業の立ち上げ期にある企業では、従業員が一貫して業務に取り組み、専門性を高めることが優先されるため、ジョブローテーションの導入は適さないといえます。
ジョブローテーションの展望:日本と海外の比較

日本では珍しくないジョブローテーションですが、海外では一般的とはいえません。その背景には、海外では多くの企業が、職務とスキルを指定して採用するジョブ型雇用を導入しているからといえます。以下に、ジョブローテーションをめぐる日本国内と海外の状況について解説します。
日本で普及している背景
日本の企業では、「まず人材ありき」という考え方が根付いており、育成した人材に適した仕事を与えるという文化が主流となっています。この背景には、日本の終身雇用制度の影響が大きく関係しています。
終身雇用が長く主流であった日本の企業では、一つの企業に長く勤めることが大きな前提となっていました。そのため企業が従業員を長期的に育成し、幅広い業務に対応できるゼネラリストとして成長させることが重要視されていたのです。ジョブローテーションは、複数の業務を経験させつつ、長期スパンで自社に適した人材を育てるという日本企業の社風に適していました。
ジョブローテーションがあるからこそ、とくに日本の新卒採用では、学歴と応募職種との関係性が重視されない傾向があります。文系の学生がエンジニアになるというように、入社してからのスキルの習得が可能です。
一方、海外では、特定のスキルや経験を持った人材を特定の職種に採用するという考えが主流です。言い換えれば、常にどの職種でも即戦力人材を前提とした採用を行っているといえます。ジョブローテーションを導入してしまえば、その人材のスキルやキャリアをすぐに活かすことができません。こうした考えや文化の違いから、ジョブローテーションの普及度合いには日本と海外で大きな違いが見られます。
ジョブ型雇用との関連性
ジョブ型雇用とは、特定の職務に基づいて人材を採用・雇用する仕組みを指します。この雇用形態では、職務経験やスキルを持つ人材が優先的に採用されるため、未経験者やスキルの乏しい人材が採用される機会は限られています。一方で、スキルや経験を積んだ熟練度の高い人材は、転職市場で高い評価を受け、採用のチャンスが多いのが特徴です。
日本でもジョブ型雇用を取り入れる企業はありますが、主に採用されているのはメンバーシップ型雇用です。メンバーシップ型雇用では、新卒一括採用を行い、長期間にわたって人材を育成しながら、さまざまな業務を経験させる仕組みとなっています。このため、企業側が従業員のキャリアを主導し、適材適所に配置していくジョブローテーションが機能しやすいのです。
一方で、ジョブ型雇用が主流の海外では、定義された業務範囲内で専門性を高めることが求められるため、頻繁な異動を伴うジョブローテーション制度はなじみにくいといえます。
<関連記事>
ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いや従業員・組織へのメリット・デメリットを解説
採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約150ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!
企業の成功事例から学ぶジョブローテーション

従業員の成長と挑戦の機会を提供するジョブローテーション
サービス業のA社では、より多くの従業員がさまざまな役割を経験し、多様なスキルを身につけて成長できるよう、ジョブローテーション制度を導入しています。同社のジョブローテーションで特徴的な点は、同じ店舗や部署で、同じ役割を2年以上続けることがないようにしていることです。
具体的には、1年から1年半という期間で、従業員は異動または昇進を通じて新たな挑戦の機会を得ます。新しい店舗や部署に移ることで、仕事の視野を広げることができます。ジョブローテーションにより、従業員は新たな視点や知識を習得し、常に成長し続けることができる環境が整っています。それにより従業員のモチベーション向上や、組織全体の活性化が実現されています。
キャリア形成を目的としたジョブローテーション
情報通信業界のB社では、社内でのキャリア形成を目的に、本配属から2年経過以降の従業員を対象に「社内職業体験」という位置づけで社内異動を実施しています。
この制度には「本人希望」と「会社指示」のケースがあります。本人希望の場合は、受入部署の状況を参考にしつつ、適用が決定されます。この仕組みにより、従業員は自身の適性を見極めつつ、多様なキャリアパスを歩む機会を得ることができます。
従業員が希望を伝えるというチャンスがあることから、この施策は、社内公募制とジョブローテーションのハイブリッド的な仕組みといえます。
従業員の自発的なキャリア形成をサポートしながら、企業全体の人材配置を最適化する役割を果たしています。
業務のミスマッチを防ぐための新入社員の部署ローテーション研修
情報通信業のC社では、新卒入社の社員を対象に「ローテーション研修」を導入しています。新入社員は、入社後2~3週間ごとに全部署での業務を体験します。これにより、会社の業務の全体像を把握できます。
同社では、「ローテーション研修」時のパフォーマンスを参考に、最初の配属部署を決定します。そのため、会社にとっても業務のミスマッチが起こりにくいというメリットがあります。
同社の取り組みは、厳密な意味でのジョブローテーションとは異なりますが、短期間で複数の業務を経験することで、自分の適性やキャリアを考える機会にもなっています。そのため、新入社員がより早く企業文化や業務に適応できるようになり、定着率の向上にも寄与しています。
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
働きがいを高める努力はジョブローテーションの成功につながる

ジョブローテーションは、企業の人材育成に大きな効果が期待できます。多様な経験を積み、社内で広い人脈を作ることで、自社に適した人材を育成できます。新入社員の育成、経営幹部候補の育成、中堅社員のスキルアップなど、さまざまな目的で導入されます。
ジョブローテーションは、従業員のスキル向上やキャリアの幅を広げるのはもちろん、企業が持続的な成長を行っていく際にも重要です。 企業が働きがいを高める努力をしていれば、ジョブローテーションにより異動した従業員も新しい環境にスムーズに適応しやすくなります。具体的には、異動先のチームが新しいメンバーを歓迎し、業務の引き継ぎを丁寧に行う文化があれば、従業員が安心して新たな役割に就けるでしょう。
逆に、異動してきた従業員がチームの中で孤立したり、適応に苦労したりする環境では、ジョブローテーションの効果は十分に発揮されません。ジョブローテーションの成功には、働きがいを高める企業文化の醸成が必要です。一人ひとりの従業員が新しい環境に目を向けやすい風土を作ることでで組織全体の活性化につながります。
「働きがい認定」は従業員のインナーブランディングにも役立つ制度です。「働きがい認定」を受けた企業は、客観的に評価された「働きやすさ」や「企業の魅力」を従業員と共有できます。従業員は自分の価値を再確認するとともに、より主体的に業務的に取り組めるでしょう。