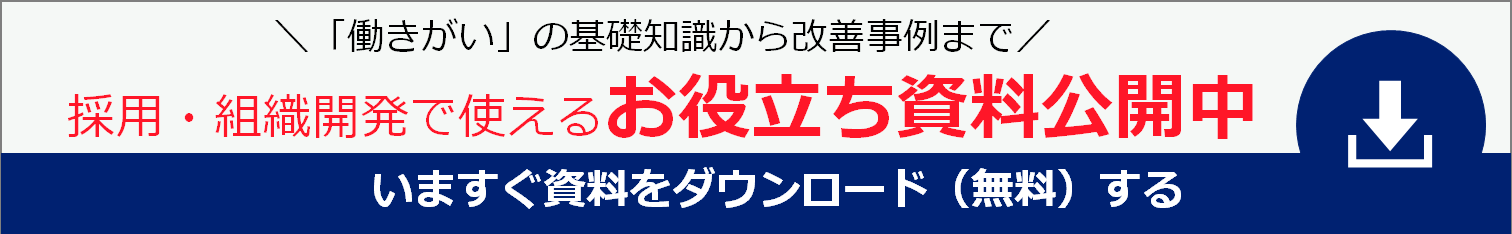職場単位でも働きがいを高め、組織全体の働きがい向上につなげるポイントは?
更新日 2025.09.102025.08.26コラム

「働きがい」と聞くと、多くの人は個人のモチベーションや価値観の問題だと考えがちです。しかし、実際には個人の働きがいは、その人が属する職場の環境や文化によって大きく左右されます。同じ会社でも部署が変わると急にやる気が出たり、逆に以前は活き活きと働いていた人が別のチームに異動した途端に元気を失ったりする光景を、私たちは日常的に目にしています。これは決して偶然ではないと考えます。
働きがいを高めるために重要なのは、個人の努力だけでなく、職場単位での組織的なアプローチです。近年は、従業員の働きがい(エンゲージメント)を高めることは必須との考えをもつ企業も多く、エンゲージメントサーベイを導入して改善に取り組んでいます。
そのような中でも、組織が大きい場合や、部署によって異なる業務や環境がある場合、組織全体での働きがい向上に苦労するケースが多くあります。例えば、経営に近い層や部門など一部の組織・職場では働きがいが高い一方で、そうでない組織・職場も存在する、といったパターンです。
では、全社的に働きがいを高める動きをしつつ、具体的にどのような取り組みが職場単位の働きがいを向上させることに繋がるか、以下で紹介していきます。
職場単位で働きがいを高める意義
GPTWが考える「働きがい」
私たちGreat Place to Work(R)(以下、GPTW)は、世界170カ国以上で「働きがいのある会社」ランキングを発表している国際的な調査機関です。30年以上にわたる調査研究を通じて、GPTWは働きがいを構成する要素を明確に定義しています。長年の研究から「働きがいのある会社」を「立場、仕事、働く場所に関係なく、あらゆる従業員が会社やリーダーを信頼し、自分の仕事に誇りを持ち、一緒に働いている人たちと連帯感を持てる会社」だと定義しています。このような会社であれば、そこで働く従業員の多くが働きがいをもって働くことができると考えています。
全員型「働きがいのある会社」モデル|働きがいのある会社研究所(Great Place To Work® Institute Japan)
高い給与や充実した福利厚生だけでは真の働きがいは生まれません。むしろ、日常的なコミュニケーションの質、マネジャーの行動、組織の透明性といったことこそが、働きがいを決定づける重要な要因なのです。
働きがいが注目されている背景
なぜ近年は働きがいや従業員エンゲージメントが注目されるようになったのでしょうか。日本で終身雇用の文化が根強かった時代には、あえて会社側から従業員へそういった働きかけをするということは軽視されてきました。しかし現在は、働きがい、従業員エンゲージメントの向上はほとんどの企業にとって必須の経営課題と言っても過言ではありません。その背景に3つの事象があります。
1つ目は「生産年齢人口の減少」です。「売り手市場」の状況はよりその傾向に拍車がかかり、採用競争が激化します。従業員エンゲージメントを高めて魅力的な会社を作らなければ、求職者から選ばれません。2つ目は「個人の価値観の多様化」です。現代は、誰しもが自分と異なる多様な価値観に触れられるようになり、仕事に対する価値観も同様です。Z世代の若手は「貢献」「成長」「やりがい」といった内発的動機付けを大切にする人が多くなっています。3つ目は、「国際競争の激化」です。バブルが崩壊後、日本経済は低迷の時代が長く続いた一方、海外では経済成長が目覚ましい国もあります。日本政府はこの現状に大きな危機感を感じ様々な政策案を打ち出しており、企業における「人的資本経営」の推進もその一つです。人的資本経営は、人材をコストではなく資本だと見なす経営のことを指しており、働きがい、従業員エンゲージメントと深い関わりがあります。
職場単位での働きがい向上がなぜ必要か?
前述のような背景から、多くの企業において働きがいへの関心が高まっていますが、トップダウンだけで進めようとしても成果にはつながりません。日本でも多くの企業がGPTWの調査に参加し、「働きがいのある会社」認定やベスト100のランキングに名を連ねていますが、これらの企業の多くに共通するのは、トップダウンの指示だけでなく、現場レベルでの働きがい向上にも継続的に取り組んでいることです。従業員の少ない組織であれば、例えば社長が旗振りをするだけでも変化を見込めるかもしれませんが、一定規模以上の組織となると、職場単位での検証と改善への取り組みが重要です。職場によって業務内容や環境が異なることは多くありますので、部門長やメンバーを巻き込み、現状を正しく理解して施策を推進することで、職場単位でも働きがい向上を推進することができ、最終的に会社全体での働きがい向上にもつながります。
職場単位での働きがい向上に向けた活動が軽視される・うまくいかない背景

多くの組織が働きがい向上に取り組んでいるにも関わらず、期待した成果が得られないケースもあります。なぜ思うような結果につながらないのでしょうか。失敗パターンを知ることで、より効果的なアプローチを見つけることができます。以下は、よく見られる職場単位での活動が軽視されてしまう・うまくいかない背景と言え、このようなことが起きていないか確認すると良いでしょう。
経営トップのコミットが不十分
働きがいが重要、とメッセージを発信するものの、あとは人事部任せとなってしまい、真剣さが従業員に伝わらないパターンです。人事部も経験が不十分であることもあり、どのように働きがい向上をすればよいかわからず結果的に働きがい向上の動きも縮小してしまうことに繋がります。
管理職の巻き込み不足
各職場の働きがい向上の鍵を握るのは、現場の管理職です。しかし、管理職への研修や意識改革が不十分なまま、現場に「働きがい向上」を求めてしまうケースがあります。
管理職自身が忙しすぎて部下とのコミュニケーションが取れない、あるいは働きがい向上の重要性を理解していない状況では、職場単位での働きがい向上を目指してもなかなか機能しません。
測定・検証・打ち手の推進が不十分
働きがいの現状を客観的に測定せず、感覚的な判断で施策を進めてしまうパターンです。
定期的なサーベイや面談を通じた定量・定性データの収集なしには、本当に改善されているのか、どの施策が効果的なのかを判断することができません。特に、大きな組織や様々な職種を抱える企業においては、全社を対象としたサーベイのみで、組織単位での結果を分析していない場合、正しく現状を把握し、有効な打ち手に繋げることが難しくなります。
トップダウンのみで従業員の声を聞けていない
経営陣が「働きがい向上」を宣言し、人事部が施策を企画・実行するものの、現場の声を十分に聞かずに進めてしまうパターンです。現場の課題は部署や職種によって大きく異なります。営業部門が求めるものと、技術部門が求めるものは違うかもしれません。画一的な施策では、一部の従業員には響いても、他の従業員には「的外れ」と感じられてしまいます。
職場単位での働きがい向上を成功させるには
前述のうまくいかない背景の裏返しとも言えますが、以下のようなポイントに気を付けて推進することで、職場単位の働きがいも向上させ、最終的に全社的な働きがい向上につながると考えます。
ポイント1: 経営トップは働きがいを経営戦略において重要なテーマと捉え、発信する
経営トップが働きがいを本当の意味で重要だと考えていること、真剣に働きがい向上に努めることを従業員に理解してもらうことが重要です。そうでなければ、働きがい向上のために行う施策がなぜ重要なのかを従業員は理解することができません。全社に向けてメッセージを発信する機会などを活用して、経営トップの考えを繰り返し伝える必要があります。思いが従業員に伝われば、「職場で自分たちにも出来ることはあるか」という視点を持ってもらうことに繋がります。
ポイント2: 部下の働きがい向上は管理職の重要な仕事と伝える
「管理職の仕事は何か?」と問われたとき、多くの人は「目標達成」「業務管理」「人事評価」といった答えを思い浮かべるでしょう。確かにこれらは重要な職務ですが、現代の管理職にはもう一つ、極めて重要な役割があります。それが「部下の働きがい向上」です。組織においてイノベーションにつながるアイディアを生み出したり、生産性向上や離職率低下を実現するには、従業員の働きがいが重要です。部下の仕事の意味付けを支援したり、透明性のある評価を行うなど、管理職は重要な役割を担います。研修などの機会を通じて、会社任せでなく、自身の大切な仕事と理解してもらうことが重要です。
ポイント3: 全社+組織別の働きがいを測定し、検証し、打ち手につなげる
全社を対象にサーベイなどで働きがいを測る際に、組織が大きい場合や様々な職種や職場がある場合、組織別でも測定することを推奨します。それによって、ポイント2でも記載のとおり、管理職が結果を踏まえて自身の重要な仕事の1つとして、部下の働きがい向上に必要な施策は何かを考えることができます。
ポイント4: 従業員とともに打ち手を検討する
経営層や人事、管理職だけで施策を検討するのではなく、従業員を巻き込みながら施策を検討すると良いでしょう。打ち手の策定を急ぐケースも多いですが、サーベイの結果をしっかりとディスカッションし、背景や原因などを良くすりあわせた上で打ち手を決定することを推奨します。ワークショップや、職場ごとに結果のフィードバックミーティングをするといった方法が考えられます。
【ホワイトペーパー】職種別働きがい向上のポイント ~これを読めば、職種ごとに対応すべきポイントが分かる!~
この資料では、働きがいを高めるうえで起こりがちなネガティブな状態を、職種ごとに分析・解説します。あわせて、職種ごとに起こりがちなネガティブ状態に合わせた対応策も方針として示しているため、ぜひ参考にしてみてください。
職場単位での働きがい向上を推進している企業が行っていること

GPTWの調査に参加している企業の中で、職場単位での働きがい向上をうまく進めている企業が何をしているか、以下の通り紹介します。
1.中長期的な戦略の中で従業員の働きがい向上を明言している
経営トップが従業員の働きがい向上にコミットしており、従業員の働きがい向上を重要な経営戦略の一部と据えています。経営トップは従業員に対して直接、間接的にメッセージを発信しており、時には直接現場に回って従業員と対話をするなど、時間もかけて推進しています。
2.全社としての目標や働きがい向上のために何をするか発信し、それが職場活動の推進につながるよう管理職に落とし込んでいる
エンゲージメントサーベイの結果を踏まえ、全社として次は何を目指していくのか、そのためにどのような施策を行うのかをしっかりと従業員に共有しています。目標の置き方は企業により様々ですが、〇年後に〇を目指すなど、具体的な数値とともに発信することも多いです。同時に、サーベイの結果概要についても触れ、回答に協力してくれた従業員への感謝も伝えます。そのような全社方針をしっかりと部門の管理職にも落とし込むことで、職場単位の活動も推進しやすくなります。
3.職場単位でのサーベイ結果を活用し、打ち手を推進している
職場別にサーベイの結果を集計し、働きがい向上に活用しています。どこまでサーベイのスコアを開示するかは企業によってさまざまな考えがありますが、しっかり働きがい向上の結果に繋げている企業では、職場の管理職には結果を開示し、打ち手を検討するよう促しています。企業によっては、職場単位でフィードバックミーティングを行い、職場のメンバー全員で結果について対話し、どのような打ち手をすべきか決定しています。必ず実行できるよう、打ち手は多くなく、また、難易度が難しすぎないものから取り組むのがポイントです。また、職場単位でもサーベイ結果を踏まえて次に目指す目標を置くケースもあります。(例:1年間で●●を〇ポイント向上させる など)職場が自ら考えるよう裁量を与えつつも、会社全体の目標との乖離がないよう、サーベイの主管部門がサポートしています。
4.人事などの組織が主導し、職場単位の働きがい向上施策の推進状況をモニタリングしている
3.で記載するように職場単位で打ち手を決定する場合、人事などサーベイの主管部門が各職場の打ち手をとりまとめ、推進状況を確認しています。打ち手決定後半年後などに、各職場がうまく行えているか、そうでない場合は何が障壁となっているかを確認するなど、サポートを行います。
5.職場別の取り組みの好事例を横展開する
職場ごとで行われている打ち手、施策で効果があったものや良い事例があれば全社で共有し、横展開します。他の組織もそれを参考に取り入れることができる上、会社主導でなく「自分たちで働きがいを高めることができる」と従業員に実感してもらえる機会となります。
6.従業員が主体となった働きがい向上活動を支援し、カルチャーの定着を目指している
従業員リソースグループ(ERG: Employee Resource Group)を設けるなど、従業員が主体となって働きがい向上を行えるような環境を整えています。従業員が主体となって、打ち手を考えられるので、トップダウンの一方通行ではなく従業員が納得感のある施策の実行につながります。これによって、働きがい向上が単なる呼びかけに終わらず、カルチャーとして定着し、より働きがいの高い組織に変革していくことができます。この施策自体が直接職場単位の働きがい向上へ寄与するものではありませんが、従業員自身が自分ごととして働きがい向上に携われることは、職場単位でも働きがいを高めていくことを定着させることに繋がります。
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
職場単位で働きがいを測ることに悪影響はないか?
職場単位でエンゲージメントサーベイなどを活用して働きがいを測り、スコア化することに抵抗感を示されるケースもあります。職場によって環境が異なることもあり、必ずしもその職場やその職場の管理職の責任ではなく、スコアが低く出てしまうことがあるため、数字を突き付けるべきではないのでは、かえって働きがいを阻害するのでは、と考える方もいます。確かにそのような点は考慮するべきではありますが、状況を正しく把握するという意味では職場単位での結果を見ることはおすすめです。悪影響が懸念される場合は、他の組織との比較はせず全社傾向とのみ比較する、開示対象範囲に注意をする、といったことは考慮しても良いでしょう。
職場単位での働きがい向上を成功させ、より良い組織を作る

これまで説明しましたとおり、全社の働きがい向上のためには、職場単位での働きがい向上を成功させることも重要です。
具体的にどのようにこれらの状態を把握し、より良い組織を作ればよいのか、GPTWが用意しているサービスを以下のとおりご紹介します。
職場単位でも結果を集計する働きがいに関するサーベイ実施
従業員の働きがいに関するサーベイを実施し、現状を把握します。GPTW Japanでは、従業員の働きがいを確認できるエンゲージメントサーベイを提供しており、部署や勤務地などの属性を追加できるので、職場単位の働きがいを測定することができます。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
職場単位のサーベイ結果を活用した、ワークショップや職場向けフィードバックミーティングの実施
調査やアンケートの結果を基に、管理職を対象としたワークショップをGPTWがファシリテートすることが可能です。それにより、しっかりと背景や要因を分析し、打ち手を決定できます。また、分析方法のレクチャーを提供したり、職場向けのフィードバックミーティングをどのように行うべきかレクチャーを提供するサービスもあります。管理職が自組織の結果を正しく分析することや、部下とともに働きがい向上に向けた打ち手を決定できるよう支援しています。
研修サービス|働きがいのある会社研究所(Great Place To Work® Institute Japan)
本コラムでは、会社全体の働きがい向上のために、職場単位で働きがいを向上させることの大切さや、職場単位での活動を成功させるポイントについてお伝えしました。サーベイでの測定や、そこから働きがい向上に向けた施策を推進することで、より良い組織作りを目指せます。従業員が働きがいを持ち、安心して能力を発揮し、成長し続けることができる環境を提供することで、企業の成長と成功を実現することができると考えます。
Great Place To Work(R)Institute Japanシニアコンサルタント 岩佐 真裕子

大手企業を中心に各社の調査実施のサポート、分析、経営層への提言や働きがい向上支援を行う。さらに、調査データの分析研究やグローバルでの調査プロジェクト対応などにも幅広く携わっている。