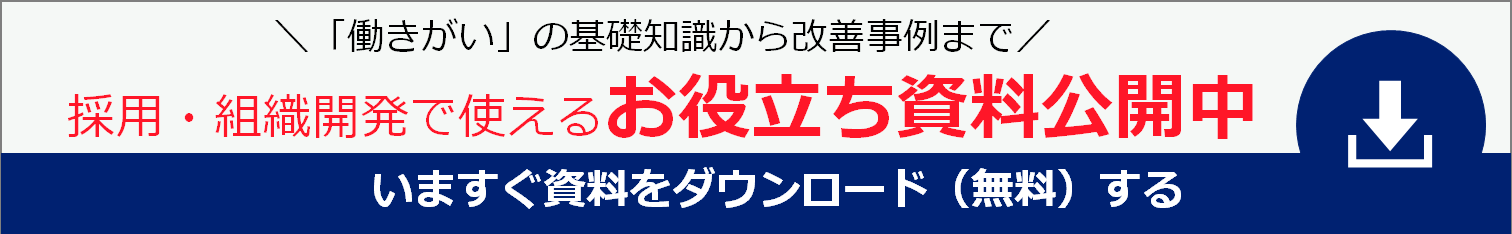データ活用議論を阻む見えない落とし穴とは?~調査データを組織変革につなげるポイント~
更新日 2025.09.302025.09.30コラム

昨今のAI台頭により、データ活用は加速化・複雑化・多様化の一途を辿っています。「データドリブン経営」という言葉が企業の戦略会議で飛び交い、早くPDCAを回していくことが重視され、様々なデータを取得する企業が急増しています。従業員エンゲージメント調査、顧客満足度調査、業績データ、行動ログ──あらゆる情報がデジタル化され、ダッシュボードに美しく可視化される時代となりました。
しかし、その一方で、データに振り回されているように見える企業も少なくありません。ある製造業では、従業員満足度調査で数値が下がるたびに「緊急対策会議」を開催し、場当たり的な福利厚生の追加や研修プログラムの導入を繰り返していました。また、別のIT企業では、エンゲージメントスコアの部署間格差に着目するあまり、低スコア部署のマネージャーを個別に呼び出して「改善計画」の提出を求める事態が発生しました。
これらの企業に共通するのは、データを取ることが目的化し、そこから何を学び、どう行動するかという本質的な議論が置き去りにされていることです。本コラムでは、このような「データ活用の罠」から抜け出し、真に組織変革につながるデータ活用のあり方についてお伝えします。
サーベイとデータが持つ「見えない罠」
データがもたらす錯覚、その本質
サーベイやその他データが、組織を変えていく手段になることは確かです。調査結果は、客観的な事実を示し、感情論ではなく論理的な議論の土台を提供します。しかし、そこには大きな罠が潜んでいます。多くの組織が陥りがちなのは、「サーベイを用いて客観的なデータやエビデンスを示せば、人は動く」という思い込みです。
現実はそう単純ではありません。手段が人を変えるのではなく、あくまで現場の人に解釈されることで意味付けが行われ、動機付けられて初めて人は動きます。その人が動いた集積の結果、人や組織、職場全体が変わっていくのです。
ここで重要なのは、データとは立場や見え方によってさまざまな解釈が可能な情報であるということです。同じ数字を見ても、人によって、状況によって、全く異なる意味を見出すことができます。データが語るのは事実の一側面に過ぎず、それをどう解釈し、どう行動に移すかは、最終的には人間の判断と意志にかかっているのです。

現場の自然な反応を理解する
現場の人々の多くは、数字を見せられても、行為を変えようとはしません。これは怠惰や無関心からではなく、むしろ自然な反応と言えます。人間には現状維持バイアス(現在の状況を維持したがり、変化を避けようとする心理的傾向)が働きます。変化にはリスクが伴い、エネルギーが必要だからです。
「この数字は一時的なものだ」「外部要因の影響だ」「測定方法に問題がある」──こうした解釈は、データを無効化し、変化の必要性を否定する方向に働きます。これは決して悪意があるからではなく、人間の心理には変化を嫌おうとする傾向があるためです。
こういう解釈に留まらせないための働きかけを、組織としては工夫する必要があります。変化が必要なのであれば、そのゴールにはどういう意味があるのか、なぜ変わらなくてはいけないかが現場にとって腹落ちし、「やろう」という意志が芽生えない限り、人は動きません。
【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】
エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。
データから「問い」を生み出す対話の重要性

では、データを活用して組織を変革するには何が必要なのでしょうか。多くの企業が見落としがちなのは、データの「解釈プロセス」です。
Great Place To Work(R)(働きがいのある会社研究所)でも、数多くの調査結果の分析・フィードバックを行っていますが、データから「問い」を立てて、自分たちで解釈に行きつくための議論を経ないと、なかなか腹落ちしづらいものです。実際の企業事例を通じて、その重要性とはどういうことか、イメージしてみましょう。
A社の事例:「問いかけ」が変えた議論の質
ある中小企業A社では、長年良い調査結果を維持しておりましたが、ある年急にスコア低下が見られました。その結果を受けて、調査分析結果を議論する会議が持たれました。その会議では、全体的にはまだ低い状態ではないものの、低下したポイントに集中して質問が飛び交いました。「なぜこうなってしまったのか」「このせいではないか、あのせいではないか」という原因探しの議論が行われ、「仕方ない」と述べる方や自分たちのせいではないというスタンスでの発言をする方も様々いらっしゃる状態でした。
調査結果をきっかけとして対話すること自体は悪いことではありません。しかし、質が問題になることがあります。この時の議論は、既に「低下した設問は、すべて悪いこと。その課題をどう潰すか」という前提で進められていました。
転換点となった一つの意見
しかし、その時にある1人の社員が重要な問いを発しました。「スコアが下がったことに集中して意見が出ているが、自分は悪いことだとは思わない。むしろスコアが低下した設問があることは自然なことであり、それをきっかけに議論が深まることが重要ではないか」
スコア低下は、あくまでサイン(兆し)であり、自分たちにとって変わることを呼び掛けている大切な声のようなものではないか。その解釈に皆がハッとし、議論の空気が一変しました。意見が建設的なものに変化し、あまり発言をしていなかった方も、自由に自分たちの考えや気になっていた点を様々語り始めました。
3つの視点による再解釈
A社様の例は、調査結果が重要なのではなく、人による受け止め(再解釈)が重要であることを示しています。どう自分たちがそれを捉えるかによって、メッセージの雰囲気も大きく変わります。
調査結果を事実レベルのただの理解から、自分たちに対するメッセージとして受け止めていく際、大きく3つのサインに集約されます。
<3つのサイン>
①弱点の克服:組織としての弱点克服につなげていくべきサイン
②前提の点検:現状当たり前となっている前提を点検し、見つめ直すサイン
③挑戦の始動:現時点では課題視されていないが、未来を見据えたときに、今新たに始めていくべきサイン
A社様の例では、スコア低下から②前提を点検することが必要だと感じ、改善の施策を増やすのではなく、今ある施策が多すぎて負荷がかかっているのではないかと考え、最終的に施策を精査して減らす結論に帰着しました。調査結果からの解釈には正解がありませんので、彼らが議論の中で決めたということに過ぎません。しかし、このプロセスを経てこの結論に至ったことには大きな意味があります。調査を通じて、改めて自分たちのスタンスが明確になり、調査結果を踏まえた、社内への建設的なメッセージ発信につながってゆきました。
A社様の例は、調査結果を深める議論の例として、非常に良い例だと言えます。数値の変化を「悪い・良い」で判断する前に、「何のサインか?」を考え、「問い」を立てることで、受け取るメッセージ、発信されるメッセージは劇的に変わります。
データを基に議論する
建設的な議論を阻む「思いつき意見」
前述したような建設的な深い議論をしていこうと思ったとき、それを阻む要素にも意識を向ける必要があります。
会社である程度の年数働いている社員であれば、自分が働いている現場について、誰でも何らかの「一家言」を持っています。そういった強い信念を持つ人たちが議論すると、飛びついたように自分軸の信念に基づいて思い付きのような意見を発してしまうことが少なくありません。とりわけ10人程度の会議体でそうした意見が出るとき、その意見の出し方は連鎖して、建設的な議論を阻害してしまいます。ひとたびこうした議論の雰囲気が醸成されると、そこから建設的な議論に戻すのは非常に難しいと言えます。
データは「思いつき意見」を排除する重要なファクター
上記事態を避ける意味でも、建設的な議論を進める際には、データを基とするというルールをしっかりと据える必要があります。データはこの「思いつき意見」を排除する上では、非常に効果的です。個人の恣意性を超え、メンバー間に新しい信頼をつくりあげる上でデータは重要な役割を果たします。
そのため、設計時点から最終的な議論を見据えた、調査設計が出来ていることが理想です。
どんな仮説を検証したいのか。そのために、どんな視点でデータを収集するか、そしてそれをどう解釈するかまで含めて、調査設計のデザインにかかっています。ぜひ調査準備時点から、「どんな議論を行いたいか」を意識しておくと良いでしょう。

個人攻撃という罠を避ける

職場レベルでの分析時の注意点
また、調査結果を職場単位まで落とし込んでフィードバックする際に気を付けなければならないのが、個人に原因を落とし込んで考えてしまうことです。
「あの人がいるから数字が悪い」「この人の影響で雰囲気が悪くなっているのではないか」こうした個人攻撃的な議論は、当人がいない場で陰口的に起きます。建設的な改善につながらないばかりか、組織の信頼関係を破壊してしかねませんので、避ける必要があります。
構造的な視点を保つ
調査データは、個人の原因とは一旦切り離して、データに向き合うことが重要です。組織やシステム、プロセスの問題として捉え、構造的な改善を議論する。その議論があった上で、必要に応じて個人的な原因に紐づく会話を行うべきです。
その意味でも、本筋に戻すファシリテーターの存在は非常に重要です。これは社内の人間が行う際には、難しいことが少なくありません。あえて外部コンサルの人間から報告をしてもらったり、個人要因に紐づく議論が始まったら、構造的な要因を考えてみるように軌道修正しましょう。重要なのは、「誰が悪いか」ではなく「何を変えるべきか」に焦点を当てることです。
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
全社共有のポイント
深い議論を行うことが出来たら、あとは組織変革につなげていくための全社共有のステップとなります。この効果的な伝え方については、他の記事(調査結果を「出して終わり」にしないために~エンゲージメント調査結果を組織の力に変える『納得感醸成』のポイント~)でもご紹介をしておりますので、ぜひそちらも参照ください。ただ、ポイントとしては議論を経てまとまった3つの「なぜ」がしっかり伝わっていることが大切です。
①なぜ、その組織を変えないといけないのか?
②なぜ、今やらないといけないのか?
③なぜ、自分たちがやらないといけないのか?
これらの問いに対する答えが腹落ちしていない限り、どんなに精緻なデータを示しても、人は本気で動こうとはしません。あくまでデータは手段であり、目的ではありません。目的は組織をより良い方向に変えることであり、そこがブレている限り、現場の人間を動かすことは出来ません。
おわりに
調査結果はあくまでデータであり、その背景にある受け取るべきサインは目には見えづらいものです。しかし、人の想い、組織の文化、チームの結束力、リーダーシップの質。これらは定量化が困難でありながら、組織の成果を大きく左右する要素です。
データ分析の技術が進歩し、AIが高度化しても、この本質は変わりません。むしろ、技術が進歩すればするほど、人間の解釈力、洞察力、対話力の価値が際立ってくると言えるでしょう。
データを見て表面的な分析をし、既存の枠組みで解釈するだけでは、真の組織変革は起こりません。ぜひ本気で、時間をかけて調査と向き合っていただきたいと思います。
データは組織を変える強力なツールですが、それを活かすも殺すも人次第です。データに振り回されるのではなく、データは人によってはじめて解釈され、本質に行き着くことができます。ぜひデータという道具を使いこなし、真の組織変革を実現していきましょう。
なお、Great Place To Work(R)では、「働きがいのある会社」調査を通じて、こうしたデータ活用の罠に陥ることなく、どのような改善の一歩目を踏み出していくかの支援を行っています。
特に、経営層向けの「カルチャーコーチング」というディスカッションでは、まさに本コラムで述べたような罠に陥らないための場づくりやファシリテートを専門的に行っています。データを単なる数値として捉えるのではなく、組織の声として解釈し、建設的な対話を生み出すためのプロセスを、経験豊富な専門家がサポートいたします。
調査結果が活用できていない方やアクション策定まで支援してほしい方へ
働きがいのある職場づくりの支援を目的として、様々な研修サービスを提供しております。調査結果を活用してのワークショップ、講演など、目的に応じてご提案が可能です。
また、実際にスコア向上を実現した企業の豊富な事例もご紹介しています。他社がどのようにデータと向き合い、どのような対話を通じて組織変革を実現したかを学べる「働きがい向上事例集」をご提供しておりますので、ぜひ以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
>>働きがい向上事例集はこちら<<
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。データを活用した真の組織変革への第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。ご相談をお待ちしております。
Great Place To Work(R)Institute Japanコンサルタント 三輪 慶(みわ けい)