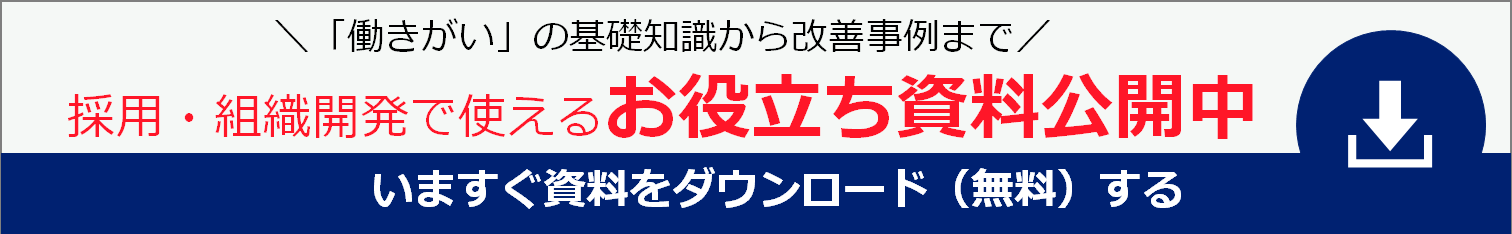人材定着のための6つの施策とポイント
更新日 2025.09.192025.09.19コラム

人材の定着は、企業の成長や競争力を支える重要な基盤です。いくら優秀な人材を採用しても、短期間で離職してしまえば、採用・教育に投じたコストを回収できず、組織に知識やノウハウも蓄積されません。逆に従業員が長く働き続けられる環境を整えられれば、生産性やサービス品質が高まり、結果として顧客満足度や企業ブランドの向上へと直結します。
本記事では、まず「人材定着」の定義や定着率の算出方法を明らかにし、その重要性と企業にもたらすメリットを整理します。人材定着を実現するための6つの主要施策を具体的に紹介し、企業が直面しがちな課題とその解決策、中小企業ならではの工夫ポイントも詳しく取り上げますので、ぜひ参考にしてください。
人材定着とは?

人材定着とは、企業が採用した従業員が長期的に職場に留まり、継続的に働き続けることです。単に在籍年数が長いだけではなく、従業員自身が意欲を持ち、組織の一員として成長・貢献を続けられる状態を意味します。以下、人材定着の定義や、人材定着率の算出方法を解説します。
人材定着の定義
人材定着とは、従業員が短期間で離職せず、長期的に企業で働き続ける状態です。一般的に「リテンション」とも呼ばれ、単に人材を確保するだけではなく、優秀な人材の流出を防ぐための取り組みも含まれます。目的は、企業にとって最も貴重な資産である「人的資本」を維持・活用し、組織全体の成長につなげることです。
理想的な人材定着とは、以下のような状態を指します。
- 従業員が企業のビジョンや価値観に共感している
- 職場環境や業務内容に満足している
- 自身のキャリア形成の機会を得られている
上記のように、人材定着は単なる「離職防止策」ではありません。個々の従業員が、企業の一員として充実感を持ちながら、長期的に活躍できる仕組みを整えるのが人材定着の本質です。
<関連記事>
リテンションとは?意味や人事施策の効果・マネジメント方法など詳しく解説
人材定着率の算出方法
人材定着率とは、一定期間にわたり企業に在籍し続ける従業員の割合です。採用や育成にかけたコストの回収度合い、職場環境の健全性を測る基準として活用されます。人材定着率の基本的な計算式は以下の通りです。
(一定期間後の在籍者数÷一定期間開始時の従業員数)×100
例えば、100名の従業員のうち95名が1年後も在籍していれば、その期間の人材定着率は95%となります。定着率は、「1年」や「3年」などの年単位で計測されるのが一般的です。離職率と対になる指標でもあり、「100%−離職率」の式でも算出できます。なお、正確に測定するためには、中途入社者を除外するなどの作業が必要です。
定着率が高い企業は、「人材が長く働ける環境を整えている優良企業」と見なされやすく、企業ブランド向上にもつながります。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
人材定着が企業にとって重要な理由・メリット

人材定着は、生産性やサービスの質が向上するだけでなく、採用コストの削減や企業ブランドの強化といった多くのメリットをもたらします。なぜ人材定着が企業にとって重要なのか、5つのメリットを整理しながら解説します。
<関連記事>
採用・教育コストの削減につながる
人材定着が企業にもたらすメリットの1つが、採用や教育にかかるコストの削減です。従業員の離職が多い企業では、欠員補充のために常に採用活動を行わなければなりません。そのためには、求人広告の掲載やエージェントへの依頼、選考や面接の実施など多大なコストがかかります。
一方で人材定着率の高い企業は、再採用や再教育の頻度が少なく済むため、長期的に見ると大幅なコスト削減が可能です。新たな人材を探す必要が減れば、採用担当者はより戦略的な人事施策に集中できます。教育担当者も、基礎研修ではなく、高度なスキルアップやキャリア支援にリソースを割けます。
社内ノウハウの蓄積と継承が進み、個々のスキルをゼロから再教育する必要性が低下するのも重要なポイントです。
生産性の向上につながる
生産性の向上も、人材が長く働き続けるメリットです。離職が多い職場では、人材の入れ替えに伴い業務が一時的に停滞したり、引き継ぎ不足によるミスが発生したりします。特に新人の戦力化には時間がかかり、その間は既存メンバーの負担も増加します。
人材定着率が高い環境では、こうした非効率を最小限に抑えられます。人材の入れ替えが少ないことで、業務の処理スピードが安定し、組織全体の業務効率が向上します。経験豊富なメンバーが継続して在籍することで、業務フローの最適化や効率的な作業分担も進み、生産性の向上につながります。
高品質で安定したサービスを提供できる
人材が長期的に定着すると、まず職場内の人間関係やチーム体制が安定します。長く働いていると次第に信頼関係が築かれ、互いの強みや役割分担が明確になるため、業務上の協力体制がスムーズに機能します。日々のコミュニケーションが円滑になり、結果として業務の効率と安定性が高まるでしょう。
従業員が同じ職場で経験を重ねれば、専門性やスキルに磨きがかかります。そして定着した人材が中心となって、継続的な改善活動に取り組める点も重要です。「人材定着→信頼関係の構築→コミュニケーション改善→熟練度向上→継続的改善」という流れになり、高品質で安定したサービス提供が可能になります。
顧客満足度の維持・向上につながる
人材定着は、社内だけでなく顧客との関係性にも直接的なメリットをもたらします。まず、担当者が長期的に同じ顧客を担当し、信頼関係が継続的に築かれる点が重要です。人の入れ替わりが激しいと、顧客は毎回、対応する相手に慣れていかなければなりません。しかし担当者が変わらなければ、「この人に任せれば大丈夫」という安心感を得られます。
さらに定着した従業員は、長期的なやり取りを通じて、顧客の特性やニーズを深く理解できます。顧客の過去の要望や取引履歴、好まれる対応スタイルなどを把握しているため、より的確な対応が可能です。新任担当者への引き継ぎ不十分によるトラブルや、対応のばらつきも減り、企業全体としての信頼性も高まります。
採用力と企業ブランドの向上につながる
人材定着は、社内の安定や顧客満足度の向上だけでなく、外部に対しても大きな効果をもたらします。特に、採用力と企業ブランドの強化につながる点は重要です。
離職率の高い企業は、「職場環境に問題があるのではないか」と疑念を持たれがちです。しかし離職率が低ければ、「働きやすさ」を示す客観的な指標として、求職者にアピールできます。「従業員が安心して働き続けられる環境がある」と見なされ、優秀な人材を惹きつけやすくなります。応募数の増加も期待できます。
採用市場では、人材定着率の高さ自体が「働きやすい職場」というイメージとして他社との差別化要因となり、結果的に採用活動を有利に進められます。
【ホワイトペーパー】若手が活躍する職場とは ~「働きがいのある会社」ランキング上位企業に学ぶ~
この資料では、若手ランキング企業の特徴を通じて、組織で若手がイキイキと活躍するためのポイントを解説し、「働きがいのある会社」ランキング上位に選出された企業の実際の取り組み事例を紹介します。
人材定着を高めるため6つの主要施策

人材が長く安心して働ける環境を整えれば、単に採用・教育コストを削減するだけでなく、組織力やサービス品質の向上にもつながります。
近年は人材不足の深刻化や売り手市場の定着、多様な働き方の普及により、優秀な人材ほどより良い環境を求めて積極的に転職する傾向が強まっています。そのため企業が人材を惹きつけ、かつ長期的に定着させるためには、計画的な改善策を継続的に実施するのが不可欠です。
以下、採用時の工夫から日常のマネジメント、評価・処遇制度の改善、柔軟な働き方の導入、さらにはデータを活用した分析まで、定着率を高めるために有効な6つの主要施策を取り上げます。
1.採用段階での情報開示とミスマッチ防止に努める
人材定着を高めるうえで重要になるのは、入社後のギャップを防ぐための工夫です。いくら研修や評価制度を整えても、そもそも「思っていた仕事と違った」という不一致が原因で早期離職につながってしまっては意味がありません。
そのため、募集段階から仕事内容・評価基準・職場環境などを正確に提示し、求職者にリアルな職場像を理解してもらう必要があります。具体的には、インタビュー記事や座談会、職場見学や業務体験の機会を設けるのがおすすめです。求職者が入社前に実際の雰囲気や働き方を体感できると、「入社してから思っていた環境と違った」という事態を防ぎ、安心してキャリアをスタートできます。
企業側も、求職者の価値観やキャリア志向を把握し、自社との適合度を見極めるのが重要です。適性検査やキャリア面談を活用すれば、求職者の将来像と、自社が与えられるチャンスが一致しているかを確認できます。採用段階での透明性と相互理解を高める取り組みは、人材定着の第一歩となるでしょう。
2.定期的なコミュニケーションの機会を実施する
人材が定着するためには、従業員が安心して意見を伝えられ、悩みや不満を早期に解消できる環境が欠かせません。そのために重要なのが、定期的なコミュニケーションの機会です。
まず、個人の課題や悩みに対応する場合は、1on1面談を定期的に実施し、上司との間で課題や不安を共有しやすい状態にします。問題が小さなうちに把握・解決できれば、モチベーションの低下や、離職につながるリスクを大幅に軽減できます。
一方、チーム全体の結束力を高めたい場合は、チームミーティングや部署を越えた交流の場を設けるのが効果的です。異なる立場の従業員が接点を持てば、相互理解や信頼関係が深まり、組織全体の一体感が作られます。特に中堅や若手にとっては、自分の部署以外に相談できる相手ができるだけでも、安心感につながります。
さらにリモートワークが普及した現在では、孤立感の解消が課題となる場合があります。この場合は、オンラインランチ会などの非業務的な交流イベントを意図的に設計するとよいでしょう。チームとのつながりを感じやすくなり、孤立感も解消されやすくなります。
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
3.成長機会を提供しキャリア支援を行う
人材が長く定着するためには、「この会社で成長できる」「将来のキャリアを描ける」という実感が欠かせません。いくら働きやすくてもやりがいがない職場では、優秀な人材ほど物足りなさを感じ、他社への転職を検討する可能性があります。そのため、企業は従業員に対して成長機会を与えつつ、キャリア形成のサポートを行うのが重要です。
まずは、業務に直結するスキル研修や資格取得の支援をします。費用補助や学習時間の確保といった仕組みを整えれば、自己研鑽を継続しやすくなり、モチベーションの向上につながります。
さらにキャリアパスを明示し、どのように成長していけるのかを明確化するのも重要です。「数年後には管理職を目指せる」「専門職としてスキルを高められる」といった道筋が見えれば、従業員は安心して将来を描けます。
加えて、異動や新規プロジェクトへの参加など、挑戦の場を意図的に用意するのも効果的です。普段の業務を超えた経験を積んでもらえば、従業員自らの選択肢を広げるだけでなく、マンネリの解消にもつながります。
4.公正で透明性の高い評価制度を運用する
従業員が安心して長く働き続けるためには、努力や成果が正しく評価される仕組みが欠かせません。評価が不透明であったり、上司の主観に左右されたりすると、不公平感や不満が募り離職の要因となります。
まず、自社が求める人物像や行動指針をもとに評価基準を明文化し、全従業員に共有する作業が不可欠です。評価のルールが明確になれば、従業員は「何を目指せば評価されるのか」を理解しやすくなり、日々の行動にも一貫性が生まれます。
その基準に基づいて、成果だけでなくプロセスや姿勢を含めて正しく評価し、それを待遇に反映させるのが重要です。単に「結果を出したかどうか」だけでなく、目標達成に至る過程やチームへの貢献度も評価すれば、個人だけでなく組織全体の成長を後押しする文化が作られます。
評価結果は、単に点数やランクを伝えるだけでなく、面談を通じて改善点と強みを具体的に伝えるのが重要です。上司からの建設的なアドバイスによって、従業員は自己成長の方向性を理解しやすくなり、「次はこうすればもっと評価される」という納得感を得られます。
5.柔軟な働き方が可能な制度を整える
現代の働き方で、人材定着を左右する大きな要素が、柔軟な勤務制度の有無です。従業員はライフステージや個々の事情に応じて、多様な働き方を求めています。企業としては、自社の状況や業務特性を踏まえながら、可能な範囲で柔軟な働き方を支援する制度を検討することが重要です。
具体的には、リモートワークや時短勤務、時差出勤などを制度化して、ワークライフバランスを整えやすくします。特に育児や介護を担う従業員にとっては、柔軟な制度があるかどうかが「働き続けられるか」を決定する要因となります。
一方で、制度を形だけ導入しても、実際に利用されなければ意味がありません。そのためには、利用しやすい職場文化を作り、上司や管理職が率先してサポートする必要があります。「制度を使うと評価が下がるのでは」という不安を払拭するために、成功事例を共有したり、利用実績を積極的に公表したりするとよいでしょう。
<関連記事>
ワーク・ライフ・バランスとは?働き方の意味や定義・メリットや古いと言われる理由をわかりやすく解説
6.データ分析による定着施策の継続改善を実施する
人材定着は一度仕組みを整えれば終わりではなく、継続的に検証・改善するのが重要です。そのためには、感覚や一部の事例に頼るのではなく、データに基づいた分析と施策改善を行う必要があります。
まず、退職理由や在籍期間の傾向をデータとして収集・分析して、離職の原因を客観的に把握します。例えば「特定の部署だけ離職率が高い」「入社3年以内に退職が集中している」といった傾向が分かれば、重点を絞ったうえでの対策が可能です。
次に、エンゲージメント調査や定期的な面談記録を活用し、既存の施策がどの程度効果を発揮しているかを検証します。従業員の満足度やエンゲージメントの変化を数値化すれば、「どの施策が有効か」「どの施策を見直すべきか」を判断しやすくなります。
さらに、得られたデータをもとに改善策を策定し、PDCAサイクルを回し続けましょう。単発的な取り組みではなく、継続的な改善活動を組織文化として定着させ、長期的に定着率を高める仕組みを作ります。
「エンゲージメントサーベイ」で離職原因を見える化し定着率アップへ

人材定着は、採用コストの削減や生産性の向上にとどまらず、顧客満足度や企業ブランドの強化などさまざまな効果を生み出します。その実現には、採用段階からのミスマッチ防止や日常的なコミュニケーション、データに基づく改善など総合的な取り組みが欠かせません。
特に重要なのは、「離職の要因を正しく把握して効果的な改善策へとつなげること」です。これができなければ、せっかくの施策も形だけのものになり、定着率向上という成果に直結しません。人材定着を最短で実現するには、エンゲージメントサーベイのような仕組みを活用し、従業員の声をもとにした改善サイクルを回すのが重要です。
ただし、エンゲージメントサーベイの効果を最大化するためには、適切なツール選択が欠かせません。人材定着に真に効果的な改善を実現するには、「働きやすさ」と「やりがい」の両面を適切に分析できるサーベイを選択することが重要です。なぜなら、働きやすい環境が整っていても、仕事にやりがいを感じられなければ、優秀な人材ほど成長機会を求めて他社への転職を検討するからです。
Great Place To Work®が提供するエンゲージメントサーベイは、世界約170ヶ国・21,000社以上で導入されており、「働きやすさ」と「やりがい」の両面から職場環境を分析することができます。第三者機関が従業員のリアルな声を収集するため、離職の原因を的確に把握することが可能です。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!