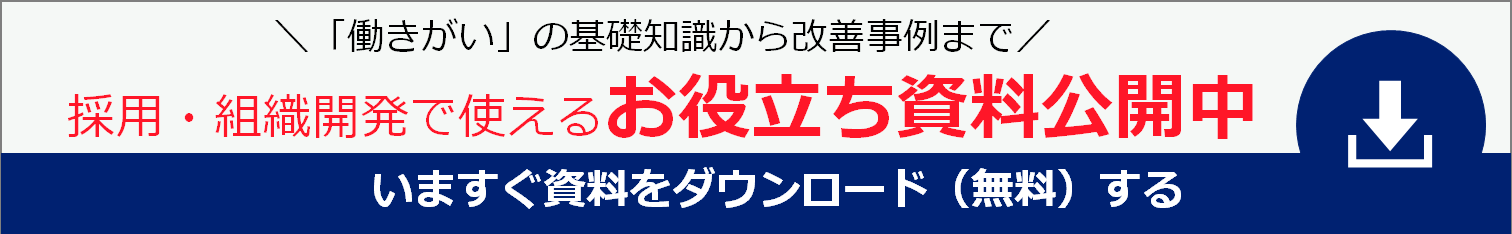採用難時代に生き残る!"人材確保"のための6つの戦略
更新日 2025.07.152025.07.14コラム

労働人口の減少や働き方の多様化が進む中、中小企業を中心とした多くの企業が人材確保に苦戦しています。しかし、企業が継続的に発展し競争力を維持するためには、人材確保は避けられない課題であり、時代に合った対策と明確な戦略の立案が必要不可欠です。
本記事では、人材確保の定義や重要性に触れつつ、企業が直面する主な課題と、それを乗り越えるための具体的な6つの戦略について詳しく解説します。
採用した人材が定着する組織をつくるためのポイントや、人材確保の成功事例もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
人材確保とは

人材確保とは、採用活動だけにとどまらず、必要な人材を継続的に確保し、企業の成長を支えるための取り組み全般を指します。これは企業の存続や競争力を維持する上で欠かせない要素です。
人手不足が深刻化する現在、そもそも必要な人材を集めること自体が大きな課題になっています。さらに、採用した人材に長く定着してもらい、能力を十分に発揮してもらうための仕組みや職場環境づくりも重要です。
このように、人材確保は多くの企業にとって最優先で取り組むべき課題のひとつです。特に若手や専門人材の採用競争が激しくなる中、魅力的な労働条件の整備、キャリア形成支援、柔軟な働き方の導入などを進める企業が増えています。人材確保を効果的に進めるためには、経営戦略の一環として位置づけ、経営層が主体的に取り組む姿勢が求められます。
人材確保の定義
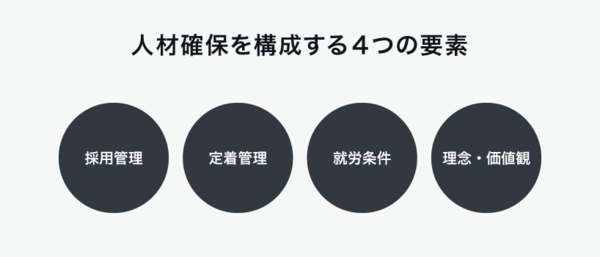
人材確保とは、企業が事業活動を安定的に維持・発展させるために、必要な人材を適切なタイミングで採用し、長期的に雇用・育成・定着させるための一連の活動を意味します。
人材確保は単なる求人募集や採用面接のテクニックにとどまらず、入社後の研修制度・キャリア支援・評価制度の整備・労働環境の改善・柔軟な働き方の導入・福利厚生の充実など、人材が長く安心して働き続けられる環境づくりまでを含む広範な概念です。
そのため、人材確保は採用と定着の両面から取り組むべき戦略的プロセスとして捉える必要があります。厚生労働省の人材確保対策事例集(※)では、「採用管理」「定着管理」「就労条件」「理念・価値観」の4つの視点が明示されています。これらを総合的に整備することが、持続的かつ安定的な人材確保を実現するポイントです。
人材確保の重要性
人材確保は、企業の持続的な成長と競争力を維持するために極めて重要な要素です。
優秀な人材は単なる労働力としてだけでなく、組織の中で新たな価値を創出し、イノベーションや業務効率の改善、生産性の向上などにも大きく貢献します。
一方で、人材不足が深刻化すると業務の停滞やコストの増加、サービス品質の低下といった経営上のリスクが高まります。また、従業員の負担が増すことでモチベーションや定着率が低下し、さらなる悪循環を生むこともあります。
特に中小企業では、一人の人材が組織や事業に与える影響が大きいため、人材確保は単なる採用活動ではなく、経営戦略そのものとして位置付ける必要があります。
そのため、採用後の定着や継続的な成長支援も重要な経営課題の一つであり、組織力や競争力を高めるために欠かせない要素といえます。
人材確保が難しい理由

多くの企業が人材確保に課題を抱えている背景には、いくつかの複雑な要因があります。
少子高齢化や働き方の変化、終身雇用制度の見直しなど、時代の流れとともに状況は大きく変化しており、これに伴い採用や定着の難しさも増しています。
人材確保の困難さを乗り越えるには、このような理由を正しく理解することに加え、問題の本質を見極める視点と、効果的な戦略や施策を講じることが求められます。
これらを踏まえて、人材確保が難しい主な理由を解説します。
働き方に対する考え方が多様化している
現代の求職者は、従来の画一的な働き方ではなく、自分のライフスタイルや価値観に合わせた多様な働き方を求めている傾向があるようです。
たとえば、リモートワーク、フレックスタイム制、副業の許容など、柔軟な勤務体系が求められます。企業がこれに対応できていない場合、優秀な人材を獲得するハードルは高くなるでしょう。
特に若年層では、給与や福利厚生だけでなく、企業文化や働きがい、自己成長の機会を重視するケースが増えています。こうした変化に対応するには、企業側も多様な働き方に適応する戦略を打ち出さなければなりません。
例として「在宅勤務のルール整備」「チームコミュニケーションを円滑にするツールの導入」「目標管理や評価制度の見直し」「多様なキャリアパスの提示」といった、実際に運用して成果を出せる仕組みを組み合わせる工夫が挙げられます。これらを実現することが、人材確保につながる有効な方法と言えるでしょう。
また、多様な人材を受け入れることで、組織にイノベーションが生まれやすくなります。他社での経験を持つ人材が新しい業務プロセスを提案したり、若手が業界の常識にとらわれない発想を持ち込むことで、新たなサービスや商品の開発、業務効率化を進められるでしょう。こうした変化は、労働力の強化や目標達成、計画の実現など、組織運営のさまざまな場面でプラスに働きます。
終身雇用制度が見直されつつある
これまで一般的であった終身雇用制度が見直されつつあることも人材確保を難しくしている要因の一つです。
生涯同じ企業で働き続けるという従来の慣行が薄れ、転職に対する抵抗感がなくなってきたことで、人材の流動性はどんどん高まっています。特に若い世代ほど、働きがい・成長機会・自己実現といった要素を重視し、自分のキャリアに対して主体的な意思決定を行う傾向が強くなっています。
そのため、企業はこれまで以上に一度採用した人材に長く定着してもらうための対策を講じる必要があります。
また、意欲のある優秀な人材が、より良い条件や働く環境を求めて他の企業へ転職するケースも増えているため、企業側は人材の定着率向上に向けて、柔軟な制度設計や働きやすい環境整備を進めていく必要があるでしょう。
労働力不足が常態化している
歯止めのかからない少子高齢化とそれに伴う生産年齢人口の減少は、日本の多くの産業で深刻な労働力不足を常態化させており、これも人材確保を一層困難にしている要因です。
特に介護・運送業・建設業・IT業界など、体力や専門性が求められる業界では人手不足が加速しており、必要な労働力を確保するための企業間の競争も激しさを増しています。加えて、都市部への人口集中や、優秀な人材が海外へ流出するケースも見られるなど、地方や中小企業では人材確保がより一層困難な状況です。
こうした構造的な課題に対し、企業は従来の採用手法に頼るだけでは不十分であり、新たな対策や採用チャネルの開拓、働き方の見直しが求められています。
このような背景から、戦略的かつ柔軟な人材確保策を講じることが、企業の存続と持続的成長を左右する重要な経営課題の一つとなっています。
求職者優位の売り手市場が継続している
人材確保が難しくなっている背景には、売り手市場が続いていることが大きな要因として挙げられます。求職者が多くの選択肢を持つ状況では、企業側も「選ばれる立場」であることを意識し、採用活動を進める必要があります。
売り手市場では、求職者は複数の企業から内定を得やすく、より良い条件や環境を求めて企業を比較検討します。そのため、採用側が描く理想の人材像と現場が本当に必要とする人物像にズレがあると、せっかく獲得した人材も他社に流れてしまうリスクが高まります。また、入社後に「思っていた仕事と違う」「職場に馴染めない」といったギャップが生まれると、転職しやすい環境であるため早期離職につながりやすくなります。
人材確保を成功させるには、売り手市場であることを前提とした戦略が必要です。経営層や人事部門が現場の声をしっかりと取り入れ、現場ニーズを反映した求人要件の設計や、長期的な育成・定着を見据えた施策を進めていく姿勢が求められます。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
人材確保に効く6つの戦略

人材確保がますます難しくなっていく現代において、企業が競争力を維持しながら成長を続けるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。
ここからは、人材確保に効果的な6つの戦略をご紹介します。
採用ターゲットの見直し
人材確保を進めるには、まず「どんな人を採用したいのか」というターゲット設定を改めて見直すことが欠かせません。現場で必要とされるスキルや経験、人物像を具体的に言語化し、採用担当者や経営層で認識を共有することから始めます。
求める人材像があいまいなままだと、採用活動が場当たり的になり、ミスマッチや早期離職のリスクが高まります。そのため、社内の現場メンバーとのヒアリングを通じて、実際にどんな人物が活躍しているのか、どのような資質が必要なのかを洗い出すことが重要です。
採用ターゲットが明確になれば、それに合わせた効果的な採用計画を立てることができます。例えば、若手層をターゲットにするならSNSやダイレクトリクルーティングを活用する、専門性の高い人材を狙うなら業界特化型媒体を選ぶなど、チャネルやアプローチ方法をターゲットに合わせて最適化できるようになります。
また、明確なターゲット像があることで、求人広告もより刺さりやすい内容に作り込むことが可能です。求職者が知りたい情報や魅力を具体的に伝えることで、応募意欲を高めることが期待できます。ターゲット像を明確にした上で、その人たちに「響く」メッセージを設計することが、採用成功への近道です。
<関連記事>
【事例あり】ダイレクトリクルーティングとは?採用力を強化する手法と成功のポイントを解説
SNS採用とは?活用ポイント、メリット・デメリット、成功事例を解説
新しい採用アプローチ方法の導入
多様化する働き方や価値観に対応するためには、従来の手法にとらわれず新たな採用アプローチを積極的に取り入れることが重要です。
例えば、企業が求職者に直接アプローチするスカウト採用やダイレクトリクルーティングは、転職潜在層にもリーチできる効果的な手法として注目されています。送るメッセージをパーソナライズし、自社で働く価値を具体的に伝えることで反応率を高められます。
また、リファラル採用も有効です。既存の従業員が候補者を選ぶことで、企業文化に馴染みやすく、定着率の高い人材を採用できる可能性が高まります。さらに、柔軟な働き方を支援する施策として、求人にリモートワークやテレワーク対応を明記する、エンジニアなど専門職ではスキル重視の採用を行うといった手法も効果的です。
加えて、アルムナイ採用(退職者の再雇用)やインターンシップ活用も、即戦力かつ定着率の高い人材を確保する有効な方法として期待されています。
アルムナイ採用の詳細については、以下の記事もご覧ください。
<関連記事>:アルムナイ採用とは?意味やメリット、実施のポイントを解説
労働条件・職場環境の改善
労働条件・職場環境の改善は、人材確保において極めて重要な戦略です。優秀な人材は複数の選択肢を持っており、より良い条件や環境を求めて企業を選ぶ傾向にあるためです。効果的な改善に取り組むには、自社の現状を把握し、優先順位をつけて取り組むことが重要です。
多くの場合、給与や賃金水準の競争力確保は重要な要素の一つですが、それだけでは不十分です。自社の規模や業界特性、予算、そして従業員が実際に求めているものを踏まえて、最も効果的な施策を選択しましょう。例えば、賃金アップが困難な場合はテレワークやリモートワークなどの働き方改革から、資金に余裕がある場合は福利厚生の充実から始めるといった具合です。ワークライフバランスを重視する従業員が増える中、柔軟な働き方を提供する環境づくりは特に効果的です。
現在の従業員のニーズに応えることは、単なる満足度向上にとどまりません。働きやすい職場環境で満足している従業員は、自然と職場の魅力を周囲に伝える「アンバサダー」となり、口コミやリファラル採用を通じて優秀な人材を呼び込む効果があります。また、離職率の低下により採用コストの削減にもつながり、結果として持続可能な人材確保が実現できるのです。
これらの取り組みはすべて、従業員が働きがいを感じられる環境づくりにつながります。給与や福利厚生の改善、テレワークなどの働き方の向上に加え、成長機会の提供、理念や社会的意義への共感、職場のコミュニケーション改善なども重要な要素です。こうした働きがいを高める取り組みは、離職防止や人材確保に直結する重要なポイントです。
入社後サポート体制の設備
採用した人材に長く定着してもらうためには、入社後のサポート体制を整備しておく必要があります。
例えば、新入社員向けの研修制度やメンター制度の導入は、早期に組織に馴染み、必要なスキルを習得するために有効な施策です。入社後のギャップを減らすために、入社前から配属部署や業務内容を具体的に説明したり、内定者フォローを丁寧に行ったりすることも効果的です。さらに、定期的に面談を実施することで新入社員の状況を把握し、不安や悩みに寄り添えるような相談しやすい環境を提供することが離職防止に繋がります。
また、キャリアパスを明確に提示し、将来的な成長の機会を見せることでモチベーションの維持を図れます。成功事例として、新人研修後に定期的な面談を実施することで定着率が向上した企業や、未経験から管理職へ昇進した従業員のキャリアを紹介することで応募率が高まった企業もあります。
こうした育成・定着に向けた施策が人材の定着と早期戦力化に直結するのです。
企業文化や働く魅力の発信
自社の企業文化や働く魅力を積極的に発信することは、それらに共感する人材を惹きつけるうえで非常に有効です。企業の経営理念や価値観に共感する人材は、入社後のミスマッチが少なく、長期的に貢献してくれる可能性が高まります。
効果的な発信を行うには、まず採用ターゲットを明確にし、そのターゲットに刺さる内容を逆算して考えることが重要です。例えば、成長志向の強い人材を求める場合は先輩社員の成長ストーリーを、ワークライフバランスを重視する人材を求める場合は柔軟な働き方の事例を中心に発信します。
採用サイト・ブログ・SNSなどを活用して、職場環境や従業員の声、働く先輩たちの様子をリアルに届けることで、候補者自身がその環境で働くイメージを具体的に描けるようになります。動画やインタビューなどを活用したコンテンツは、よりリアルな職場の雰囲気が伝わるため、訴求力が強く効果的です。
継続的な情報発信により候補者とのコミュニケーションを図ることで、自社に興味を持つ人材プールを形成できれば、採用力の向上が期待できるでしょう。
採用データを活用した戦略設計
勘や経験に頼るだけでなく、採用データを収集・分析し、戦略設計に活かすことがより効果的な人材確保に繋がります。
応募者の属性や選考プロセスごとの通過率、内定辞退率、入社後の定着率などを分析することで、採用活動における課題を定量的に把握できます。こうした分析結果に基づいて改善点を明確にし、ターゲット設定や採用チャネル、選考方法などを見直すことで、採用効率の向上やミスマッチの防止が可能です。
また、採用管理システム(ATS)などを活用することで、データの収集・管理・分析を一元化できるため、人的コストの削減が見込めます。
さらに、市場や競合の採用状況を調査・分析することで、自社の立ち位置や改善点が明確になり、競合との差別化戦略の立案にも役立ちます。
このように、データに基づいた戦略的な採用活動は、採用成功率の向上、採用コストの最適化、採用プロセスの効率化を同時に実現する重要なアプローチです。
昨今、企業の認知度や求職意識を高めるために、採用ブランディングをする企業が増えています。この資料では、採用ブランディングの概要、メリット・デメリットに加え、具体的な実施手順や成功のポイントを解説します。
人材が定着する組織をつくる5つの実践ポイント

人材の採用・確保に成功しても人材が定着しなければ、採用コストの増大や組織の不安定化を招き、持続的な成長は望めません。
従業員が長く活躍できる組織づくりのためには働きやすさとやりがいを兼ね備えた「働きがいのある会社」を目指すことが重要です。その実現には、待遇改善や制度変更だけでは不十分で、従業員の離職要因を根本から解決し、定着を推進する中長期的な取り組みが求められます。
そこで、人材が定着する組織づくりに向けた5つの実践ポイントをご紹介します。
ミッション・ビジョン・バリューの浸透
ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは、組織が掲げるミッション(使命)、組織が目指す未来像(ビジョン)、そして組織として大切にする価値観や行動指針(バリュー)を指す概念です。
MVVの明確化と社内への浸透は、従業員一人ひとりの行動や判断に一貫性をもたらし、組織全体の方向性を揃える効果があります。MVVが浸透していない組織では、仕事が単なる作業になってしまい、目標との繋がりを実感できず、モチベーションやエンゲージメントの低下から離職につながりやすくなるでしょう。
特に「バリュー(価値観)」は、従業員が日々の業務で判断や行動を行う際の基準となるものです。そのため、管理職が率先してバリューに基づいた行動を示し、職場全体に浸透させることが重要です。例えば「誠実さ」「透明性」といった価値観を、言葉だけでなく具体的な行動で示す必要があります。
MVVの浸透により、従業員は自分の仕事に意味や価値を見出し、組織への帰属意識や働きがいが高まります。バリューをまとめた冊子の配布や研修の実施により、新入社員や内定者も含めた全従業員が価値観を理解し、定着率の向上が期待できます。
「働きがいのある会社」とされる企業は、バリューを明確に定義し、日常のコミュニケーションから採用活動まで、あらゆる場面で価値観の共有を徹底しています。
働きやすさ投資
人材を定着させるには、働きやすい職場づくりが求められます。働きやすい職場づくりには「働きやすさ投資」が欠かせません。従業員の意見を尊重し、安心して働ける環境を整える、適切な設備や休暇制度、ワークライフバランスを推進することなどがポイントです。
例えば、オフィス設備の改善や休暇取得の柔軟化などが挙げられます。加えて、リモートワークなどの柔軟な働き方を導入し、場所や時間に縛られずに働ける環境を整えることも、現代の多様なニーズに応えるために欠かせない施策です
一方で、特定の層に向けた施策を打ち出すことで、企業の姿勢を明確に示す戦略もあります。例えば、授乳室や母乳用冷凍庫の設置は、働く女性や求職者への強いメッセージになるでしょう。
こうした働きやすさへの投資は、従業員のストレス軽減や満足度向上をもたらし、「この会社で長く働きたい」という気持ちを育みます。また、従業員側にも自律的に働く姿勢が求められます。自らのパフォーマンスを最大化するために仕事の進め方を調整し、約束した成果をしっかり出すような自律性が、働きやすい職場をより良いものにする土台となるでしょう。
インクルージョンの担保
人材の定着に欠かせない「働きがい」を高めるためのポイントとして「インクルージョンの担保」が挙げられます。これは従業員全員が尊重され、それぞれの能力を最大限発揮できる環境をつくることを意味します。
多様な人材が安心して意見を交わせる職場には、深い相互理解と信頼関係が欠かせません。経営者や管理職は、日常的なコミュニケーションを通じて従業員一人ひとりを理解し、チームの一体感を育む必要があります。そのためには、次の「相手を理解する3つのフレーム」を意識して対話を重ねることが大切です。
1.Skill(スキル)
どんなスキルを持ち、何ができるのかを知ることです。例えば、ITスキルや動画編集、講師経験などを理解することが挙げられます。
2.Personality(パーソナリティ)
どんな性格や持ち味があるのかといった個々のパーソナリティを把握することです。例えば、気遣いができる、リーダーシップがある、ムードメーカーになれるといった特性が挙げられます。
3.Context(コンテクスト)
どんな背景や思いを持っているのかを把握することです。例えば、将来の目標や働く理由、人脈などが挙げられます。コンテクストの把握には、意識的な対話と情報収集が求められます。
これらの視点を持ち、意識的に会話を重ねることで、多様な人材がお互いを尊重し、一体感を持って働ける職場を実現できます。
インクルージョンを実現するには、職場全体での継続的な学びや、価値観の違いを受け入れる姿勢を育むことが不可欠です。心理的安全性を確保し、誰もが自分の意見を安心して述べられる環境は、従業員の帰属意識や満足度を高め、組織へのエンゲージメントを向上させます。結果として、定着率の向上につながるのです。
<関連記事>
心理的安全性とは?高めるメリットや方法、働きがいとの関連について解説
やりがいに火をつける
ここでいう「やりがい」とは、仕事の中に意味や達成感を見出し、自ら進んで行動したくなる内発的な動機を指します。やりがいを感じている従業員は、仕事への満足度が高く、組織への愛着も深まるため、自然と定着率の向上につながります。
従業員のやりがいを引き出す有効な手段の一つが「1on1(ワン・オン・ワン)」です。上司が部下に対して「なぜこの仕事が大切なのか」を伝えることで、仕事へのモチベーションを上げることができます。1on1の効果を高めるためには、形式だけでなくマインドセットが重要です。上司は1on1を「部下を評価する場」ではなく「支援する場」と認識して取り組む必要があります。また、「最近どう?」「困っていることある?」といったオープンな問いかけや、「ありがとう」「助かったよ」などの承認の言葉を積極的に使うことが効果的です。
さらに効果を高めるためには、1on1の頻度や記録の工夫も重要です。月に1回などの定期的な実施を習慣化し、記録と振り返りを行うことで関係性の強化を図ります。加えて、1on1で共有された内容をもとに成長支援や業務改善に活かすことで、面談が形骸化せず、実効性を持つ仕組みとして機能します。
<関連記事>
1on1ミーティングとは?目的や進め方、話すことのテーマを紹介
職場カルチャーの明確化
人材を定着させるには、職場カルチャーの明確化も重要です。職場カルチャーとは、その組織独自の価値観や雰囲気、働き方のスタイルを指します。例えば「仲間意識が強く部署を超えて助け合える」「上下関係なく意見を言える」「多様な働き方を認め尊重し合える」など、企業風土として根付いたものです。
働きがいはこの職場カルチャーとも密接に結びついています。カルチャーに共感できれば居心地が良く、モチベーション高く働けますが、違和感を覚えると心理的安全性が損なわれ、ストレスの原因になります。例えば、自由度が高い職場を好む人が上下関係が厳しい体育会系の文化に入ると、強いミスマッチを感じるでしょう。
職場カルチャーを明確にし、採用段階から正直に発信することで、価値観の合わない人材の入社を防げます。結果として、入社後のミスマッチによる早期離職を減らし、カルチャーに共感した人材の長期定着が実現できるのです。企業は職場カルチャーを具体的に伝え、求職者も面接やカジュアル面談で従業員と直接話し、価値観の適合性を確かめることが重要です。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
人材確保に成功した企業の事例

多くの企業が人材確保に苦戦していますが、独自の取り組みや工夫により成功を収めている企業も数多く存在します。
ここでは、人材確保に成功した3つの具体的な事例をご紹介します。自社の人材確保戦略を考える上で、参考にしてください。
1.継続的な働きがい向上によって従業員数が倍増した事例
株式会社NEWONEは、「エンゲージメント」を軸に人材育成・組織開発・人事コンサルティングを行う企業で、働きがいを重視した組織づくりによって人材確保に成功しています。
創業当初から個人と組織が相互に貢献し合う関係性を築くことを重視し、管理職向けマネジメント研修や新入社員オンボーディング支援など幅広い研修を展開してきました。
同社が特に重視しているのは、「フラットでオープンな場」をつくり、誰もがそこに参画できる環境づくりです。全従業員参加型のクレド刷新では階層に関係なく全員が意見を出し合い、感謝を可視化するピアボーナス制度では従業員同士が対等に評価し合います。また、部門間交流を促す飲み会補助制度も、部署の壁を越えたオープンなコミュニケーションを促進する仕組みです。こうした取り組みを通じて、月次アンケートと年次調査を活用した組織づくりのPDCAを継続的に実行してきました。
こうした取り組みにより、従業員数は30名台から70名へと倍増し、採用応募数や内定承諾率も向上しました。継続的に組織の状態を可視化し、改善を重ねることで、働きがいの高い組織として多くの人材を引きつけています。
※参考:「4年連続「働きがいのある会社認定」で従業員も倍増! 株式会社NEWONEの事例」
2.働きやすさ投資によって人材確保に成功した事例
レジル株式会社は「脱炭素を、難問にしない」をミッションに掲げ、分散型エネルギー事業・グリーンエネルギー事業・エネルギーDX事業・脱炭素ソリューション事業の4つの事業を展開し、脱炭素社会の実現を目指している企業です。
同社は2021年以降、「働きがい」を競争戦略の中核に据え、スーパーフレックスタイム制やロケーションフリー、副業支援、社内FA制度などの多様な施策を導入し、積極的に働きやすさ投資に取り組みました。これらの施策は、従業員の意志ある成長を支援するためのものです。
さらに、従業員への働きがいアンケート結果は全社に共有するとともに、取締役会や経営会議でも詳細分析を共有し、スコアが高い項目と低い項目を一覧化。各事業部やチーム単位での状況を徹底的に可視化し、データに基づいた改善を継続的に実施しました。
この結果、女性管理職比率は4.5%から23%へと大幅に向上し、多様な人材が活躍できる環境が整備されました。そして、こうした働きやすい環境が評価され、求人応募数は約4倍に増加しました。
※参考:働き方が変わらなければ、ビジネスモデルは変わらない!レジル株式会社の挑戦
「働きがいのある会社づくり」の推進・発信で採用応募者が増加した事例
株式会社ホリエは、デザイン性と住宅性能を兼ね備えた住宅ブランド「シエルホームデザイン」を展開する企業です。
人口約6,000人の町に本社を置いていることから、都市部の企業と比べて人材確保の難易度が高く、給与などの労働条件だけでは差別化が困難でした。そこで「ここで働く特別な価値」を創出する必要がありました。
そこで同社は、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を全従業員で策定し、日常的に浸透活動を行うほか、大胆な権限委譲により若手が大規模プロジェクトを担うなど、企業文化を中心とした「働きがいのある会社」を構築していきました。そして、こうした取り組みが評価され、Great Place To Work®の「働きがい認定」を4年連続で取得しています。
同社は、この認定を積極的に広報活動に活用しました。例えば、採用サイトや会社説明会のチラシで認定マークを掲載し、「働きがいのある会社として第三者機関に認められた企業」であることを強くアピール。地方企業でありながら働きがいの高い職場であることを客観的に証明する強力な武器として活用しました。
その結果、2022年には新卒450名からの応募があり、優秀な人材6名の採用に成功しました。中途採用においても同様で、「働きがい認定があるから応募した」という求職者が多数現れるなど、認定の広報効果が直接的に採用成果につながっています。
同社の取り組みは、地理的なハンデや人口の壁を認定取得と戦略的な発信によって突破した成功事例といえるでしょう。
※参考「人口6,000人の町の働きがい認定企業 「働きがい」で優秀な人材を惹きつける株式会社ホリエの事例」
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
「働きがい認定」で応募数・内定承諾率アップを目指そう

「働きがい認定」などの外部認証制度を積極的に活用することは、人材確保において非常に有効な戦略的取り組みの一つです。
こうした認定は、企業が従業員にとって働きがいのある職場環境を実現しているという客観的かつ公的な証明となり、求職者に対する信頼性や安心感の向上に直結します。
このように、採用ブランディングを強化することで、求人応募者の増加、内定承諾率の上昇、内定辞退率の低下といったさまざまな効果が期待できるため、採用活動全体の効率向上に繋がります。