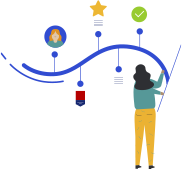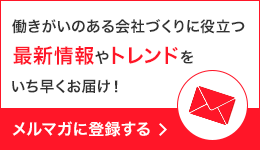リスキリングとは?意味やメリット、導入の方法まで徹底解説
更新日 2023.09.222023.09.22用語集

AIやテクノロジーの進化によって産業構造が大きく様変わりした今、日本政府が推進していこうとしているのが働く人々のリスキリングです。本記事ではリスキリングとは具体的にどのようなものなのか、メリットやデメリット、企業が導入する場合のステップなどについて詳しく解説します。
目次
リスキリングとは?
リスキリング(Re-skilling)とは、既存の従業員が新しいスキルや能力を習得し、異なる職種や業務に適応するプロセスを指します。リスキリングの主な目的は、組織が従業員の能力を最大限に活用し、新しいビジネスニーズに応えることです。技術の進化や市場の変化によって、従来の業務や職種が影響を受ける場合に、労働者たちがその変化に適応するための取り組みとして行われます。
従業員のリスキリングは、以下の要因から重要性を増しています。
① テクノロジーの進化: デジタル化や自動化の進展により、従来の仕事が変わるか消失する場合があり、新しいスキルが求められます。
② 労働力の柔軟性: 組織は、変化する状況に適応できる多様なスキルを持つ従業員を確保する必要があります。
③ 競争力の維持: リスキリングによって、企業は迅速に変化する市場で競争力を保つことができます。
④ 従業員のエンゲージメント: 従業員が成長と学習の機会を提供されることで、モチベーションや満足度が向上する可能性があります。
リスキリングは、教育・トレーニングプログラムやオンラインリソースを活用して実施されることが一般的です。組織は従業員のニーズや適性に基づいてカスタマイズしたプランを策定し、新しいスキルの習得をサポートします。これによって、従業員は変化に適応し、長期的なキャリアの発展を実現できるようになります。
リスキリングとリカレント教育の違い

リスキリングとリカレント教育は、両方とも労働者が変化する職業環境に適応するためのアプローチですが、それぞれ異なる焦点と目的を持っています。
リスキリングは、既存の従業員が新しいスキルや能力を習得し、異なる職種や業務に適応することを指します。これは、急速なテクノロジー進化や市場変化によって、既存の仕事が変わるか消失する場合に行われます。リスキリングの主な目的は、従業員のスキルを最新の需要に合わせてアップデートし、組織内での位置づけを維持または向上させることです。
一方で、リカレント教育は、労働者が一生涯にわたって学習と就労を繰り返すことを強調する概念です。特に、一度会社を退職・求職してから大学などでキャリアに繋がる学習をすることを指します。企業は、個人(従業員)が自己成長や専門知識の更新を通じて持続的なキャリア発展をすることを支援します。これにより、個人は変化する環境に適応し続けることができます。
まとめると、リスキリングは変化に対応するために既存の従業員のスキルをアップデートすることに焦点を当て、リカレント教育は一生涯の学習を通じて個人のキャリア発展を支援することに焦点を当てています。リスキリングは企業主体で、リカレント教育は個人主体と捉えることもできます。両者は相補的なアプローチであり、労働市場の変化に適応し、持続的な成長を実現するために重要な役割を果たします。
リスキリングが注目される背景
リスキリングという言葉がよく聞かれるようになった背景には、主に以下の2つの出来事があります。
2020年世界経済フォーラム(ダボス会議)の主要議題に
2020年の世界経済フォーラムの年次総会では、リスキリング革命が主要な議題となりました。世界経済フォーラムは、2030年までに全世界で10億人により良い教育、スキル、仕事を提供する必要があると提唱しています。
リスキリング革命を成功させるためには、政府、企業、個人が連携して取り組む必要があります。
- 政府:リスキリングのための教育や研修プログラムを提供するとともに、企業が従業員のリスキリングを支援するためのインセンティブを導入する
- 企業:従業員のスキルアップを促進するための教育や研修プログラムを提供するとともに、リスキリングに必要な費用を負担する
- 個人:新しいスキルを習得するために自ら主体的に学び、研鑽する
2022年10月に岸田総理がリスキリング支援を表明
岸田総理は、2022年10月に所信表明演説で、リスキリング支援を表明しました。これは、デジタル化やAIなどの技術革新によって、既存のスキルが陳腐化していく中で、新しいスキルを習得し、再就職や転職を成功させるための取り組みです。
岸田総理は、リスキリング支援として、次のような施策を打ち出しています。
- リスキリングのための教育や研修プログラムの提供
- 企業が従業員のリスキリングを支援するためのインセンティブの導入
- 個人がリスキリングを行うための費用の補助
岸田総理のリスキリング支援は、日本の労働者がデジタル化やAIなどの技術革新に適応し、新しい仕事に就き、経済成長に貢献するために重要なものとされています。
企業がリスキリングを推進するメリット
企業がリスキリングを推進する具体的なメリットとしては、以下の4つが挙げられます。
人材不足への対応、採用コスト削減
従業員に新たなスキルを提供することで、将来の需要に適応し、最新の技術や業務に対応できるようになります。これにより市場環境やニーズの変化があっても外部から新たに人材採用をする必要性が減少し、柔軟に人材不足に対処できるようになります。また、採用コストの削減にも繋がります。特にデジタルスキルに長けたDX人材は獲得競争が激しく採用コストが高くなる傾向にあるため、これは大きな利点です。
エンゲージメントの向上

リスキリングは従業員に新たなスキルを学ぶ機会を提供し、自身の成長に対する意欲を高めます。新たなスキルを習得する過程は充実感をもたらし、モチベーションを向上させます。それと同時に、そのような学習機会を提供してくれる会社に対してのエンゲージメントが高まります。
関連記事:エンゲージメントとは?従業員満足度との違いや高める方法
離職率の低下
リスキリングは企業が従業員に対してキャリアパスをサポートする姿勢を示し、成長機会を提供するものです。新たなスキルの習得や自己研鑽に価値を感じる従業員にとって、そのような機会の提供は会社に留まる理由のひとつになります。選択肢が豊富であればあるほど、他の企業では得られない経験として従業員には魅力的に映ります。結果として離職率の低下に繋がることが考えられます。
イノベーションの促進
新たな知識やスキルの獲得は、既存の業務の改善だけではなく、新たな事業機会の創出に繋がるものです。企業としては、社内ビジネスコンテストの開催など、知識やスキルを活かしたアイデアを発散する場などを組織的に設けることで、イノベーションの芽を作ることに繋がります。
関連記事:イノベーションとは?ビジネスにおける定義や課題を解説
リスキリングを導入するデメリット
リスキリングの導入にはいくつかのデメリットが考えられます。これらのデメリットを適切に管理し、メリットとバランスを取りながら導入することが求められます。
導入に予算と時間がかかる
リスキリングの導入には相応の予算と時間がかかります。トレーニングプログラムの設計や実施、従業員の学習時間などにコストと労力が必要です。また、既存の業務に負担をかける可能性があるため、生産性への一時的な影響も考慮する必要があります。
従業員が抵抗感を示す場合がある
すべての従業員がリスキリングに対して前向きになるとは限らず、抵抗感を持つ従業員が出てくる場合があります。新たなスキルを習得する過程は時間と努力が必要であり、従業員はそれに対するモチベーションを持って取り組む必要があります。また、一部の従業員が既存のスキルに固執する可能性もあります。
従業員間でスキルの差が生まれる
全ての従業員がリスキリングに参加するわけではない場合、特定の人材のスキル向上が他の従業員とのギャップを生む可能性も考慮すべきです。企業としてはナレッジ共有会を開催したり、リスキリングを経た従業員を新たに入社する社員のメンターにアサインしたりして、知の還流が行われるように配慮することが大切です。
継続的な運用が必要
特にデジタルスキルについては、急速な技術進化に追いつくため、リスキリングの内容を継続的に更新・改善する必要があります。これには新たな教材の開発やトレーニングの再設計などが含まれ、労力とコストがかかる可能性があります。
日本のリスキリング導入における課題

日本におけるリスキリング導入にはいくつかの課題が存在します。まず、少子高齢化社会であることから、若手社員へのスキル普及もさることながら、中堅・シニア層のスキル転換が欠かせません。しかし長くキャリアを築いている経営層や社員は伝統的な教育文化や働き方に固執する場合があります。そういった抵抗を乗り越え、全社的にスキルアップ意識を高める必要があります。
さらに、リスキリングには予算や時間がかかるため、日本企業の9割以上を占める中小企業での導入が遅れがちです。教育制度やトレーニングプログラムの整備も不可欠であり、業界ごとに必要なスキルの違いも考慮する必要があります。ここには政府・自治体の費用的補助に加え、外部の専門家の協力が必要になってきます。
また、デジタルスキルという面では急速なテクノロジーの進化に追いつくため、常に最新のスキルを提供する必要がありますが、それが継続的な課題となっています。日本は「IMD世界デジタル競争力ランキング(2022年)」において63か国中29位で、また4年連続で順位を下げているDX後進国です。リスキリングの取り組みそのものについても、まずタレントマネジメントなどのHR techを活用し、社内の保有スキルを可視化するところからの整備が必要です。
総括すると、日本におけるリスキリング導入の課題は、伝統的な文化や働き方の変革、中小企業の参入障壁、教育制度の改革、テクノロジーの追従など幅広い面にわたります。これらの課題に対処しながら、リスキリングを成功させるための環境整備と取り組みが求められます。
リスキリングを導入するための方法
リスキリングの導入を効果的かつ持続的に行うための、ステップの一例です。
①モチベーションの促進
まず、経営層や人事からリスキリングの目的や価値を従業員に明確に伝え、彼らの自律性を引き出すことが大切です。会社の目指す方向性に新たなスキルが必要であることを強調します。キャリアパスや報酬の見直しも考慮することを伝えられるとより効果的でしょう。
②スキルマッピングと評価
従業員の現有スキルと将来のスキル要件を整理し、どのようなスキル人材が足りていないのか、ギャップを特定します。これにより、具体的なリスキリングの方向性を把握できます。
③トレーニングプログラムの設計
特定されたスキルギャップに基づき、従業員に適切なトレーニングプログラムを設計します。オンラインコース、ワークショップ、内部トレーナーによるセッションなど、多様な方法を組み合わせて提供します。
④実践機会の提供
社内プロジェクトなどを通じて、新たなスキルを実際の業務に適用する機会を提供します。実務経験を通じて従業員がスキルを磨き、自信を得ることができます。
⑤フィードバックと改善
プログラム進捗を定期的に評価し、従業員からのフィードバックを収集します。必要に応じてプログラムを調整・改善し、継続的な質の向上を図ります。
⑥上司によるサポート
上司からのバックアップとリーダーシップは、従業員のリスキリングへの参加意欲を高めます。上司は1on1などの機会を活用し、部下が目指すゴールに対して進歩できているか、つまずいていないかなどを丁寧に確認します。
⑦継続的なモニタリング
リスキリングの成果を定期的に評価し、改善の余地や新たなニーズを把握します。継続的な学習文化を育成するために、定期的なトレーニングの提供も検討します。
リスキリングで人気の学習テーマ

デジタル(DX)
リスキリングにおいて最も人気を集めている学習テーマの一つは、「デジタルスキルの強化」です。現代の労働環境では、デジタルテクノロジーがますます重要となり、従業員はこれに適応するスキルを必要としています。
デジタルスキルの強化には、プログラミングやソフトウェア開発、データ分析、AI・機械学習などの分野が含まれます。これらのスキルは、企業がデジタル化やオンラインプレゼンスの強化を追求する中で、求められる要素となっています。従業員がこれらのスキルを習得することで、業務の効率化や新たなビジネス戦略の実現に貢献することができます。
コミュニケーション
コミュニケーションスキルも不動の人気テーマです。リモートワークの増加により、遠隔でのコミュニケーションの難しさを感じる機会も増えています。単なる「会話」ではなく、相互信頼を生み出し物事を前に進める「対話」のスキルを学ぶことは、チーム、会社、顧客や取引先など多様な範囲に大きな貢献をもたらします。
リーダーシップ、マネジメント
リーダーシップやマネジメントスキルも注目されています。数十年前と現在では、必要とされるリーダーシップやマネジメントの在り方も変わってきています。また組織のステージや市場におけるポジションによっても異なります。従業員が時代と環境に応じたリーダーシップ・マネジメントのスキルを習得することで、組織の成果や文化を形成する力を高めることができます。
まとめ
リスキリングは、従業員が変化する環境に適応し、新たなスキルを習得するプロセスです。VUCA時代と言われる不確実で変化の激しい現代社会において、企業がリスキリングの体制を整えておくことは、経営面の成果だけでなく従業員の雇用を守ることにも繋がります。本記事でご紹介したステップや課題を意識しながら、是非取り組んでみてください。
●関連情報
リクルートマネジメントソリューションズ「リスキリング強化特集」(研修コース)
「働きがいのある会社」を
目指しませんか?
GPTWは世界約150ヶ国・年間 10,000社以上の導入実績を活かし、企業の働きがい向上や広報をサポートします。
- 自社の働きがいの現状を可視化したい
- 働きがい向上の取り組みを強化したい
- 採用力・ブランド力を向上させたい