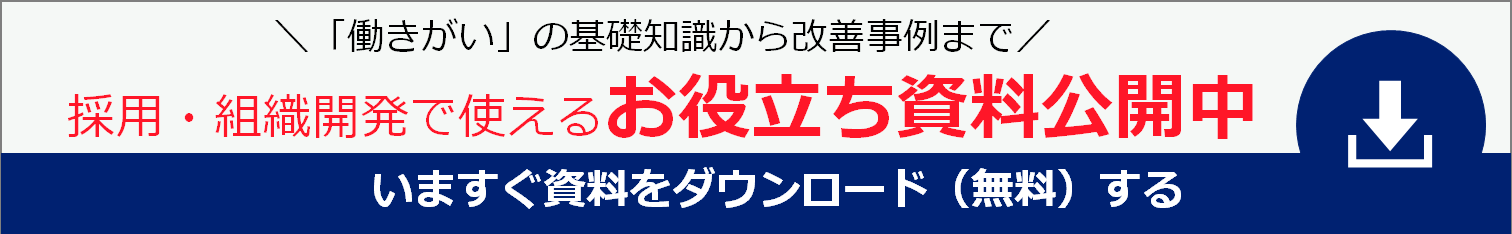組織拡大がもたらす"見えないリスク"とは?
更新日 2025.09.242025.09.24コラム

事業が拡大し組織規模が大きくなる過程では、経営者や人事担当者は「見えないリスク」に直面することがあります。特に急速な成長期には、創業当初にはなかった課題が次々と顕在化し、これまで有効だった仕組みや文化が機能しなくなるケースも少なくありません。
現場と経営の意識のズレ、マネジメント層の未成熟、従業員の働き方の限界など、組織に潜むリスクは、放置すれば成長を阻害する要因となります。
本記事では、組織拡大とその成長段階に触れつつ、そこに潜む組織の「ひずみ」の存在を明らかにし、先手を打って対策を講じる方法やうまく乗り越えた事例を解説します。
組織拡大とは?

組織拡大とは、企業が成長に伴って人員や事業規模を拡大し、組織体制を変化させていくプロセスを指します。
ここでは、組織拡大の成長段階や企業規模ごとの変化、それぞれのメリットに付いて解説します。
組織拡大の成長段階
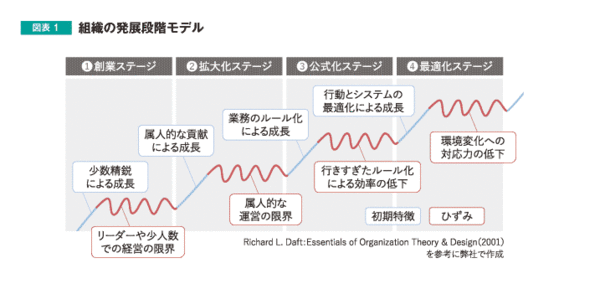
画像引用:リクルートマネジメントソリューションズ「「組織の発展モデル」から組織課題の焦点を発見する
組織の拡大は、人間の成長過程のように段階を経て進みます。
組織発展段階モデルによれば、企業は創業ステージ・拡大化ステージ・最適化ステージといったステージを経るなかで、次の段階に進むための「壁」に直面します。この壁こそが「組織のひずみ」であり、適切な対応ができなければ成長の停滞を招きます。
創業ステージは資金調達や事業を軌道に乗せることに追われる一方で、拡大化ステージ・最適化ステージでは人材の採用や育成、組織体制の見直しなど、人事課題に直面しやすくなるという調査結果もあります。
特に急成長する企業では、事業の拡大スピードに組織の成長が追いつかず、人事制度の未整備や情報共有の遅れなどが発生しやすい傾向にあります。
このように、組織の成長過程で必ず発生する「ひずみ」こそが見えないリスクの正体であり、このひずみをいかに早期に捉え、適切に乗り越えていくことが持続的な企業成長・組織拡大の鍵となるのです。
組織の「ひずみ」を放置すると何が起きるのか?
組織の「ひずみ」は放置すればするほど深刻化します。
表面的には業績が伸びているように見えても、裏側で解決されない課題が積み重なると、成長が鈍化したタイミングで一気に問題が表面化する場合があります。その結果、意思決定や実行のスピードが低下し、戦略の実行力そのものが損なわれるリスクが高まります。
さらに、社内の混乱や疲弊が先行して表れ、社員のモチベーション低下や離職率の上昇などにつながり、事業成長に直接的なブレーキをかける恐れもあります。
多くの企業では、何か違和感があっても対応は後回しにされがちです。現場から声が上がらなかったり、リーダーが感度を失っていたりすることで、問題の存在自体を認識できず、結果的に放置されるケースも少なくありません。
つまり、組織のひずみを無視するのは、経営判断ミスや戦略失敗を放置しているのと同じであるため、表面化する前に察知し、早期に対処する仕組みを整えることが重要です。具体的な対処法については後述します。
採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!
組織の発展モデルの特徴と起こり得るひずみ

組織拡大は成長の証であると同時に、構造と心理の両面に新たな課題やリスクをもたらします。
組織の人数が増えると意思決定にかかる時間が伸びたり、情報の粒度がばらついたりしてきます。30人規模を境に、中間管理職を介する運営への移行が必要になり、経営者が全員と直接対話することが難しくなってくるため、従業員の日々の悩みや不満、ズレに気付きにくくなります。
さらに、これまで機能していたルールや慣習が通用しなくなり、経営理念が浸透しづらくなるなど、企業文化や組織の一体感が揺らぎやすい時期です。
課題を早期に認識して適切な対策を講じなければ、組織運営はたちまち立ち行かなくなり、事業の成長が鈍化したり、最悪の場合は組織崩壊を招く恐れもあるため注意が必要です。
ここからは、組織の発展モデルの特徴と、それぞれのステージにおいて起こり得るひずみについて解説していきます。
創業ステージ
創業ステージは、志を共にする少数精鋭が熱量とビジョンで突き進み、開発や顧客検証に全精力を注ぐ段階です。組織運営の仕組みは未整備のため、信頼と暗黙知、各自の感覚に依存しやすく、意思決定は創業者へ集中するのが特徴です。
そのため、意思決定や実行までのスピードは速いものの、判断の負担が一点に集中することでリーダーが疲弊しやすくなります。
また、役割が曖昧なまま進んでしまうと業務は属人化し、その後の再現性が担保できません。それまでのノウハウやナレッジが言語化されていない状態で人員を増やしても、指示待ちや教育などの重複対応、トラブル対応に追われてしまい、思うように生産性が上がりません。
採用後のオンボーディングも体力勝負になりがちで、育成が間に合わないことでサービスや商品の品質が低下する場合もあります。
これが創業ステージで起こりがちなひずみであり、乗り越えるためにはその後の組織拡大を見据えた準備をしておくことが重要です。
<関連記事>
採用力が業績を左右する時代:今なぜ"採用力強化"が必須なのか
拡大化ステージ
拡大化ステージでは、売上と人員が急増し、専門部署や中間管理職が導入されます。オペレーションが徐々に体系化していき、増えた人員でうまく業務を回すための仕組みや、人事・評価などの制度づくりも進んでいきます。
一方で、組織間・部門間の連携不足(サイロ化)が起こりやすく、チームワークが乱れやすい時期でもあります。急増した人数に対応するために中間管理職を置くも、経験やスキルが不足していることでマネジメントが機能不全に陥るケースも少なくありません。
また、創業ステージから属人化していた業務の標準化を図る際も、方針の不一致やコミュニケーション不全が顕在化し、再現性の高い「やり方」が固まるまでは、トラブルやイレギュラー対応が多発し、現場が混乱しがちです。
さらに、採用スピードに人材育成や文化醸成が追いつかないと、組織文化や価値観の分裂や対立が発生しやすくなり、生産性の低下や離職率の上昇などを招きます。
公式化ステージ
公式化ステージは、業務プロセスや権限、制度が文書化されるなど、ルールとマニュアルが整ってくる段階で、企業としてのミッションやバリューの再定義、それらを組織全体に浸透させるための活動が活発化します。
また、公式化ステージは拡大化ステージの慌ただしさが落ち着き、組織としての安定性や継続性が重視される時期でもあります。
その反面、過剰なルールやそれらを守ろう、守らせようとするあまり、形式主義・官僚主義に傾いてしまうと、現場レベルの柔軟性が低下し、迅速な意思決定ができないことがあります。このような状況になると、あらゆる面で本質よりも形式や手続きばかりが重視される非効率な組織文化に転落します。
さらに、安定性や継続性を重視しすぎると挑戦する意欲が低下し、イノベーションの芽を摘むリスクも高まります。
このように、公式化ステージでは組織の秩序を安定化させる一方で、硬直しないようにチャレンジを重んじる文化を醸成するといったバランスが重要です。
最適化ステージ
最適化ステージは、組織や事業が持続的に成長していけるよう、変化に対応しながら効率性や生産性の向上が重視される段階です。
事業や業務の現状をより正確に把握するために、データに基づいて業務改善を行い、各所にテクノロジーを導入して効率と生産性を高めようと働きかけます。
また、競争力を保つために、人材育成や定着率の向上にも重きを置く時期であり、自社での働きがいやエンゲージメントの設計も重視されます。経営層と現場間で対話と評価の仕組みを整備し、現場の声を拾い上げ、評価や報酬の適正化を図ります。
一方で、数値偏重や行き過ぎた成果主義が人心の離反を招き、チームワークの低下や不満の増加、離職率の上昇などにつながる場合もあります。さらに、「管理される感」が強まると、従業員一人ひとりの主体性や創造性、モチベーションが低下してしまいます。
組織や事業が成熟しすぎて、変化への対応力が鈍化したり、新たな成長機会を見失う「停滞の罠」がこの段階のひずみといえるでしょう。
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
組織拡大で起こり得る「ひずみ」を乗り越えるステップ
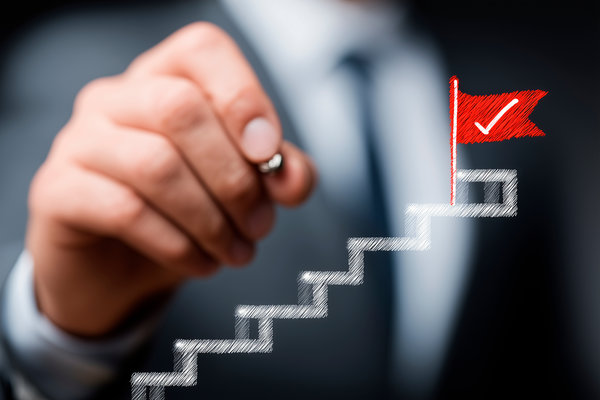
組織が成長する過程で「ひずみ」が生じるのは自然なことであり、避けられない現実です。むしろ、「ひずみ」が生じるのは組織が拡大している証拠ともいえます。
重要なのは、その問題を放置するか、あるいはしっかり向き合って先手を打つかという姿勢です。
ここでは、組織拡大の過程で起こりえる「ひずみ」を乗り越えるために、「予測する」「現状を把握する」「打ち手を講じる」という3つのステップを解説します。この順番を意識することで、「ひずみ」によるリスクを最小限に抑え、組織をスムーズに拡大していけるでしょう。
ステップ1:予測する
課題を乗り越える第一歩は、成長に伴い「ひずみは必ず生じる」という前提に立ち、将来起こり得る課題を具体的に予測することです。
Great Place To Work®では、組織拡大にあたり「組織」と「個人」の両面で、得るものと失うものを整理することを推奨しています。
組織の拡大は、多くの利点と同時に、避けがたい課題も伴います。まず、組織としては、社会に対するインパクトをより広範囲に与えることが可能となり、権限を現場に移譲することで意思決定や業務遂行のスピードが加速します。一方で、規模が大きくなるにつれ、経営と現場の距離が広がり、密なコミュニケーションが難しくなります。
また、レポートラインが複雑になることで、意思決定に時間がかかるようになり、新任管理職が部下のマネジメントに苦慮し、モチベーションの低下を招くリスクもあります。
個人にとっては、業務の分担が進むことで負荷が軽減され、自分がやりたい仕事に集中しやすくなるというメリットがあるものの、同時に、経営の意思決定に直接関与する機会が減り、トップとの距離を感じるようになるなど、組織との一体感が薄れる側面もあります。
特に従業員数が30人・50人・100人に達する局面は「節目」とされ、30人規模では権限委譲と中間層の育成、50人規模では意思決定の遅延や文化の揺らぎ、100人規模では制度疲労やサイロ化の進行が顕著になるといわれています。
こうした課題を事前に予測しておけば、兆候が表れた段階で迅速に察知し、後手に回らず対応できるでしょう。
【ホワイトペーパー】30人・50人・100人の壁の乗り越え方
組織成長の壁とは、ベンチャー企業やスタートアップ企業の規模が大きくなり、従業員数も増加していくなかで生じるさまざまな問題です。この資料では、問題が起きやすい30人・50人・100人の壁に焦点を当て、組織成長の壁を乗り越えるステップや注意点について解説します。
ステップ2:現状を把握する
予測を立てたら、次は現状を正確に把握し、ひずみが生じていないかを確認しましょう。
問題は多くの場合、表面化する前に兆候が現れるため、そのような異変にすぐに気付くためにも継続的なチェック体制を整えることが大切です。
具体的な手法としては、年1回のエンゲージメントサーベイや360度サーベイによる網羅的な調査が挙げられます。これにより、社員のモチベーションや信頼関係を数値化した把握が可能です。さらに、月1回の上司・人事・チューターによる1対1ミーティングを実施すれば、従業員の小さな不安や悩みを吸い上げやすくなります。
併せて、匿名で投稿できるバーチャル目安箱を設置することで、声を上げにくい社員からの意見も集めやすくなるでしょう。また、ミーティング終了直後に簡単なアンケートを行い、空気感を即座に把握することも有効です。
こうした複数の仕組みを組み合わせることで、数字と感覚の両面から現状を捉え、先手を打った対応が可能になります。
【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】
エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。
ステップ3:打ち手を講じる
現状把握で浮かび上がった課題は、原因を追求して打ち手を講じる必要があります。
例えば、調査の結果「組織の連帯感は高いが経営層への信用が低い」と判明した場合、組織規模が急成長したことで、創業メンバーや経営層が思い描く理念や戦略が伝わりにくくなっていたり、中間管理職になんらかの不満が溜まったりするかもしれません。
課題に対する仮説が立ったら、経営層は方針をより具体的かつ納得感のある形で発信し、社内への説明責任を果たす、社員の声を反映できる場を設けてボトムアップの文化を強化する、ミドルマネジメント層に対してはマネジメント研修などを行ってスキルアップを図るといった打ち手が考えられます。
さらに、打ち手は一度で終わるものではなく、定期的に検証と修正を繰り返すことで初めて成果につながります。改善を継続する姿勢こそが、組織の持続的な成長を支える鍵となるのです。
<関連記事> プレイングマネジャーとは?役割や抱える課題、支援の方法を解説
組織拡大時に「ひずみ」を乗り越えた事例

組織が拡大する局面では、現場と経営の意識のズレ、働き方の限界、中間層のマネジメント力不足といったひずみが生じますが、このような課題を乗り越えられるかどうかがその後の成長を大きく左右します。
ここからは、実際に起きた「ひずみ」と向き合い、それを乗り越えた3社の取り組み事例を紹介します。
事例1:株式会社コラボスタイル
株式会社コラボスタイルは、2023年版「働きがいのある会社」ランキング小規模部門で初参加ながらベストカンパニー入りを果たした注目企業です。
同社はクラウド型ワークフローシステム「コラボフロー」を展開し、急速な事業成長の中で組織マネジメントの強化に取り組んできました。特徴的なのは、積極的な権限移譲によって中間層に責任を与え、「チャレンジは正義」「スピードは正義」というスローガンのもと、上司と部下が相互にマネジメントする仕組みを築いた点です。
さらに「肯定ファースト」のカルチャーや「上司一人ルール」により、納得度の高い環境を整備するなど、社員が安心して働ける基盤を作ることで、働きやすさの向上と従業員満足度の向上に成功しています。
こうした積極的な施策が組織の「ひずみ」を乗り越える力となり、持続的な成長を後押ししています。
参考:株式会社コラボスタイル
事例2:ブラックライン 株式会社
ブラックライン株式会社は、日本上陸からわずか4年で「働きがいのある会社」ランキング小規模部門39位に選出された外資系SaaS企業です。
急速な拡大期において同社が重視してきたのは「一枚岩」の組織づくりです。顧客満足を最優先に据え、従業員全員が共通の方向を向くことが事業成長につながると考えています。
その基盤となるのが全員参加で決めた「コアバリュー」であり、カルチャーフィットを徹底した採用や日常的な賞賛制度を通じて浸透を図っています。さらに「Work from Anywhere」に象徴される柔軟な働き方や「ファミリーファースト」の文化により、多様な人材が安心して働ける環境を整備するなど、積極的な取り組みが採用や外部からの信頼強化にもつながっています。
採用において妥協せず、価値観を共有できる人材を迎える姿勢が、組織のひずみを防ぎ、持続的成長を支える原動力となっています。
参考:ブラックライン株式会社
事例3:株式会社ARISE analytics
株式会社ARISE analyticsは、KDDIとアクセンチュアのジョイントベンチャーとして2017年に設立され、2023年版「働きがいのある会社」ランキング中規模部門でベストカンパニーに選出されました。
異なる文化を持つ両社出身者の融合にあたり、当初は思考プロセスの違いから摩擦も生じましたが、全社員で議論を重ね「目指す姿」を共有することで乗り越えてきました。
さらに「働きがい」を包括的に推進する役職としてCWOを設置し、教育体系「ARISE University」や勉強会を通じてデータサイエンティストの成長を支援し、コロナ禍では社内報やオンライン交流施策を導入し、連帯感の維持にも注力してきました。
また、サーベイを通じて組織を「見える化」するなど、従業員の声を経営に生かす姿勢が従業員からの信用につながり、ひずみを成長の糧へと変えることに成功しています。
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
「ひずみ」の可視化と採用強化を両立するならGPTW の「エンゲージメントサーベイ」

組織拡大の過程では必ず「ひずみ」が生じます。重要なのは、その兆候をいち早く可視化し、適切な打ち手につなげることです。
組織の状況を把握するツールとして、「エンゲージメントサーベイ」がおすすめです。GPTW の「エンゲージメントサーベイ」は「働きやすさ」と「やりがい」の両面から「働きがい」を測定できるだけでなく、結果が一定基準を超えると「働きがいのある会社」として認定を受けられます。
従業員の声に基づいた客観的な評価により、採用市場での信頼性向上にもつながるため、現状把握と採用強化を同時に実現できるでしょう。
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!