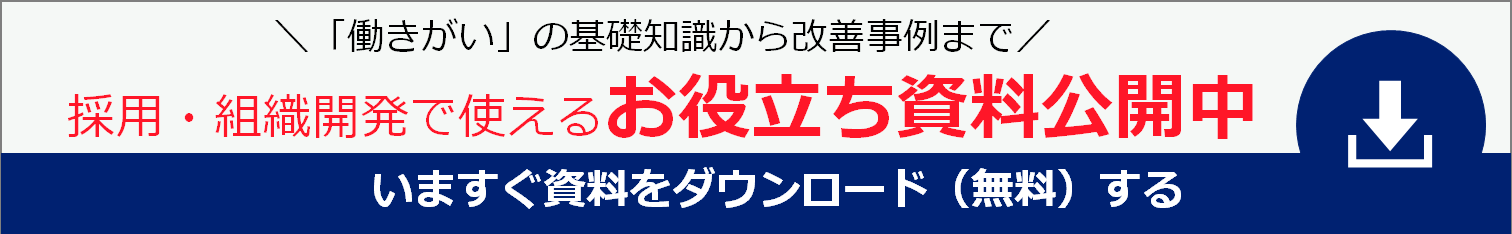採用のミスマッチが起きてしまう原因とは?早期離職を防ぐ対策について解説!
更新日 2025.09.242025.09.24コラム

採用活動で避けて通れない課題の一つが「採用のミスマッチ」です。企業と候補者の間で認識のズレが生じると、入社後に「思っていた仕事内容と違った」「職場の雰囲気になじめない」といった不満につながります。そして、早期離職やモチベーション低下、ひいては生産性の低下を招くリスクがあります。
上記のような事態を防ぐには、なぜミスマッチが起きるのか、原因を正しく理解して適切な対策を講じることが不可欠です。本記事では、採用のミスマッチが発生する具体的な原因を「新卒採用」「中途採用」のケースに分けて整理し、それぞれの場面で効果的に実践できる対策を解説します。
採用ミスマッチの状況とデメリット

「採用ミスマッチ」は、企業と候補者の間で期待や認識がずれてしまうことで発生します。以下、採用ミスマッチが現状でどのような状況になっているのか、そして実際にどのようなデメリットがあるのかを解説します。
採用ミスマッチの状況
厚生労働省が令和6年10月25日に公表した「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」(※)によると、就職後3年以内に離職する割合は、新規高卒就職者で38.4%、新規大卒就職者で34.9%と、依然として高い水準で推移しています。
さらに事業所の規模によっても差が見られ、例えば従業員数が5人未満の小規模事業所では、大卒者の3年以内離職率が59.1%と高い数値を示しています。産業別では「宿泊業・飲食サービス業(56.6%)」「生活関連サービス業・娯楽業(53.7%)」など、サービス業を中心に離職率が突出して高い傾向があるようです。
※参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」
採用ミスマッチで起こり得る三つのデメリット
採用段階で生じた企業と候補者の認識のズレは、入社後にさまざまな形で表面化します。以下では、採用ミスマッチによって起こり得る代表的なデメリットを3つに整理し、それぞれの影響を解説します。
<関連記事> リテンションとは?意味や人事施策の効果・マネジメント方法など詳しく解説
早期離職のリスクが高まる
採用ミスマッチでまず注意したいのが、早期退職のリスクです。入社直後に仕事内容や職場環境が想像と違うと感じると、「この会社で頑張る意味があるのか」という疑問が芽生えます。小さな違和感が積み重なり、その結果として「辞めても構わない」と考えるようになります。
特に即戦力として採用されたハイレベルな人材は、転職市場における需要も高く、自らの市場価値を把握しているケースがほとんどです。そのため転職のハードルが低く、ギャップを感じた際に転職を決断しやすい傾向があります。新卒採用の場合も同様で、多様な働き方が認められるようになった昨今、転職・退職のハードルはそれほど高くありません。
採用・育成コストの無駄が生じる
採用ミスマッチが発生すると、企業にとって大きな損失となるのが「採用・育成コストの無駄」です。人材を1人採用するためには、求人媒体の掲載料、採用担当者の工数、面接や選考の運営費用など、多大な時間と費用がかかります。特に近年は人材獲得競争が激化しており、採用単価も上昇傾向にあります。
さらに採用後には、新人の育成や研修にリソースを投下しなければなりません。せっかく教育を施しても、本人が成果を出す前に離職してしまえば、その投資は回収できないまま失われます。金銭的な無駄にとどまらず、教育担当者やチームの負担増にもつながります。
加えて、離職が発生すれば再び採用活動をやり直さなければならず、追加の費用と工数が必要です。採用ミスマッチは、「単なる失敗」で終わらず、次の採用・教育プロセスにも波及します。
現場のモチベーション低下を招く
採用ミスマッチによる早期離職が続くと、現場における士気やモチベーションにも深刻な影響が及びます。
まず、離職が連続すると、職場全体に不安感を与える要因となります。「なぜ次々と人が辞めていくのか」「この職場に長くいて大丈夫なのか」といった疑念が広がり、従業員の心理的安全性が損なわれるかもしれません。
また、残った従業員の業務負担も増加します。人員が補充されるまでの間は既存メンバーが業務をカバーする必要があり、過重労働や疲弊感につながります。結果として、採用担当者や人事部への信頼低下につながるかもしれません。
<関連記事> 採用力が業績を左右する時代:今なぜ"採用力強化"が必須なのか
採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!
採用ミスマッチが発生するのはなぜ?

採用ミスマッチが生じる背景には、単一の理由ではなく複数の要因が絡み合っています。ここからは、新卒採用と中途採用に分けて、採用ミスマッチがどのように発生するのかを具体的に掘り下げます。
新卒採用のケース
新卒採用では、社会人経験を持たない学生が主な対象となるため、企業の実態や仕事内容に対して認識のズレが生じやすい傾向があります。企業側にある原因としては、「説明会や採用広報で十分な情報を提供できていない」「面接・選考で学生の適性を見極めきれていない」などです。
一方、学生側も社会人としての実務経験がないため、自己分析や企業研究が浅く、入社後に「想像と違った」と感じやすい状況にあります。以下、新卒採用での課題と、早期離職を防ぐための具体的な防止策を解説します。
入社前後のフォロー体制ができていない
新卒採用では、入社前後のフォロー不足が採用ミスマッチを引き起こす大きな要因です。入社前のフォローが不十分だと、学生側の不安感が強まり、「本当にこの会社で良いのか」と迷いがちです。このような不安から内定辞退や入社直後の早期離職につながるリスクが高まります。
また、入社後のオンボーディングや研修体制が整っていない場合も問題です。初期段階での教育やサポートが不十分だと、「期待されていないのでは」と感じたり、職場にうまく適応できず孤立感を深めたりします。
メンター制度や相談体制が用意されていない職場では、困難や悩みを抱え込んだまま退職を選択するケースも少なくありません。このように入社前後のフォロー体制が欠けていると、採用ミスマッチを加速させる要因となります。
十分な情報共有・相互理解ができていない
新卒採用での採用ミスマッチの背景には、企業と学生との間で十分な情報共有や相互理解ができていない点も挙げられます。
企業側の典型的な問題は、説明会や面接で企業の良い側面ばかりを強調し、課題や困難な部分を十分に伝えていないケースです。具体的な業務内容や職場環境について説明が曖昧であったり、入社後のキャリアパスに関する情報提供が不足していたりすると、ギャップを持たれやすくなります。
一方で、学生側も十分な企業研究や業界理解ができていない場合があります。社会人経験のない新卒は、情報収集の不足から「何となくのイメージ」で就職先を決めてしまうケースも少なくありません。その結果、入社後にギャップを痛感し、「思っていたのと違った」と早期離職につながります。
適切な選考・評価ができていない
選考や評価の不十分さも、新卒採用におけるミスマッチの要因です。企業側で「採用要件や理想とする人物像が不明瞭」なまま採用活動を進めると、面接でどの点を重視すべきかが定まらず、結果的に基準が曖昧な状態で選考を進めます。
特に新卒採用においはスキル面だけでなく、人柄や価値観、潜在能力を丁寧に把握するのが重要です。しかしそれができていないと「企業文化や仕事のスタイルに合わない人材」を採用してしまい、入社後にギャップが生じやすくなります。
採用ミスマッチを防ぐためには、まず自社が求める理想の人物像を明確に定義し、その基準に基づいて候補者を評価することが欠かせません。それを前提として、人柄や価値観、将来的な成長の方向性が自社と合致しているかどうかを見極める必要があります。
<関連記事> 360度評価(多面評価)とは?メリットやマネジメント方法・失敗例と対策を解説
透明性のある組織・制度運営ができていない
新卒採用では、組織や制度の運営に透明性が欠けているのも、採用ミスマッチを引き起こす大きな要因となります。
ありがちなのが、配属先や業務内容が不透明である場合です。学生は「どの部署で、どのような仕事をするのか」を明確にイメージできず、不安を抱えたまま入社します。入社後に想定外の配属を受ければ、ギャップが大きくなり、早期離職につながりかねません。
それから、評価制度や昇進の仕組みも問題になりやすい部分です。どのような基準で評価されるのか、どの程度努力すればキャリアを積み重ねられるのかが見えないと、将来像を描けず、働き続けるモチベーションが低下します。
さらに、職場の人間関係や企業文化とのミスマッチも、新卒が直面する大きな課題です。制度や方針だけでなく、日常的なコミュニケーションのスタイルや価値観が合わないと、働きにくさを感じやすくなります。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
中途採用のケース
中途採用でも、採用ミスマッチは大きな課題となっています。新卒採用と異なり、候補者は社会人経験を有しているため、スキルや実績を前提とした即戦力として期待できます。
しかしその一方で、前職との比較やキャリア志向の違いなど、独自の要因によってミスマッチが発生しやすい側面があるため注意が必要です。ここからは、中途採用における代表的な原因を整理し、どのような背景でミスマッチが生じるのかを解説します。
候補者のスキルがニーズと合っていない
中途採用におけるミスマッチの代表的な原因が、候補者のスキルと企業が求めるニーズとの不一致です。企業側が即戦力を期待して採用したにもかかわらず、実際には求められる専門スキルや経験が不足しており、周囲の従業員に大きな負担がかかります。
スキル不足の状態で採用されると、本人にとっても「期待に応えられていない」というプレッシャーや不安感が生まれ、早期の離職につながりかねません。結果として、企業は再度の採用活動や育成コストを余儀なくされるなど、悪循環に陥るリスクがあります。
このような状況を防ぐには、採用前の段階で「自社で活躍する人材の特性と必要なスキル」を明確に定義し、候補者と照らし合わせることが不可欠です。職務内容を具体的に示し、採用基準を明確化すれば、企業と候補者双方の期待値を揃えやすくなります。
企業文化や社風との不適合
新卒採用と同様、中途採用でも、企業文化・社風との不適合が採用ミスマッチの大きな原因です。候補者はこれまでの職場環境や経験をもとに、自分に合った働き方や価値観を持っています。
しかし入社後に実際の企業文化がその期待と大きく異なっていた場合、「居心地の悪さ」「ストレス」を強く感じ、結果的に早期離職につながる可能性が高まります。例えば「自由度の高いフラットな環境」を期待していたのに、実際は上下関係の厳しいトップダウン型の組織であれば、ギャップは大きくなるでしょう。
こうしたミスマッチを防ぐには、採用選考の段階で、企業文化や社風に関するリアルな情報を積極的に発信するのが重要です。
採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!
採用ミスマッチを未然に防ぐ対策

採用ミスマッチを防ぐためには、単に選考基準を厳しくするだけでは不十分です。以下、実践すべき具体的な対策を整理しつつ、採用ミスマッチを未然に防ぐ方法を詳しく解説します。
選考~入社までに行う施策
選考〜入社までに行うべきなのは、以下のような施策です。
- 採用基準を明確に提示する
- インターンシップ制度を導入する
- リファラル採用を取り入れる
- カジュアル面談を行う
- 適性テストを活用する
- 内定者フォローイベントを開催する
それぞれ詳しく解説します。
採用基準を明確に提示する
採用ミスマッチを防ぐための第一歩は、採用基準を明確に提示することです。基準が不明瞭なまま採用活動を進めると、企業と候補者の間で認識のズレが生じやすくなります。そのため、まずは自社で活躍している従業員の特性やスキルを具体的に分析し、求める人物像を設定しましょう。
例えば、コンピテンシーを基準に人物像を定める方法があります。コンピテンシーとは、すでに成果を上げている従業員の行動特性を抽出し、それを採用基準に落とし込むアプローチです。採用基準が上手く設定できれば、採用後の定着率向上にもつながります。
採用基準を明文化すると、候補者自身も「自分のスキルや志向性がこの企業に合致しているかどうか」を判断しやすくなります。結果として、企業と求職者双方が納得感を持ったマッチングが可能になり、ミスマッチによる早期離職のリスクを低減できます。
インターンシップ制度を導入する
採用ミスマッチを防ぐうえで、インターンシップ制度の導入もおすすめです。インターンシップには企業と候補者の双方にメリットがあります。
企業側にとっては、候補者が実際の業務にどのように取り組むかを観察でき、スキルや適性、潜在能力をより深く見極められます。一方で候補者にとっても、自身のスキルや志向が企業文化や仕事内容にフィットしているかを入社前に確認できる重要な機会となります。
特に長期間のインターンシップは、候補者の潜在的な特徴や、仕事への向き合い方を把握するのに便利です。単なる短期での体験にとどまらず、実際の業務を通じてお互いを理解すれば、双方にとって納得感のある採用につながります。
リファラル採用を取り入れる
リファラル採用の活用もミスマッチを防ぐ方法として有効です。リファラル採用とは、既存の従業員からの紹介によって人材を獲得する採用手法です。近年、多くの企業が導入を進めています。
リファラル採用の大きなメリットは、紹介者である従業員が、自社の文化や業務内容を深く理解している点です。企業の雰囲気や仕事内容に適した人材を紹介してもらえる可能性が高く、従来の公募採用よりもミスマッチが起こりにくい傾向があります。
紹介された候補者にとっても、入社前から紹介者を通じて企業の情報を手に入れやすくなります。社風や仕事内容に関するリアルな情報を把握しやすく、入社後のギャップが少なくなり、結果として定着率の向上につながります。
リファラル採用は、求人広告やエージェント利用に比べて採用コストを抑えられるという副次的効果も期待できます。「紹介する側」「紹介される側」双方にとってメリットがあり、採用の質を高める有効な手段です。
<関連記事> リファラル採用制度とは?導入メリットや手順・成功させるポイントなど詳しく解説
カジュアル面談を行う
カジュアル面談もおすすめの施策です。カジュアル面談とは、正式な選考プロセスから切り離された形で、企業と候補者が気軽に情報交換を行う場を指します。面接のように評価を目的としないため、候補者はリラックスした雰囲気で企業担当者と対話でき、疑問や不安を率直に質問しやすくなります。
企業側にとっても、カジュアル面談は、自社の魅力をダイレクトに伝える場として活用できます。会社説明会や求人票では伝えきれない職場の雰囲気や働き方を共有できるため、入社後のギャップを軽減しやすくなるでしょう。
さらに企業側は、カジュアル面談を通じて、候補者の人間性や価値観を理解できます。スキルや経歴だけでは見えにくい側面を把握し、自社の文化や働き方にフィットするかどうかをより的確に判断できるわけです。結果として、早期離職を防ぐのにつながります。
適性テストを活用する
適性テストを活用するのもよいでしょう。面接では、候補者の印象や受け答えに左右されやすく、短時間で多面的に人物像を把握するのが困難です。適性テストを導入すれば、候補者の適性やスキル、性格、価値観、さらには潜在能力までを客観的に評価できます。
適性テストにはさまざまな種類があります。例えば性格診断であれば、候補者の行動特性や価値観を把握でき、能力検査であれば論理的思考力などを測定できます。職務遂行能力を測るテストも、実際の業務パフォーマンスを予測するために便利です。こうしたテストを組み合わせれば、候補者が企業の求める人材像に合致しているかをより正確に見極められます。
複数の評価者による合議制の選考と組み合わせれば、1人の面接官の主観に偏らず、多角的な視点から候補者を評価できます。
内定者フォローイベントを開催する
採用ミスマッチを未然に防ぐためには、内定者フォローイベントの開催も重要な取り組みの1つです。内定承諾から入社までの期間は、求職者が将来への期待と同時に不安を抱えやすい時期でもあります。
入社前のタイミングでフォローを行うことで、不安を解消し、企業への理解度とエンゲージメントを高められます。具体的な取り組みとして挙げられるのは、内定者懇親会や従業員との交流会、現場見学、OJT研修、勉強会などです。
内定者にとっては「企業への理解が深まる」「同期や従業員とのつながりを早めに築ける」といったメリットがあります。一方で企業側にとっても、早期に内定者との信頼関係を構築できるため、内定辞退や入社後の早期離職を防ぎやすくなります。
内定者フォローイベントは、双方にとってプラスに働く仕組みであり、結果として採用ミスマッチの予防と定着率の向上につながる重要な施策です。
入社後に行う施策
採用プロセスを通じて候補者を適切に見極めることは大切ですが、それだけで採用ミスマッチを完全に防げるわけではありません。入社後のサポートが不十分であれば、せっかく採用した人材も「期待と違う」「相談できる環境がない」と感じ、早期離職につながる可能性が高まります。以下、入社した人材が安心して働き、企業の一員として成長していけるようにするための具体的な施策を解説します。
メンターによるサポートを行う
採用ミスマッチによる早期離職を防ぎ、従業員の定着を促すための手段の1つが、メンター制度の導入です。新人に対して、経験豊富な先輩従業員(メンター)が指導・相談役としてつくことで、業務面のサポートができます。
メンター制度の大きな特徴は、単なる業務指導にとどまらない点です。新人が抱えやすい職場での人間関係の悩みや、企業文化への適応に関する不安など、幅広い課題について相談できる環境を整えられます。「相談できる人がいない」という孤立感を防ぎ、定着率の向上につながります。
ミスマッチの兆候を早期に把握できるなど、企業にとってのメリットも大きいでしょう。問題が小さいうちに対応すれば、離職リスクを軽減しつつ、より円滑な育成・定着につなげられます。
定期的に面談を行う
入社後の従業員が安心して働き続けられる環境を整えるには、定期的な面談機会を確保するのが重要です。新しい環境や業務に慣れるまでの間、従業員は不安や悩みを抱えやすく、放置すると早期離職につながるリスクがあります。
上記のような状態を防ぐには、直属の上司や人事担当者が定期的に面談を行うのが効果的です。入社後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月といった、環境や役割に変化が起こりやすいタイミングで面談を設定すると、課題を早期に把握し、適切なフォローを行えます。
具体例として、1on1ミーティングがあります。短時間かつ高頻度のコミュニケーションは、従業員が抱える小さな不安や疑問をその場で解消しやすい形式です。継続的な対話を通じて従業員のエンゲージメントを高められれば、早期離職を未然に防ぎ、定着率の向上にも直結します。
キャリア志向をヒアリングする
採用ミスマッチによる早期離職を防ぐうえで、従業員本人のキャリア志向を継続的にヒアリングするのも重要です。たとえ現時点で従業員がミスマッチを感じていても、自分の希望が検討・反映されるのであれば、エンゲージメントの維持につながります。
前述の定期面談やキャリア面談の場では、次の観点を深掘りしましょう。
- 今後のキャリアプランとその理由・動機
- 現在の業務との一致点・乖離点、負荷や学習テーマ
- 伸ばしたいスキル・経験、挑戦したい役割
ミスマッチが見つかった場合でも、直ちに配置転換をするのは難しいかもしれません。その際は、難しい理由を丁寧に説明したうえで、代替案を本人と一緒に設計する姿勢が重要です。「声が届く」「成長に伴走してくれる」という実感は、働き続ける強い動機になります。
採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!
採用ミスマッチ防止の成功事例

不動産仲介事業/リフォーム事業/戸建住宅事業を軸に「くらしの総合商社」として様々なサービスを提供するフロンティアホールディングスでは、若手の早期離職を防ぎ、高いエンゲージメントを維持するために、「採用時の価値観の一致」に徹底的にこだわっています。経営理念への共感を前提に選考を設計し、社長自ら理念を語るセッションや、職場体験・合宿を通じて、会社との相性を深く確かめる機会を提供しています。
選考段階でミスマッチを排除することで、入社後の離職率は平均の3分の1以下という成果を上げています。加えて、内定後のフォローにも余念がありません。可能な内定者にはアルバイトとして実務を経験してもらい、電話営業や契約手続きの補助など、入社前から実践的な助走期間を設けています。
また、社長が候補者や内定者と直接関わり、食事の場を設けたり、1年目社員の様子をミーティングで確認したりと、一人ひとりを丁寧にフォロー。さらに、全社員で感謝を伝え合う「サンキューレター」文化も、内定者にまで開かれており、月間2万通を超えるメッセージが飛び交っています。入社前から従業員と内定者が自然につながり、社内の一体感を醸成する仕組みです。こうした一連の取り組みが実を結び、Great Place To Work® Institute Japanが発表する「働きがいのある会社」若手ランキングで、2023年から1位を獲得しています(2025年9月現在)。
特に注目する点は、経営陣が全施策に直接関与していることです。理念から人事施策、現場の風土づくりまで、すべてがつながっているため、表面的な「働きやすさ」ではなく、本質的な「働きがい」が生まれています。このような姿勢が、若手からの支持と組織の安定成長を同時に実現しているのです。
<関連記事> なぜ若手はこの会社で辞めないのか?3年連続1位の裏にある、リアルな実践策を独自取材
【ホワイトペーパー】若手が活躍する職場とは ~「働きがいのある会社」ランキング上位企業に学ぶ~
この資料では、若手ランキング企業の特徴を通じて、組織で若手がイキイキと活躍するためのポイントを解説し、「働きがいのある会社」ランキング上位に選出された企業の実際の取り組み事例を紹介します。
エンゲージメントサーベイを活用する

採用ミスマッチを未然に防ぎ、従業員の定着を促すには、組織の現状を客観的に把握する仕組みが欠かせません。その代表的な手法が、エンゲージメントサーベイです。従業員が企業に対して抱く「愛着」や「貢献意欲」を測定する調査であり、数値やコメントを通じて組織の健全性を可視化します。
エンゲージメントサーベイを活用すれば、「人間関係が合わなかった」「仕事内容の説明が不足していた」といった採用ミスマッチの原因を特定できます。こうしたデータは、採用段階の改善や入社後フォロー体制の強化など、具体的な対策を検討するうえで重要です。
エンゲージメントサーベイは、単発的に実施するのではなく、定期的に行うと効果的です。継続的にデータを収集すれば、施策の改善効果を検証できるだけでなく、組織全体の健康状態をモニタリングするツールとしても機能します。
<関連記事> 調査結果を「出して終わり」にしないために~エンゲージメント調査結果を組織の力に変える『納得感醸成』のポイント~
採用ミスマッチの理由を突き止めるならGPTWの「エンゲージメントサーベイ」

採用ミスマッチは、企業の生産性や定着率に大きな影響を与える課題です。その要因は「情報不足」や「相互理解の不足」などさまざまですが、いずれにせよ現状を客観的に把握するのが重要になります。
GPTWのエンゲージメントサーベイを活用すれば、従業員の「働きがい」「企業への愛着度」を定量的に測定でき、さらに自社の強みや改善が必要なポイントを明確にできます。データの積み重ねによって、採用ミスマッチの防止にもつながるかもしれません。
また、調査結果によっては「働きがい認定」の取得にもつながり、経営戦略や人材戦略の目標として設定できます。認定は、社外への信頼性を高めるだけでなく、従業員の誇りや定着意欲を高めるインナーブランディング効果も期待できます。
従業員が長く活躍できる組織をつくるために、まずはサーベイを活用し、得られた情報を基盤にした採用活動を進めてみてはいかがでしょうか。
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!