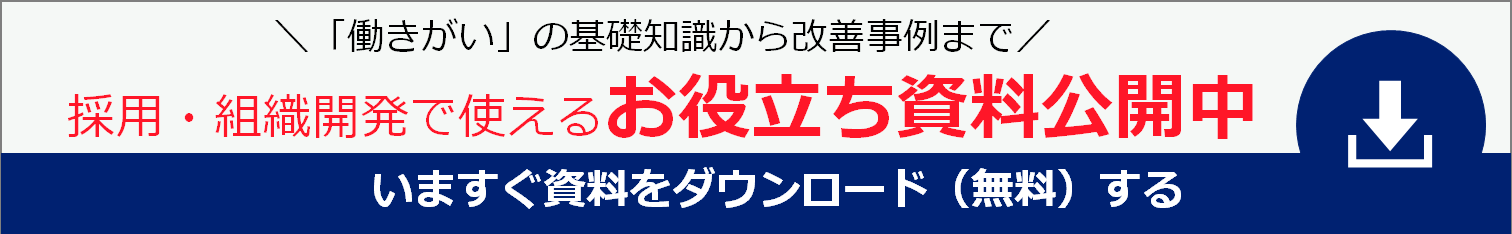人材流出がもたらすリスクと影響~なぜ人が辞めるのか?見逃しがちな組織の"ほころび
更新日 2025.09.192025.09.19コラム

「人材流出が止まらない」という状況は、多くの企業が直面する深刻な課題です。優秀な人材が退職する理由には、給与や待遇といった表面的な要因だけでなく、組織の内部に潜む見過ごされがちな「ほころび」が根本的な原因として存在することが少なくありません。
ここでは、なぜ人材流出が起こるのか、その具体的な理由と企業が抱えるリスク、そして人材流出を防ぐための効果的な対策について詳しく解説します。
そもそも人材流出とは

人材流出とは、企業で雇用契約を結んで働いていた人材が、定年や解雇以外の理由で他の企業へ転職したり、独立したりする現象を指します。通常、「流出」という言葉が示すように、企業にとっては優秀な人材を失うネガティブな出来事として捉えられます。
かつての日本では終身雇用制度が一般的であり、新卒で入社した企業で定年まで勤め上げることが主流でした。しかし、近年ではこの終身雇用制度が実質的に崩壊し、より良い労働条件やキャリアアップの機会、働きがいを求めて転職する人材が増えています。2019年には経団連も終身雇用制度の維持は困難であると明言。現代の企業は新たな雇用形態への対応を迫られています。このような背景のもと、人材流出は多くの企業にとって重要な経営課題の一つとなっているのです。
人材流出が止まらない原因

人材流出が止まらない企業には、組織内に問題を抱えています。理由は企業によってさまざまですが、多くの場合は職場環境への不満や将来への不安が根底にあります。これらの要因が複合的に作用することで、従業員が離職や転職を決断するケースが増えています。企業が人材流出を食い止めるためには、自社の状況を冷静に分析し、根本的な問題に対処することが不可欠です。以下では、人材流出につながる代表的な原因について解説します。
人間関係の問題
職場の人間関係は、人材流出に直結する大きな問題の一つです。上司や同僚との相性が合わない、チームに馴染めないといった状況は従業員にとって強いストレスとなり、退職を検討するきっかけとなります。人間関係が良好でない職場では、コミュニケーションが停滞し、業務の効率低下や孤立感の増大につながりやすくなります。とりわけ中小企業では、組織規模が小さいため、人間関係のこじれが業務全体に与える影響が大きい傾向があります。
また、近年普及しているリモートワークでも、新入社員や中途採用者が職場に溶け込みにくいという課題があり、人材流出の一因となるおそれが指摘されています。人間関係に関する不満は離職理由の中でも大きな割合を占めており、その改善は人材定着において極めて重要な課題といえます。
報酬や待遇への不満
給与や待遇への不満も、人材流出を引き起こす大きな要因です。担当している業務内容や責任の重さに比べて報酬が見合わない場合、従業員はモチベーションを失い、より良い条件を求めて転職を検討する傾向が強まります。特に若手社員にとっては、現状の待遇への満足度のほか、将来のキャリアへの期待感も重要です。将来的に給与上昇が見込めない職場環境では、早期に転職を検討するケースも少なくありません。
また、同業他社に比べて給与水準が低い場合や、物価上昇に応じた昇給がなされない場合も、不満が蓄積しやすくなります。残業代の未払いといった法的に問題のある職場が問題視されるのはもちろんですが、評価基準が不明確で昇給・昇格の仕組みが見えない場合も不満が高まります。公平性と透明性のある給与制度を整備し、適切な給与水準を維持することは、人材流出を防ぐための不可欠な取り組みといえます。
労働環境への不満
過重労働や劣悪な労働環境は、人材流出を加速させる深刻な問題です。長時間労働の常態化やサービス残業の横行、有給休暇が取得しにくい状況は、従業員の心身を疲弊させ、ワーク・ライフ・バランスを崩す原因となります。優秀な社員ほど多くの業務を任されやすく、過剰な負担を抱えることで退職に至るケースも少なくありません。
さらに、パワハラやセクハラが放置されている職場、非効率な業務プロセスが改善されない環境も従業員の不満を高めます。近年は働き方改革の浸透により、働きやすさや柔軟な勤務形態を重視する人が増えているため、労働条件が悪い企業は敬遠されます。リモートワークへの対応不足や柔軟な働き方が選べないことも、人材流出の大きな要因となります。こうした問題が放置されると、「ブラック企業」というレッテルを貼られ、採用面でも悪影響を及ぼす可能性があります。
【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】
エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。
企業文化との不一致
企業文化や社風との不一致も、人材流出の主要な要因の一つです。従業員が企業の価値観や行動規範に共感できない場合、居心地の悪さやモチベーションの低下につながります。風通しが悪く意見を言いにくい職場や、悪口や陰口が飛び交う環境では、従業員同士の信頼関係が築きにくく、早期離職を招きやすい傾向があります。実際に、Googleの研究では心理的安全性の高いチームほど離職率が低いことが明らかになっており、職場の雰囲気が人材定着に大きく影響することが実証されています。
企業文化や社風に上記のような問題がない場合でも安心はできません。近年は「自分らしく働きたい」という価値観を持つ人材が増加しており、企業文化が自分にとって合わないと感じれば、早々に転職を決断することも珍しくないのです。企業文化との不一致からの人材流出を防ぐには、まずは採用段階で候補者と企業文化のミスマッチを最小限に抑える努力を行うことが重要です。さらに、入社後も文化理解を促進し、共感を得られる環境を整備することが求められます。
<関連記事>
心理的安全性とは?高めるメリットや方法、働きがいとの関連について解説
キャリア形成への不安
キャリア形成に対する不安も、人材流出を引き起こす大きな要因です。従業員が自社内でキャリアパスを描けない、スキルアップや成長の機会が不足していると感じると、将来への不安を抱き、より成長できる環境を求めて転職を検討する傾向があります。
近年では、働き方改革により労働環境が改善された一方で、「ホワイトすぎる職場」が新たな課題として注目されています。職場が快適すぎる状態は、成長意欲の高い人材にとっては、ときに不満要因となります。たとえば、挑戦の機会が少ない職場や、難易度の低いプロジェクトばかり続く環境では、従業員のスキル向上が期待できません。AI技術の進歩により将来的に代替される可能性のある業務に従事している場合、中長期的なキャリア形成への不安が高まります。新しい知識や経験を積む機会を求める人材ほど、成長実感の得られない現状では満足できなくなります。
また、キャリアパスが不明瞭であったり、スキルが社内に限定されたりする場合、従業員は社外で経験を積もうと考えるようになります。近年では、副業や社外での活動を認める企業が増えており、これはキャリア形成の多様化と従業員の成長意欲に応える企業の取り組みの表れです。企業は従業員が自社内でどのように成長し、キャリアを築けるのかを具体的に示し、教育制度や能力開発の機会を提供することが、人材流出防止の鍵となります。
従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ
世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!
人材流出がもたらすリスクと影響

人材流出は、企業にとって多岐にわたる深刻なリスクと影響をもたらし、ときに経営全体に大きな損失を与える可能性があります。とくに優秀な人材の流出は、企業の成長や競争力に直接的なダメージを与えるだけでなく、残された組織全体の士気低下や採用活動の困難化など、負の連鎖を引き起こしかねません。以下では、人材流出が引き起こす代表的なリスクとその影響について解説します。
従業員の士気が低下する
人材流出が続くと、残された従業員の士気が著しく低下することが懸念されます。周囲の同僚が次々に退職していく状況を目の当たりにすると、「この会社に何か問題があるのではないか」という不信感を抱きやすくなります。
さらに、退職者の業務を引き継ぐことで残された従業員の負担が増し、長時間労働や過重労働が常態化する可能性も高まります。こうした状況はストレスや疲労の蓄積を招き、モチベーションの低下につながります。その結果、従業員エンゲージメントが下がり、生産性の低下を招くとともに、さらなる人材流出を誘発する悪循環に陥る危険性があります。離職率の上昇が見られる組織では、早期の対策が欠かせません。
知識の流出や顧客離れが起こりやすい
人材流出は、単なる人員の減少にとどまらず、企業にとって重要な知識や顧客基盤の喪失を引き起こします。
たとえば、長年企業に貢献してきた優秀な従業員が退職すると、業務を通じて培われたノウハウや専門知識の継承が失われる可能性があります。ベテラン社員がいなくなったため、小さなミスが発生しやすくなったり、顧客満足度が低下したりします。とりわけ、競合他社に転職した場合、相手企業にとっては即戦力となり、競争力を高める要因となるため、自社にとっては大きな損失となります。
また、退職者が特定の顧客との強い信頼関係を築いていた場合には、その顧客までもが自社から離れてしまう可能性があります。こうした知識や顧客の流出は、企業の事業継続や競争力維持に深刻な影響を与えるリスクがあるといえます。
採用経費の増加が懸念される
人材流出が止まらない企業では、退職者の穴を埋めるために新たな人材を採用する必要があり、その結果、採用経費が大幅に増加するという問題が生じます。求人広告の掲載費用、人材紹介会社への手数料、説明会や選考にかかる時間的コストなどは、企業にとって大きな負担となります。
また、短期間で離職者が出た場合には、それまで投資してきた教育・研修コストが無駄になるだけでなく、再び採用から教育までのプロセスを繰り返さなければならず、コストの損失はさらに拡大します。人材流出が頻発する企業では、常に採用活動に追われることになります。その結果、人事部門のリソースが不足し、本来注力すべき人材戦略や組織開発に手が回らなくなるリスクがあります。
企業イメージが悪化する恐れがある
人材流出が続くことは、企業のイメージ悪化につながる深刻なリスクです。離職率が高い企業は「働きにくい会社」というマイナスの印象を持たれやすく、採用活動や販売活動に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、インターネットの口コミやSNSでのネガティブな情報拡散は、新たな人材の応募を阻害する要因となります。とくに中小企業や地方企業においては、イメージの悪化が人材確保の困難さを一層助長する恐れがあります。
一方で、従業員の定着率が高い企業は「安心して働ける会社」として社会的評価を得やすく、採用面でも有利になります。逆に定着率の低さは、最悪の場合、企業存続に関わる大きなリスクとなり、倒産の引き金となる可能性すらあるのです。
<関連記事>
人材流出を止める5つの対策

人材流出を防ぐためには、原因を正しく把握したうえで、組織として具体的な対策を講じることが欠かせません。以下では、人材定着率を高めるために有効な5つの対策について解説します。
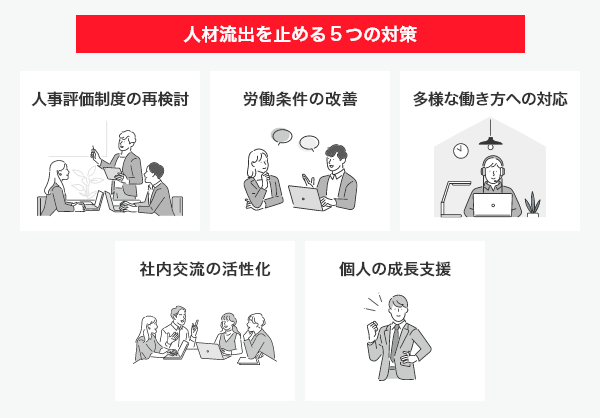
1. 人事評価制度の再検
人材流出を防ぐための効果的な方法の一つが、人事評価制度の再検討です。従業員が「自分の努力や成果が正当に評価されていない」と感じると、不満やモチベーション低下につながり、最終的には退職のきっかけとなる可能性があります。特に、現在の評価制度に対して従業員から不満の声が上がっている場合や、評価基準が曖昧で納得感が得られていない状況では、人事評価制度の見直しが大きな効果を発揮します。
具体的には、評価基準を明確にし、従業員が自身の目標と評価内容の関連性を理解できるようにすることが重要です。さらに、定期的なフィードバックの機会を設け、評価結果を丁寧に説明することも納得感を高める効果があります。昇給や昇格の基準を明確にすることで、従業員は将来的なキャリアや報酬の道筋をイメージしやすくなり、安心して働き続けることができます。こうした人事評価制度の見直しは、定着率向上に直結する重要な対策です。
2. 労働条件の改善
労働条件の改善は、人材流出を食い止めるための基本かつ重要な対策です。長時間労働やサービス残業、休日出勤の多さ、有給休暇の取りにくさは、従業員に大きな負担を与え、退職を招く大きな要因となります。
改善策としては、まず現状の労働時間や休暇取得状況を正確に把握し、過剰な残業を削減する取り組みを行うことが必要です。具体的には、勤怠管理システムの導入や業務プロセスの効率化、労働時間のコントロールなどが有効です。また、給与水準を適切に整備することも従業員の安心感につながります。労働条件を整えることは、従業員が長く安心して働ける環境を実現するうえで欠かせない取り組みです。
3. 多様な働き方への対応
近年はワーク・ライフ・バランスを重視する価値観が広がり、従業員は仕事と私生活の調和を求める傾向が強まっています。多様な働き方を導入することは、人材流出の予防につながります。
具体的には、フレックスタイム制やリモートワークの導入、育児や介護との両立を支援する制度の整備が挙げられます。また、副業を認めることで、従業員が社外でスキルを磨く機会を提供し、自己成長を支援することも有効です。中小企業や地方企業など、組織のあり方によってはリモートワークの導入が難しいところもあります。ただし、大きなコストをかけずとも、始業・終業時間の柔軟化、休憩時間の自由設定、有給休暇の時間単位取得、家族の行事に合わせた特別休暇制度など、従業員のニーズに応える制度は導入可能です。
多様な働き方への対応は、従業員の満足度や企業へのエンゲージメントを高めると同時に、優秀な人材の確保と維持につながる競争力強化の手段といえます。
<関連記事>
ワーク・ライフ・バランスとは?働き方の意味や定義・メリットや古いと言われる理由をわかりやすく解説
4. 社内交流の活性化
社内交流の活性化も、人材流出を防ぐうえで欠かせない取り組みです。特に、部署間の連携が少なく縦割り組織になっている職場や、リモートワークの普及により対面でのコミュニケーションが減少している職場では、この取り組みが大きな効果を発揮します。社内コミュニケーションが活発になれば、職場の雰囲気が改善され、従業員が孤立感や不満を感じにくくなります。
具体策としては、社内イベントや交流会の開催、部署横断的なプロジェクトの推進、メンター制度の導入、1on1ミーティングの定期実施などが挙げられます。こうした取り組みによって、従業員同士の信頼関係が深まり、組織全体の一体感が高まります。結果として職場に活気が生まれ、人材流出を抑制する効果が期待できます。
5. 個人の成長支援
従業員の成長を支援することは、人材流出を止めるための最も重要な対策の一つです。特に、若手社員や中堅社員から「成長実感が得られない」「キャリアパスが見えない」といった声が上がっている職場や、業務が定型化しており新しいスキルを身につける機会が少ない職場では、この取り組みが極めて重要になります。成長意欲の高い人材は、スキルアップやキャリアアップの機会を強く求めており、それが得られないと転職を検討しやすくなります。
企業が取り組むべき施策としては、キャリア開発支援の強化や研修プログラムの充実、資格取得支援制度の導入、社内公募制度による挑戦機会の提供などがあります。また、メンター制度を活用してキャリア相談の場を設けるなど、目標設定やフィードバックを通じて従業員が成長を実感できる仕組みを整えることも有効です。
企業が積極的に従業員の成長を支援することで、従業員は「自社でキャリアを築ける」と感じやすくなり、企業へのエンゲージメントが高まります。その結果、人材流出を防ぎ、長期的な組織の安定につながります。
<関連記事>
リスキリングとは?意味や導入のメリット、働きがいとの関係を解説
【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】
エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。
人材流出防止の取り組み事例

人材流出を防止するためには、原因を分析するだけでなく、他社の先進的な取り組みから学び、自社に合った施策を導入することが効果的です。実際に、多くの企業が従業員のモチベーション向上や職場環境の改善に取り組んでおり、こうした取り組みは人材定着の観点からも注目されています。ここでは、その具体的な事例を紹介します。
事例1:株式会社ディスコの「個人Will制度」
株式会社ディスコはGreat Place To Work® Institute Japanが発表する、「働きがいのある会社」ランキングに17年連続で選出(2025年9月時点)されるなど、高い従業員満足度を維持し続けている企業です。同社の特徴的な取り組みの一つが「個人Will制度」です。
この制度は、社内通貨「Will」を用いて従業員が仕事内容や協働相手を自由に選択できる仕組みで、管理会計の概念を個人レベルにまで落とし込んだものです。従業員は希望する仕事に手を挙げ、依頼者と合意が得られればその業務を担うことができ、成果に応じてWillを獲得します。獲得したWillは賞与の一部に反映されるため、従業員のモチベーション向上につながっています。
従来のように上司が一方的に仕事を割り振るのではなく、従業員同士の合意を基盤に業務が進むため、自然と「お互いに期待をかけ合い、コミットする関係性」が生まれます。こうした仕組みにより、社員間の信頼関係が強化され、働きがいを感じられる職場づくりに成功しています。
<関連記事>
「静かな退職」の予防策となり得る 株式会社ディスコの「個人Will制度」とは
事例2:DXCテクノロジー・ジャパンのタレントドリブン経営
DXCテクノロジー・ジャパンは「タレントドリブン」を掲げ、従業員の個性や強みを最大限に活かす取り組みを進めています。「Your COLOR面談」で一人ひとりの価値観を引き出し、カードゲーム形式のアクティブラーニングで自己理解と他者理解を促進。さらに調査結果を基に有志がタスクフォースを組織し、経営陣の情報発信強化など現場発の改善を継続しています。
こうした取り組みを通じ、従業員が主体的に会社づくりに関わる風土が定着し、誇りや挑戦心の向上につながりました。同社では「この会社で働いていて良かった」と従業員が感じられることがお客様へのサービス品質に直結するという考えのもと、従業員一人ひとりの強みややりたいことを活かせるよう柔軟な仕事のアサインを行っています。この結果、従業員の成長実感とお客様への価値提供が好循環を生み、タレントドリブン経営の基盤となっています。
<関連記事>
働きがい認定でタレントドリブン経営を加速! DXCテクノロジー・ジャパンの事例
事例3:株式会社U.Sの「働きがい」の定量化と組織づくり
ブランディングやクリエイティブを軸に企業変革を支援する株式会社U.Sは、従業員20名規模のスモールカンパニーながらGreat Place To Work® Institute Japanが行う「働きがいのある会社調査」に参画し、自社の強みと課題を定量的に可視化しました。調査を導入した背景には、メンバーのアイディア創出を支える環境づくりや、制度がきちんと受け止められているかを確認したいという課題がありました。
同社は早くからグレード制度や合宿型のオフサイトミーティングを導入し、評価の納得感やビジョン共有を重視してきました。また「インプット・アウトプット休暇」など独自制度で学びと刺激を支援しています。調査結果を通じて、これらの取り組みが従業員体験として浸透していることを確認でき、「仕事に行くのが楽しみ」というスコアの高さも得られました。
一方で「経営層の考えが見えにくい」という課題も明らかになったため、対話の場を強化する改善を実施しました。こうした継続的な組織改善の取り組みと、小規模ながら本気で制度設計を行う姿勢が、同社の人材定着と成長の基盤となっています。
<関連記事>
人が主役の変革支援企業が挑む「働きがい」の定量化と次の一手 株式会社U.Sの事例
【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選
「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。
従業員エンゲージメントを高めて人材流出を防ぐ「働きがい認定」

人材流出を防ぐためには、従業員エンゲージメントの向上が極めて重要です。従業員エンゲージメントとは、従業員が自社の目標や価値観に共感し、仕事に意欲的に取り組む状態を指します。この状態が高いほど、企業への愛着や貢献意欲が強まり、離職率の低下につながります。
しかし、エンゲージメント向上の取り組みは多岐にわたり、どこから手をつけるべきか迷う企業も少なくありません。近年では、そうした企業にとって有効な手法の一つとして「働きがい認定」が注目されています。認定を取得する過程で、企業は従業員の声を可視化し、組織の強みと課題を客観的に把握できます。それを基に改善を積み重ねることで、従業員が誇りを持てる職場環境が整い、エンゲージメントの向上へとつながります。
従業員エンゲージメントを高めることは、単に離職率を下げるだけでなく、生産性や創造性の向上、さらには企業の持続的な成長を支える基盤ともなります。エンゲージメントの高め方には終わりがなくゴールを定めにくいからこそ、取り組みの証として「働きがい認定」を一つの目標に据えて活動してみるのも有効です。認定の取得を通じて、自社の魅力を社内外に示すとともに、従業員が誇りを持って働ける環境を実現することが、人材流出を防ぐ最良の一手になるでしょう。
採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!